今回のお気に入りは、奇跡の図鑑です。
「昆虫学者、奇跡の図鑑を作る」という面白いタイトルの本を見つけました。
著者は丸山宗利さん。
丸山さんの著書は初めて読んだ「アリの巣の生きもの図鑑」のときから大のお気に入り。
本書を読み始める前に気になる事がひとつありました。
本書は「奇跡の図鑑」の制作記なので読んでいる最中に、あるいは読み終えたら、その図鑑を読みたくなることでしょう。
そのときのために本書を読み始める前に「奇跡の図鑑」を入手することにしました。
同じことを考えた人は多いはず。
2冊をセットで売るとは丸山さんは商売上手ですね!
なお本書でいう「奇跡の図鑑」とは「昆虫 新版(学研の図鑑LIVE)」のこと。
その図鑑が届いてから、心置きなく本書を読み始めました。
著者は図鑑制作にあたり、子どもたちのために“生きている昆虫”の写真で図鑑を作ろう!という目標を掲げました。
トンボは死後かなり変色すると聞いたことがあります。
変色するのはきっとトンボだけではないでしょう。
著者が生きた昆虫にこだわったのはきっととても大切なことなのだろうと思います。
さらに種の特徴を見やすいように虫の姿勢や、白バックでの撮影にもこだわりました。
でも生きた虫がじっとしている訳がありません。
理想的な姿勢をとらせるために撮影担当者たちが大変な思いをしたことがリアルにつづられています。
また卵からかえり幼虫時代を過ごし成虫になる時期はそれぞれの虫で決まっています。
その時期に合わせて北海道、沖縄・南西諸島、小笠原諸島まで手分けして昆虫採集と撮影を行いました。
わずか1年で絶滅危惧種を含む2800種を網羅したことができたのは、まさに「奇跡」といえます。
撮影担当者として選ばれたのは、全国各地の博物館の学芸員やネット上に素晴らしい昆虫写真を公開している若者たち。
著者と以前からの知り合いで秀でた技術を持っている方がほとんどとはいえ、図鑑にプロカメラマン以外の写真を使うとは前代未聞だったようです。
ネット社会となり、その人の技術が見えるようになったことが大きいと思います。
彼らは、著者から「図鑑づくりを手伝ってくれないか」と直接声をかけられ、二つ返事で協力を申し出たそうです。
そりゃそうでしょう。
昆虫好きの世界の大スター丸山さんから直接声をかけられることや、図鑑づくりに携われる機会など、彼らにとって「奇跡」以外の何物でもないのですから。
彼らの多くはいつどこに行けば目指す虫が採集できるかを熟知しているため、わずか1年で目標を超える種類を撮影しました。
編集者によると、1500種から2100種を掲載することを想定して企画をスタートしたそうですが、結果として7000種を超える昆虫写真が届き、2800種に絞り込むのがやっとだったそうです。
本書は丸山さんの視点による図鑑制作記ですが、主力となった方たち7名?のコラムを要所に配置することで、より真実に近づけています。
丸山さんの著述は読みやすいけれどドラマチックさに欠けます。
「奇跡の図鑑」制作がどれだけ困難な作業だったのかを知るには、コラムを飛ばさず読むことをおすすめします。
特に最後の2人のコラムは最高でした。
最大の協力者である伊丹市昆虫館学芸員・長島さんのコラムは感動して胸が熱くなりました。
昆虫写真がそろい、校正作業に入らなくてはならない時期になっても、「良い写真が撮れたので、差し替えてください!」といって次から次と写真が送られてきたそうです。
限られた時間の中でぎりぎりまで良い図鑑を作ろうとした彼らのエピソードにはとても感動しました。
このエピソードの落ちが、差し替えを一番申し出たのが総指揮官であるはずの著者・丸山さんだった、ということも感動的でした。
続いて長島さんは、この図鑑があまりに多くの人の力で作られたため、最高の図鑑であると言い切っても、自画自賛にならず、恥ずかしくないと書いています。
また制作陣がみな「最高の図鑑が出ます!」とSNSに投稿しまくる現象が起きたことにも感動しました。
制作当初、長島さんは丸山さんに向こう25年間は倒されない最高の図鑑を作りましょうと宣言していましたが、図鑑が完成した今は、才能あふれる若い人がたくさんいることを知ったため、10年後でもいいから彼らの手でさらに素晴らしい図鑑を作って欲しいという願いを書いています。
1年間、一緒に全力疾走した仲間たちへのエールに胸が熱くなりました。
最後のコラムは編集者の牧野さん。
制作チームの熱意に押され、差し替えをぎりぎりまで許した結果、書店への予告で2700種掲載とうたったにもかかわらず、実際は100種追加になったそうです。
牧野さんは、当初の予定よりも厚くなってしまった図鑑が少しでも軽くなるように製紙会社と新しい紙を開発したことを紹介していました。
この紙は、密度を落としたにもかかわらず、インクが表面に留まるという相反する機能を持っており、軽いのに正確に発色しました。
さらにページの角を丸くすることで、安全かつページをめくりやすくしました。
図鑑を開く子どもたちのために総力戦で臨んだことがよく判るエピソードです。
最後の最後に著者・丸山さんが書いたエピソードもまた感動的でした。
幼くして病のため病院を出られない子どもたちのために、移動博物館と称して昆虫標本をアクリルの箱に入れて持ち込んでいるそうです。
その時の子どもたちの輝く瞳に感動し、実寸大の生きた昆虫を満載した図鑑を制作したかったのだそうです。
どれもこれも涙腺のゆるくなった還暦ジジイの胸を打つエピソードばかり。
著者は他にも涙ぐましい努力を続けた制作協力者たちがたくさんいたことを本書で紹介しています。
最終的に300人を超えた制作協力者たちの力で「奇跡の図鑑」が世に出たことを改めて知りました。
これは粗末にできない貴重な図鑑です。
大切に鑑賞しなくてはなりません。
今は本書を副読本として、図鑑鑑賞をしています。
「昆虫学者、奇跡の図鑑を作る」という面白いタイトルの本を見つけました。
著者は丸山宗利さん。
丸山さんの著書は初めて読んだ「アリの巣の生きもの図鑑」のときから大のお気に入り。
本書を読み始める前に気になる事がひとつありました。
本書は「奇跡の図鑑」の制作記なので読んでいる最中に、あるいは読み終えたら、その図鑑を読みたくなることでしょう。
そのときのために本書を読み始める前に「奇跡の図鑑」を入手することにしました。
同じことを考えた人は多いはず。
2冊をセットで売るとは丸山さんは商売上手ですね!
なお本書でいう「奇跡の図鑑」とは「昆虫 新版(学研の図鑑LIVE)」のこと。
その図鑑が届いてから、心置きなく本書を読み始めました。
著者は図鑑制作にあたり、子どもたちのために“生きている昆虫”の写真で図鑑を作ろう!という目標を掲げました。
トンボは死後かなり変色すると聞いたことがあります。
変色するのはきっとトンボだけではないでしょう。
著者が生きた昆虫にこだわったのはきっととても大切なことなのだろうと思います。
さらに種の特徴を見やすいように虫の姿勢や、白バックでの撮影にもこだわりました。
でも生きた虫がじっとしている訳がありません。
理想的な姿勢をとらせるために撮影担当者たちが大変な思いをしたことがリアルにつづられています。
また卵からかえり幼虫時代を過ごし成虫になる時期はそれぞれの虫で決まっています。
その時期に合わせて北海道、沖縄・南西諸島、小笠原諸島まで手分けして昆虫採集と撮影を行いました。
わずか1年で絶滅危惧種を含む2800種を網羅したことができたのは、まさに「奇跡」といえます。
撮影担当者として選ばれたのは、全国各地の博物館の学芸員やネット上に素晴らしい昆虫写真を公開している若者たち。
著者と以前からの知り合いで秀でた技術を持っている方がほとんどとはいえ、図鑑にプロカメラマン以外の写真を使うとは前代未聞だったようです。
ネット社会となり、その人の技術が見えるようになったことが大きいと思います。
彼らは、著者から「図鑑づくりを手伝ってくれないか」と直接声をかけられ、二つ返事で協力を申し出たそうです。
そりゃそうでしょう。
昆虫好きの世界の大スター丸山さんから直接声をかけられることや、図鑑づくりに携われる機会など、彼らにとって「奇跡」以外の何物でもないのですから。
彼らの多くはいつどこに行けば目指す虫が採集できるかを熟知しているため、わずか1年で目標を超える種類を撮影しました。
編集者によると、1500種から2100種を掲載することを想定して企画をスタートしたそうですが、結果として7000種を超える昆虫写真が届き、2800種に絞り込むのがやっとだったそうです。
本書は丸山さんの視点による図鑑制作記ですが、主力となった方たち7名?のコラムを要所に配置することで、より真実に近づけています。
丸山さんの著述は読みやすいけれどドラマチックさに欠けます。
「奇跡の図鑑」制作がどれだけ困難な作業だったのかを知るには、コラムを飛ばさず読むことをおすすめします。
特に最後の2人のコラムは最高でした。
最大の協力者である伊丹市昆虫館学芸員・長島さんのコラムは感動して胸が熱くなりました。
昆虫写真がそろい、校正作業に入らなくてはならない時期になっても、「良い写真が撮れたので、差し替えてください!」といって次から次と写真が送られてきたそうです。
限られた時間の中でぎりぎりまで良い図鑑を作ろうとした彼らのエピソードにはとても感動しました。
このエピソードの落ちが、差し替えを一番申し出たのが総指揮官であるはずの著者・丸山さんだった、ということも感動的でした。
続いて長島さんは、この図鑑があまりに多くの人の力で作られたため、最高の図鑑であると言い切っても、自画自賛にならず、恥ずかしくないと書いています。
また制作陣がみな「最高の図鑑が出ます!」とSNSに投稿しまくる現象が起きたことにも感動しました。
制作当初、長島さんは丸山さんに向こう25年間は倒されない最高の図鑑を作りましょうと宣言していましたが、図鑑が完成した今は、才能あふれる若い人がたくさんいることを知ったため、10年後でもいいから彼らの手でさらに素晴らしい図鑑を作って欲しいという願いを書いています。
1年間、一緒に全力疾走した仲間たちへのエールに胸が熱くなりました。
最後のコラムは編集者の牧野さん。
制作チームの熱意に押され、差し替えをぎりぎりまで許した結果、書店への予告で2700種掲載とうたったにもかかわらず、実際は100種追加になったそうです。
牧野さんは、当初の予定よりも厚くなってしまった図鑑が少しでも軽くなるように製紙会社と新しい紙を開発したことを紹介していました。
この紙は、密度を落としたにもかかわらず、インクが表面に留まるという相反する機能を持っており、軽いのに正確に発色しました。
さらにページの角を丸くすることで、安全かつページをめくりやすくしました。
図鑑を開く子どもたちのために総力戦で臨んだことがよく判るエピソードです。
最後の最後に著者・丸山さんが書いたエピソードもまた感動的でした。
幼くして病のため病院を出られない子どもたちのために、移動博物館と称して昆虫標本をアクリルの箱に入れて持ち込んでいるそうです。
その時の子どもたちの輝く瞳に感動し、実寸大の生きた昆虫を満載した図鑑を制作したかったのだそうです。
どれもこれも涙腺のゆるくなった還暦ジジイの胸を打つエピソードばかり。
著者は他にも涙ぐましい努力を続けた制作協力者たちがたくさんいたことを本書で紹介しています。
最終的に300人を超えた制作協力者たちの力で「奇跡の図鑑」が世に出たことを改めて知りました。
これは粗末にできない貴重な図鑑です。
大切に鑑賞しなくてはなりません。
今は本書を副読本として、図鑑鑑賞をしています。











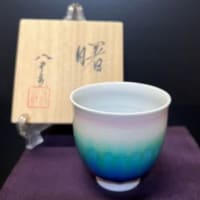






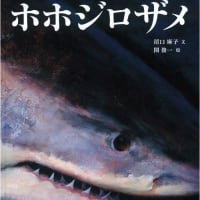
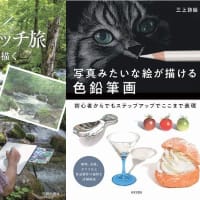





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます