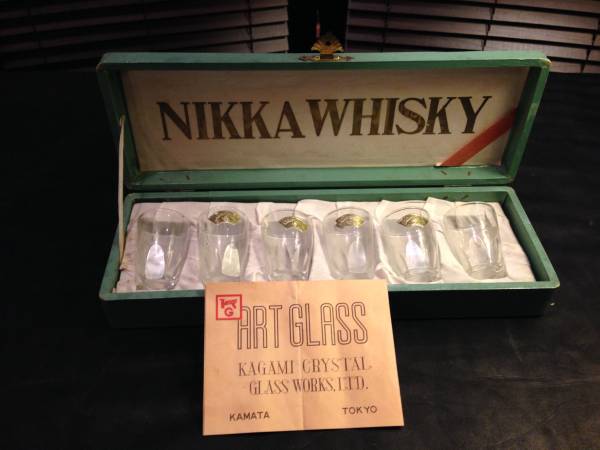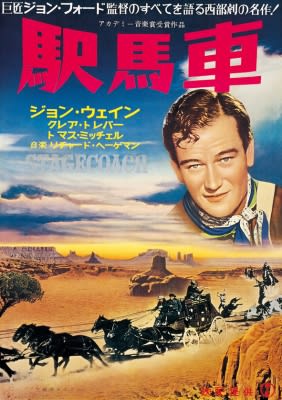今回のお気に入りは、「相模湾産後鰓類図譜」です。
「相模湾産後鰓類図譜」がネットオークションに出品されていました。
※「後鰓」は「こうさい」と読むそうで、ウミウシのことだそうです。
調べてみると本書は昭和天皇の最初の著書らしいということがわかり興味が湧き落札しました。
平成になって26年にもなりますが、自分の人生ではまだ昭和時代の方が長いためか、いまだにとっさに天皇というと昭和天皇の穏やかなお顔を思い浮かべます。(それなのに皇太子といわれると、現・皇太子のお顔を思い浮かべます)
昭和天皇が生物学に造詣が深いことは、晩年に粘菌の研究をしていたことで知っていましたが、ウミウシをはじめとした相模湾の動物相や、那須や下田須崎の植物について多くの著書を発表していたことは知りませんでした。
さすがに「学者天皇」「生物学天皇」といわれただけあります。
本書は皇居内生物学御研究所を編者として昭和24年9月に岩波書店から発行されました。
序文は編纂主任の理学博士 服部廣太郎が書いています。
その一部を抜粋してご紹介します。
・相模湾の生物相は南方系統の特色をも交えてすこぶる変化性に富んでいることは、つとに内外諸学者の等しく認めるところである。
・今上陛下が年々葉山御用邸に行幸になり、そこに御滞在の期間には常に相模湾頭の動植物を親しく御採集になって御研究の対象と遊ばすのが恒例となっている。
・御蒐集になった貴重な研究資料は著しき数に達し、その中には学問上未知の新種として諸専門家の名のもとに既に学会に発表された報文も少なからず存在する。
・この図譜に採択した種類は、すべて陛下が親しく御採集になって一旦御検討になったものを、当時生物学御研究所員だった故真田浩男と加藤四郎とが直ちに写生に着手し新鮮にして生きながらの色彩と容姿とを努めて精細に描写した原図と後鰓類の専攻家理学博士馬場菊太郎はこれに解説を付けたものとを併せて編纂した。
・収録した種類は陛下の御採集品のみに限定した関係上、諸学者の研究によって相模湾に産することがすでに知られている種類でも一切省略することにした。
・今回生物学御研究所の最初の試みとして、刊行したこの図譜
・特殊の一部類の種類のみをかくも相当に多数に網羅した図譜は、我邦のみならず欧米の諸国にあっても未だその類例をみないものである。
また(財)水産無脊椎動物研究所の機関誌「うみうし通信」創刊号に、日本貝類学会 波部忠重会長が本書に関して記述していますのでそれも抜粋してご紹介します。
・陛下は、馬場菊太郎の奉仕で「相模湾産後鰓類図譜」を発表された。
・陛下は昭和6年から底引網で相模湾の改訂生物の採集をはじめられた。
・御関心が深かったものにウミウシ類がある。陛下はこれらの形や美しさを愛されて、これらの生きているときの姿を所員によって写生図をつくらせた。
・昭和21年3月GHQ天然資源局長が生物学御研究所へ参上し、これらの美しい図を見て陛下の御研究の深いことに驚き、御発表になることをすすめた。
・馬場菊太郎がお手伝いして「相模湾産後鰓類図譜」が出版された。
・相模湾は珍奇な生物が多いことで世界に知られ、外国の学者も研究したが、陛下の御採集によって、一層相模湾の生物が解明されつつある。
うーん、陛下の著作と言い切るには弱いな・・・。
どちらかというと陛下が採集したウミウシ類の資料を学者が図鑑にしたと言った方が良いのではないかな・・・。
でも一般的には、陛下初の著書はこれ!といわれています。
悩んでいても仕方がないので、とりあえず本書が昭和天皇の初めての著書ということで納得して、ありがたく読むことにしました。
実際に読んでみたら、解説文は研究者が読むようにお堅くてとても読みづらかったです。
そのため解説文は、名前が気になったり、姿が美しかったりしたもののみ拾い読みしました。
本書は学者向けのまさに専門書。
残念ながら素人が楽しみにページをめくるような本ではありませんでした。
「学者天皇」の最初の著書として、世界に出しても恥ずかしくないようにと力が入っていたのではないでしょうか。
本書は、前半にウミウシ155種?の解説、後半に50ページ170枚の原色図版という構成。
本書の原色図版を期待して鑑賞しましたが、正直いって上手いのか下手なのかよくわかりませんでした。
色鮮やかだったり地味な色合いだったりというのは種類によって違うのでしょうが、どれも平面的。
どの図版も立体感が欠落しているように見えました。
ウミウシって相当凹凸があるはずなのに・・・。
本書の原色図版の原画は、国立科学博物館の企画展「日本の博物図譜」に出品されたそうですし、何と言っても皇居内生物学御研究所の所員が描いたのですから、自分に見る目が無いのでしょうか?
という訳で本書は原色図版を鑑賞すると上手に見えずにがっかりし、解説文を読むと堅すぎて面白くないという二重に残念な結果に終わりました。
きっと素人が手を出すべき本ではなかったということでしょう。
話は変わりますが、昭和天皇は忙しい公務の傍らウミウシや貝、ヒドロ虫などの海洋生物や、変形菌(粘菌)やキノコ類などを研究しており、貝類で110種類ほどの新種を発見し、他の生物も100種類近くの新種を発見したそうです。
以前、鳥類図版で有名なグールドのことを調べているときに「ジョン・グールド鳥類図譜総覧」という本に行き当たりました。
山階鳥類研究所および玉川大学教育博物館が所蔵するグールドの鳥類図譜全巻のリストをまとめたものですが、その著者は平成天皇の長女 清子様でした。
さらに山階鳥類研究所の創設者、山階芳麿も元皇族。
代々天皇家の方々って生物学に興味があるのですね。
最後に。
本書を読んだことは、生物学者としての昭和天皇を実感する良い機会になりました。
(雲の上の存在であることに違いはありませんが・・・)
陛下本人が実際に解説文などの文章を書いた著書がもしあるのなら読んでみたいな、と考えています。
「相模湾産後鰓類図譜」がネットオークションに出品されていました。
※「後鰓」は「こうさい」と読むそうで、ウミウシのことだそうです。
調べてみると本書は昭和天皇の最初の著書らしいということがわかり興味が湧き落札しました。
平成になって26年にもなりますが、自分の人生ではまだ昭和時代の方が長いためか、いまだにとっさに天皇というと昭和天皇の穏やかなお顔を思い浮かべます。(それなのに皇太子といわれると、現・皇太子のお顔を思い浮かべます)
昭和天皇が生物学に造詣が深いことは、晩年に粘菌の研究をしていたことで知っていましたが、ウミウシをはじめとした相模湾の動物相や、那須や下田須崎の植物について多くの著書を発表していたことは知りませんでした。
さすがに「学者天皇」「生物学天皇」といわれただけあります。
本書は皇居内生物学御研究所を編者として昭和24年9月に岩波書店から発行されました。
序文は編纂主任の理学博士 服部廣太郎が書いています。
その一部を抜粋してご紹介します。
・相模湾の生物相は南方系統の特色をも交えてすこぶる変化性に富んでいることは、つとに内外諸学者の等しく認めるところである。
・今上陛下が年々葉山御用邸に行幸になり、そこに御滞在の期間には常に相模湾頭の動植物を親しく御採集になって御研究の対象と遊ばすのが恒例となっている。
・御蒐集になった貴重な研究資料は著しき数に達し、その中には学問上未知の新種として諸専門家の名のもとに既に学会に発表された報文も少なからず存在する。
・この図譜に採択した種類は、すべて陛下が親しく御採集になって一旦御検討になったものを、当時生物学御研究所員だった故真田浩男と加藤四郎とが直ちに写生に着手し新鮮にして生きながらの色彩と容姿とを努めて精細に描写した原図と後鰓類の専攻家理学博士馬場菊太郎はこれに解説を付けたものとを併せて編纂した。
・収録した種類は陛下の御採集品のみに限定した関係上、諸学者の研究によって相模湾に産することがすでに知られている種類でも一切省略することにした。
・今回生物学御研究所の最初の試みとして、刊行したこの図譜
・特殊の一部類の種類のみをかくも相当に多数に網羅した図譜は、我邦のみならず欧米の諸国にあっても未だその類例をみないものである。
また(財)水産無脊椎動物研究所の機関誌「うみうし通信」創刊号に、日本貝類学会 波部忠重会長が本書に関して記述していますのでそれも抜粋してご紹介します。
・陛下は、馬場菊太郎の奉仕で「相模湾産後鰓類図譜」を発表された。
・陛下は昭和6年から底引網で相模湾の改訂生物の採集をはじめられた。
・御関心が深かったものにウミウシ類がある。陛下はこれらの形や美しさを愛されて、これらの生きているときの姿を所員によって写生図をつくらせた。
・昭和21年3月GHQ天然資源局長が生物学御研究所へ参上し、これらの美しい図を見て陛下の御研究の深いことに驚き、御発表になることをすすめた。
・馬場菊太郎がお手伝いして「相模湾産後鰓類図譜」が出版された。
・相模湾は珍奇な生物が多いことで世界に知られ、外国の学者も研究したが、陛下の御採集によって、一層相模湾の生物が解明されつつある。
うーん、陛下の著作と言い切るには弱いな・・・。
どちらかというと陛下が採集したウミウシ類の資料を学者が図鑑にしたと言った方が良いのではないかな・・・。
でも一般的には、陛下初の著書はこれ!といわれています。
悩んでいても仕方がないので、とりあえず本書が昭和天皇の初めての著書ということで納得して、ありがたく読むことにしました。
実際に読んでみたら、解説文は研究者が読むようにお堅くてとても読みづらかったです。
そのため解説文は、名前が気になったり、姿が美しかったりしたもののみ拾い読みしました。
本書は学者向けのまさに専門書。
残念ながら素人が楽しみにページをめくるような本ではありませんでした。
「学者天皇」の最初の著書として、世界に出しても恥ずかしくないようにと力が入っていたのではないでしょうか。
本書は、前半にウミウシ155種?の解説、後半に50ページ170枚の原色図版という構成。
本書の原色図版を期待して鑑賞しましたが、正直いって上手いのか下手なのかよくわかりませんでした。
色鮮やかだったり地味な色合いだったりというのは種類によって違うのでしょうが、どれも平面的。
どの図版も立体感が欠落しているように見えました。
ウミウシって相当凹凸があるはずなのに・・・。
本書の原色図版の原画は、国立科学博物館の企画展「日本の博物図譜」に出品されたそうですし、何と言っても皇居内生物学御研究所の所員が描いたのですから、自分に見る目が無いのでしょうか?
という訳で本書は原色図版を鑑賞すると上手に見えずにがっかりし、解説文を読むと堅すぎて面白くないという二重に残念な結果に終わりました。
きっと素人が手を出すべき本ではなかったということでしょう。
話は変わりますが、昭和天皇は忙しい公務の傍らウミウシや貝、ヒドロ虫などの海洋生物や、変形菌(粘菌)やキノコ類などを研究しており、貝類で110種類ほどの新種を発見し、他の生物も100種類近くの新種を発見したそうです。
以前、鳥類図版で有名なグールドのことを調べているときに「ジョン・グールド鳥類図譜総覧」という本に行き当たりました。
山階鳥類研究所および玉川大学教育博物館が所蔵するグールドの鳥類図譜全巻のリストをまとめたものですが、その著者は平成天皇の長女 清子様でした。
さらに山階鳥類研究所の創設者、山階芳麿も元皇族。
代々天皇家の方々って生物学に興味があるのですね。
最後に。
本書を読んだことは、生物学者としての昭和天皇を実感する良い機会になりました。
(雲の上の存在であることに違いはありませんが・・・)
陛下本人が実際に解説文などの文章を書いた著書がもしあるのなら読んでみたいな、と考えています。