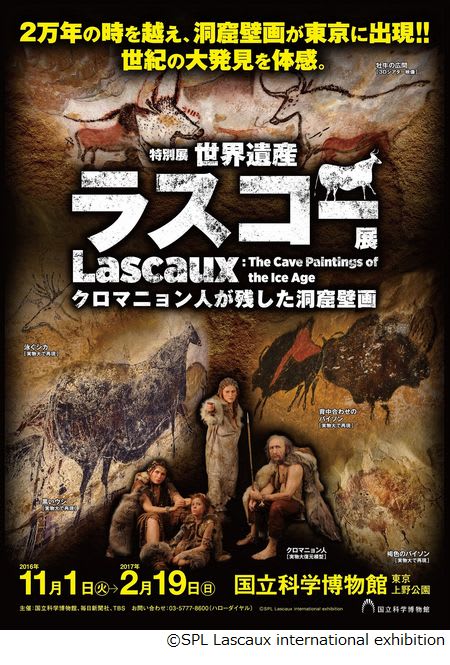今回のお気に入りは、凍原です。
桜木紫乃の「凍原 北海道警釧路方面本部刑事第一課・松崎比呂」を読みました。
柴咲コウ主演のドラマ「氷の轍(わだち)」が本書の続編らしいと聞き、予習を兼ねて、といったところです。
前に葉室麟が北海道新聞に連載している「影ぞ恋しき」がシリーズ第3巻ということを知り、途中で前2巻を読んで、登場人物の関係がようやくわかった、ということがあったものですから。
ちなみにネットで「氷の轍」をチェックしたら「凍原」とは主人公の名前が違いました。
釧路が舞台ということと脇役のベテラン刑事が共通しているだけかもしれません。
今のところ「続編」というのは、?マークです。
AMAZONの内容紹介を引用します。
=====
少女は、刑事にならねばならなかった。
1992年7月、北海道釧路市内の小学校に通う水谷貢という少年が行方不明になった。
両親、警察関係者、地元住民の捜索も実らず少年は帰ってこなかった。
最後に姿を目撃した同級生の杉村純少年によると、貢少年は湿原のほうへ向かっていったという。
それから17年、貢の姉・松崎比呂は刑事となって札幌から釧路の街に帰ってきた。
その直後、釧路湿原で他殺死体が発見される。
被害者は、会社員・鈴木洋介34歳。
彼は自身の青い目を隠すため、常にカラーコンタクトをしていた。
比呂は先輩刑事である片桐周平と鈴木洋介のルーツを辿るように捜査を進めてゆく。
事件には、混乱の時代を樺太、留萌、札幌で生き抜いた女の一生が、大きく関係していた。
『起終点駅(ターミナル)』で大ブレイク!
いま最注目の著者唯一の長編ミステリーを完全改稿。
待望の文庫化!
=====
「混乱の時代を樺太、留萌、札幌で生き抜いた女の一生」を描くパートが、かなりのウエイトを占めていました。
被害者が彼女の孫ですからそれは自然でしょうが、そこに主人公の弟の行方不明事件が関わってきます。
そして最後のドンデン返し。
二つの事件の陰にはもう一つの事件が隠されていたのです!
一般的なミステリー小説では、第3の事件までも明らかにして幕を閉じるのでしょうが、本書は違いました。
樺太、室蘭、釧路で懸命に生きた名も無き女の一生を静かにフェイドアウトさせます。
人生の最期くらい静かに送らせてあげたい。
著者のそんな思いに読者も納得したのではないでしょうか。
本書は、個性豊かな登場人物たちが織りなすドラマであり、美しい釧路湿原にある染色工房が舞台。
こちらも映像化が望まれる作品でした。
桜木紫乃の「凍原 北海道警釧路方面本部刑事第一課・松崎比呂」を読みました。
柴咲コウ主演のドラマ「氷の轍(わだち)」が本書の続編らしいと聞き、予習を兼ねて、といったところです。
前に葉室麟が北海道新聞に連載している「影ぞ恋しき」がシリーズ第3巻ということを知り、途中で前2巻を読んで、登場人物の関係がようやくわかった、ということがあったものですから。
ちなみにネットで「氷の轍」をチェックしたら「凍原」とは主人公の名前が違いました。
釧路が舞台ということと脇役のベテラン刑事が共通しているだけかもしれません。
今のところ「続編」というのは、?マークです。
AMAZONの内容紹介を引用します。
=====
少女は、刑事にならねばならなかった。
1992年7月、北海道釧路市内の小学校に通う水谷貢という少年が行方不明になった。
両親、警察関係者、地元住民の捜索も実らず少年は帰ってこなかった。
最後に姿を目撃した同級生の杉村純少年によると、貢少年は湿原のほうへ向かっていったという。
それから17年、貢の姉・松崎比呂は刑事となって札幌から釧路の街に帰ってきた。
その直後、釧路湿原で他殺死体が発見される。
被害者は、会社員・鈴木洋介34歳。
彼は自身の青い目を隠すため、常にカラーコンタクトをしていた。
比呂は先輩刑事である片桐周平と鈴木洋介のルーツを辿るように捜査を進めてゆく。
事件には、混乱の時代を樺太、留萌、札幌で生き抜いた女の一生が、大きく関係していた。
『起終点駅(ターミナル)』で大ブレイク!
いま最注目の著者唯一の長編ミステリーを完全改稿。
待望の文庫化!
=====
「混乱の時代を樺太、留萌、札幌で生き抜いた女の一生」を描くパートが、かなりのウエイトを占めていました。
被害者が彼女の孫ですからそれは自然でしょうが、そこに主人公の弟の行方不明事件が関わってきます。
そして最後のドンデン返し。
二つの事件の陰にはもう一つの事件が隠されていたのです!
一般的なミステリー小説では、第3の事件までも明らかにして幕を閉じるのでしょうが、本書は違いました。
樺太、室蘭、釧路で懸命に生きた名も無き女の一生を静かにフェイドアウトさせます。
人生の最期くらい静かに送らせてあげたい。
著者のそんな思いに読者も納得したのではないでしょうか。
本書は、個性豊かな登場人物たちが織りなすドラマであり、美しい釧路湿原にある染色工房が舞台。
こちらも映像化が望まれる作品でした。