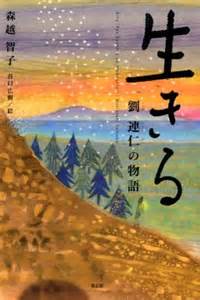
『生きる 劉連仁の物語』(森越智子著)
また、泣かずにはおれない本に巡り会った。第62回青少年読書感想文全国コンクールの中学校部門の課題図書『生きる 劉連仁の物語』である。事件の概略はよく知っていたが、たくさんの本が出ているにもかかわらず、ちゃんと読んだことはなかった。
強制労働で
事件の発端は1944年9月の中国山東省で日本軍によって拉致され、北海道まで連行され、昭和炭坑明治鉱業所には200人が配分された。劉連仁さんたちは苛酷な労働を強いられ、敗戦までの1年に満たない間に、9人が死亡し、179人がけがを負い、280人が病気に罹った。敗戦で186人が生きて帰ることができた。
余りに過酷で不当な強制労働に、逃亡者が続出したが、いつも捉まっては連れ戻され、見せしめのリンチを受けた。劉連仁さんは雪解けを待ち、7月に脱走し、故郷をめざした。すでに脱走していた4人と合流し、つらい逃亡生活が始まった。食べ物といえば、野ニラ(のびる)と山白菜だけであり、「空腹に目がくらみ、獣に怯え、雨に凍え、このままではどこかに行き着くどころか、その前にのたれ死ぬかもしれない…思った以上に山の逃亡が厳しいことを、劉連仁は悟っていた…」。
道がある限り前へ
13日目に5人は山を下りて、はたけの作物を食べたために、捜索隊が組織され、2人が捉まってしまった。3人での逃亡生活が始まり、「道がある限り前へ」と心を固めて、留萌の海岸から北上して、2カ月目には稚内にたどり着いた。
2度目の冬を迎えるために、3人は穴を掘り、食べ物を貯えた。雪が降り、すべてが凍り付く北海道の冬。1日1人あたり、大根1片、ジャガイモ1個、昆布少々で、冬眠するように長い冬を耐えた。
1946年4月、発見され2人が捉まり、劉連仁だけになった。劉連仁は火(マッチ)と鍋を盗み、村を離れ、山に向かった。「たぶんここには二度と来ることはないだろう。生きのびるためには、決して同じ道を戻ってはならない。決して同じところにとどまってはならない」と心に決めて、それから12年間、孤独な山の生活は1958年2月に発見されるまでつづいた。
日本政府の態度
雪におおわれた穴のなかで、息絶え絶えの劉連仁が発見された。「長い苦しみが終わったばかりの劉さんをもう一度傷つけることが起こりました。それは苛酷な強制労働に耐えかねて炭坑を逃げ出し、逃亡し続けた劉さんを、日本政府は『不法入国者』『不法残留』の疑いのある者と見なしたことでした」。官房長官は「劉連仁は労工協会の契約で日本に来た」などと言って、強制連行の事実を認めようとしなかった。
1996年劉連仁さんは東京地裁に提訴し、勝訴を勝ち取ったが、東京高裁は「国家無答責の法理」を適用して、敗訴し、2007年最高裁は上告を棄却した。何という理不尽な対応だろう。劉連仁さんは2000年9月に87歳で亡くなった。
学ぶべきこと
著者は「戦争は人間に『ほんとうの自分』というものを、無理やり捨てさせる。別の皮を被らされ、心にある良心も、誰かに向けるやさしさも、人間らしさのすべてを、自分という存在そのものを捨てさせる。そして、そのことをいったん受け入れてしまったら、最後、濁流に押し流されたように引き返せなくなる」と書いている。
『生きる 劉連仁の物語』から学ぶべきか。安倍内閣は特定秘密保護法、集団的自衛権、戦争法を手にしている。そして両院で3分の2を占めた改憲派は憲法9条を改正して、まさに戦争をする国に衣替えしようとしてる。私たちの決断と実行が問われているのではないか。
また、泣かずにはおれない本に巡り会った。第62回青少年読書感想文全国コンクールの中学校部門の課題図書『生きる 劉連仁の物語』である。事件の概略はよく知っていたが、たくさんの本が出ているにもかかわらず、ちゃんと読んだことはなかった。
強制労働で
事件の発端は1944年9月の中国山東省で日本軍によって拉致され、北海道まで連行され、昭和炭坑明治鉱業所には200人が配分された。劉連仁さんたちは苛酷な労働を強いられ、敗戦までの1年に満たない間に、9人が死亡し、179人がけがを負い、280人が病気に罹った。敗戦で186人が生きて帰ることができた。
余りに過酷で不当な強制労働に、逃亡者が続出したが、いつも捉まっては連れ戻され、見せしめのリンチを受けた。劉連仁さんは雪解けを待ち、7月に脱走し、故郷をめざした。すでに脱走していた4人と合流し、つらい逃亡生活が始まった。食べ物といえば、野ニラ(のびる)と山白菜だけであり、「空腹に目がくらみ、獣に怯え、雨に凍え、このままではどこかに行き着くどころか、その前にのたれ死ぬかもしれない…思った以上に山の逃亡が厳しいことを、劉連仁は悟っていた…」。
道がある限り前へ
13日目に5人は山を下りて、はたけの作物を食べたために、捜索隊が組織され、2人が捉まってしまった。3人での逃亡生活が始まり、「道がある限り前へ」と心を固めて、留萌の海岸から北上して、2カ月目には稚内にたどり着いた。
2度目の冬を迎えるために、3人は穴を掘り、食べ物を貯えた。雪が降り、すべてが凍り付く北海道の冬。1日1人あたり、大根1片、ジャガイモ1個、昆布少々で、冬眠するように長い冬を耐えた。
1946年4月、発見され2人が捉まり、劉連仁だけになった。劉連仁は火(マッチ)と鍋を盗み、村を離れ、山に向かった。「たぶんここには二度と来ることはないだろう。生きのびるためには、決して同じ道を戻ってはならない。決して同じところにとどまってはならない」と心に決めて、それから12年間、孤独な山の生活は1958年2月に発見されるまでつづいた。
日本政府の態度
雪におおわれた穴のなかで、息絶え絶えの劉連仁が発見された。「長い苦しみが終わったばかりの劉さんをもう一度傷つけることが起こりました。それは苛酷な強制労働に耐えかねて炭坑を逃げ出し、逃亡し続けた劉さんを、日本政府は『不法入国者』『不法残留』の疑いのある者と見なしたことでした」。官房長官は「劉連仁は労工協会の契約で日本に来た」などと言って、強制連行の事実を認めようとしなかった。
1996年劉連仁さんは東京地裁に提訴し、勝訴を勝ち取ったが、東京高裁は「国家無答責の法理」を適用して、敗訴し、2007年最高裁は上告を棄却した。何という理不尽な対応だろう。劉連仁さんは2000年9月に87歳で亡くなった。
学ぶべきこと
著者は「戦争は人間に『ほんとうの自分』というものを、無理やり捨てさせる。別の皮を被らされ、心にある良心も、誰かに向けるやさしさも、人間らしさのすべてを、自分という存在そのものを捨てさせる。そして、そのことをいったん受け入れてしまったら、最後、濁流に押し流されたように引き返せなくなる」と書いている。
『生きる 劉連仁の物語』から学ぶべきか。安倍内閣は特定秘密保護法、集団的自衛権、戦争法を手にしている。そして両院で3分の2を占めた改憲派は憲法9条を改正して、まさに戦争をする国に衣替えしようとしてる。私たちの決断と実行が問われているのではないか。























