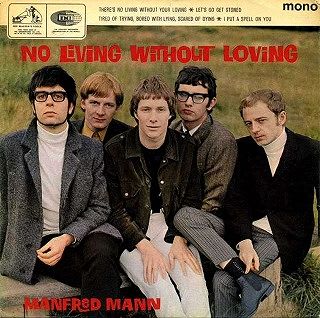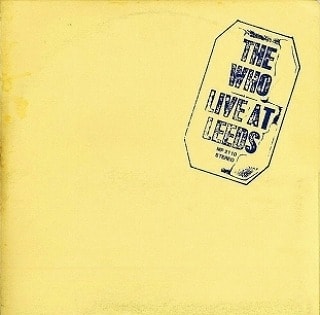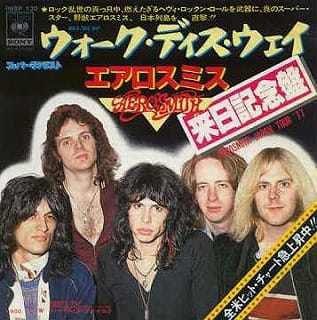■Sugar Sugar / The Archies (RCA / 日本ビクター)
この年度末になって、実態の無い会社に振り回されて難儀しておりますが、これが大衆芸能の世界では意外と歓迎されてきた歴史は無視出来ないでしょう。
特に音楽業界ではレコードという「音」だけで勝負する歌手やグループが確かにあって、全くコンサートライプをやらずに通した後期ビートルズは特異な存在かもしれませんが、他にもニルソンなんていう奇特な人もいましたですね。
で、本日ご紹介のアーチーズは、なんとアニメの中のバンドでした。
それを仕掛けたのはアメリカ音楽業界の大立者だったドン・カシューナというプロデューサーで、実はモンキーズで大成功したプロジェクトを引き継いだのが、アーチーズだったのです。
もちろん自我に目覚めたモンキーズに逃げられた後の二番煎じではありますが、モンキーズが実在のメンバーを使った、言わば「実写」だったのに対し、アーチーズは最初っから「アニメ」の中の架空のバンドですから、完全にプロデューサーの意のままに歌って活躍出来るんですねぇ~。
そしてテレビやコミック雑誌の連載に登場するアーチーズは、ジャケットどおりのキャラクターで毎回、あれやこれやのドタバタを演じ、バンドを組んで楽しく歌うという設定でしたから、直ぐに「第二のモンキーズ」として売り出され、一番の目的だったレコードセールスに結びつける戦略は見事に成功へと昇り始めたのです。
それが昭和44(1969)年に全米チャートのトップにランクされ、我国でもラジオから流れまくって大ヒットした「Sugar Sugar」に代表されるのですが、実際、調子良くてウキウキするリズムと明るいメロディ、お気楽優先主義の歌とコーラスは、例えば1910フルーツガム・カンパニーの「Simon Says」に代表される、所謂「バブルガム」と呼ばれた「お子様向けのポップス」でありながら、そのサウンド作りの完璧さは決して侮れる世界ではありません。
曲を書いたのはジェフ・バリーとアンディ・キムのコンビですが、まずジェフ・バリーと言えば1960年代初頭から妻のエリー・グリニッチと共作で多くのヒットを生み出したソングライターの偉人! 例えばロネッツの「あたのベイビー / Be My Baby」、クリスタルズの「ハイ・ロン・ロン / Da Doo Ron Ron」、ディキシー・カップスの「涙のチャペル / Chapel Of Love」、トミー・ジェイムズの「Hanky Panky」等々、キリが無いほどですが、そのミソは弾けるリズムと「泣き」を含んだ覚えやすいメロディのコンビーションだと思います。
一方、アンディ・キムは当時のジェフ・バリーが子飼のシンガーソングライターとして、既に幾つかの小ヒットを放っていた実力派ということで、まさに業界の裏方でありながら、何が売れるかを実践的に知っていたことが強みでしょう。
そこで肝心のアーチーズですが、これを実際に歌っていたのはロン・ダンテというセッションシンガーで、この人は影武者的に様々な歌手やグループの実質的な「顔」になっていたポップス界の証人のひとり! アーチーズ以外でも、エイス・デイやカフ・リンクス等々での仕事はバブルガム~ソフトロックのファンによって広く認知されていると思います。
もちろんバックの演奏はドン・カシューナが御用達の有能スタジオミュージシャンということは、つまり初期のモンキーズと同じ味わいが濃厚に楽しめるのです。
ちなみにアーチーズのアニメは日本でも放送されていたと思うのですが、個人的にはあまり記憶にありませんし、残念ながら、そういうところから当時の音楽ファンには軽視され、特に我国ではそれが顕著でしたから、残された音源やアルバムはきちんと聴かれたことが無いでしょう。サイケおやじにしても、このシングル盤はリアルタイムで買っていたものの、その他の楽曲演奏については完全に後追いでした。
しかし音楽業界の仕組みや掟を知るにつれ、このアーチーズをきっかけに更なるポップス天国へと導かれたのは幸いでした。
そこで冒頭の話に戻れば、現実的に実態が無くとも合法的に利潤を追求出来れば、例え難儀したとしても結果オーライ♪♪~♪
それが本日の気分として、このシングル盤を楽しんいるのでした。