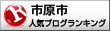今、市原市が災害対策として力を入れているのが、共助や自助のチカラを高める取り組み。
今年の2月から6月にかけて6回にわたって「いちはら防災100人会議」を開き、先日も「地区防災計画キックオフミーティング」を開催。約100名の市民が計画の策定に向けた基礎知識を学びました。

地区防災計画は行政が作る計画ではなく、およそ小学校区単位という身近な地域で住民同士が作る、オリジナルの「共助の計画」です。
お馴染みの跡見学園女子大学・鍵屋一先生による講演の後は、ワールドカフェ方式のワークショップ。
「一人暮らしで車いす生活のお年寄りがご近所にいます。災害時にお年寄りの命を守り、命をつなぐためには何をしたらよいでしょうか?」
とうお題について、グループごとに考えをまとめました。

最後に全員がテーブルを回って「イイネ!」と思うアイディアにシールをペタン。
私も参加しました(^.^)。

今後市原市では、計画の策定を希望する地域を募集して、モデル的に進めていく予定です。
地域の共助のチカラが、少しずつ形になろうとしています。
今年の2月から6月にかけて6回にわたって「いちはら防災100人会議」を開き、先日も「地区防災計画キックオフミーティング」を開催。約100名の市民が計画の策定に向けた基礎知識を学びました。

地区防災計画は行政が作る計画ではなく、およそ小学校区単位という身近な地域で住民同士が作る、オリジナルの「共助の計画」です。
お馴染みの跡見学園女子大学・鍵屋一先生による講演の後は、ワールドカフェ方式のワークショップ。
「一人暮らしで車いす生活のお年寄りがご近所にいます。災害時にお年寄りの命を守り、命をつなぐためには何をしたらよいでしょうか?」
とうお題について、グループごとに考えをまとめました。

最後に全員がテーブルを回って「イイネ!」と思うアイディアにシールをペタン。
私も参加しました(^.^)。

今後市原市では、計画の策定を希望する地域を募集して、モデル的に進めていく予定です。
地域の共助のチカラが、少しずつ形になろうとしています。