vol.1から読んでね ★
さて 去年の春ごろから仲良しになった団塊シティーオヤジたち。その中のまとめ役オジは大学もなぜか二つ卒業していて 某所で教鞭をとり文筆もしているという文化度の高いオジである。
当然かなりの読書家である。
そのオジとひょんなことから本の話で盛り上がった。E・ケストナーの話だった。
ワタシの幼少の頃、かなり好きだった児童文学者である。
ワタクシ今まで生きてきて 男性と「飛ぶ教室」について盛り上がったのは初めてであった。あちらもそうだったらしい。
以前も書いたけど まったく利害関係もなく もちろん恋愛感情もない異性友達と昔読んだ本の話ができるというのは新鮮な体験であった。
そこでそのオジと昔読んだ本の話から、さらに今読んでいる本の話にもなった。日本の小説部門では三浦しおん氏の「仏果を得ず」 山本兼一氏の「利休にたずねよ」偶然最近読んで良いと思った本の趣味も一致した。
 ← これも実におもしろい
← これも実におもしろい
世の中には数多の本が出ているのに ここまで趣味が一致するのは珍しいことである。
ところが、私が「その人のは読んだことないですよ」と言った作家。そのことでオジは大変残念がった。「局さん 読んでないんだ ぜひ読んでみて」と
「は~い じゃ 今度買うね」と言ったら 「あっ いいよ買わなくて ちょっと待ってて」と言われた。
そしたらこのほど本の宅配便が送られてきた。ご丁寧に読む順序までレクチャーしてある。

百田さんを知らないのは不勉強であった。こちらを読んでくださる方の中には愛読している方も多いと思う。
ちょうどこのたびの胃腸風邪ですべての予定をキャンセルして家にいなくてはならなかったこの二日、スポーツドリンクとオジがくれた本を枕元に置いて ひたすら読書にふけったのであった。
まだ 永遠の~ と Boxの二冊が読み終わったところだけど、久しぶりにページをめくるのがもどかしくなるようなストーリー運びのうまさと 読んだ後の静かな感動(永遠の) すがすがしさ(BOX)に心をあらわれたわね。
わざわざここで比較の対象として名前を出すのも性格が悪いと思うが 最近実家に帰ったら、弟より 「ねーちゃん これ、おもしろいよ」と渡されたのは 去年の文春の「このミステリーがすごい」で選ばれていた 貴志OO氏の 「悪の経×」であった。厚い上下巻の本だが、確かにどんどん読み進める本であった。
サイコパスの高校教師が教え子を次々に殺していくというストーリー。描写もうまいし、やはり読み出したら止まらない面白さのある話なんだけど 読後感の悪い事・・・ 「あ~ 面白かった だけど なんなの?」
教師の鬼畜度が常軌を逸していて何も感情移入できないってところもあるけど、作者がこの殺戮話を通して何を伝えたいのかさっぱりわからず、刺激的な殺傷場面におしまいには頭の芯が疲れて「あっ もう読み返すこともないや」と思った。 考えてみるとバトルロワイアルの焼き直し感もあったしね。
しかし この百田氏の二冊。
ホントにいいよ。泣けたよ。感情移入できるよ。作られた登場人物ながら、「あ~ あなたたちに会えて良かった」と思える人たちに会えた気がする。
これは片っ端から私の気の合う人たちにおすすめしたい本である。
手始めに家族に 「読め 読め」とおしつけてある。
これについては もう一冊を読んでからそのうちここでまとめてみたいと思う。
さて 去年の春ごろから仲良しになった団塊シティーオヤジたち。その中のまとめ役オジは大学もなぜか二つ卒業していて 某所で教鞭をとり文筆もしているという文化度の高いオジである。
当然かなりの読書家である。
そのオジとひょんなことから本の話で盛り上がった。E・ケストナーの話だった。
ワタシの幼少の頃、かなり好きだった児童文学者である。
ワタクシ今まで生きてきて 男性と「飛ぶ教室」について盛り上がったのは初めてであった。あちらもそうだったらしい。
以前も書いたけど まったく利害関係もなく もちろん恋愛感情もない異性友達と昔読んだ本の話ができるというのは新鮮な体験であった。
そこでそのオジと昔読んだ本の話から、さらに今読んでいる本の話にもなった。日本の小説部門では三浦しおん氏の「仏果を得ず」 山本兼一氏の「利休にたずねよ」偶然最近読んで良いと思った本の趣味も一致した。
 ← これも実におもしろい
← これも実におもしろい世の中には数多の本が出ているのに ここまで趣味が一致するのは珍しいことである。
ところが、私が「その人のは読んだことないですよ」と言った作家。そのことでオジは大変残念がった。「局さん 読んでないんだ ぜひ読んでみて」と
「は~い じゃ 今度買うね」と言ったら 「あっ いいよ買わなくて ちょっと待ってて」と言われた。
そしたらこのほど本の宅配便が送られてきた。ご丁寧に読む順序までレクチャーしてある。

百田さんを知らないのは不勉強であった。こちらを読んでくださる方の中には愛読している方も多いと思う。
ちょうどこのたびの胃腸風邪ですべての予定をキャンセルして家にいなくてはならなかったこの二日、スポーツドリンクとオジがくれた本を枕元に置いて ひたすら読書にふけったのであった。
まだ 永遠の~ と Boxの二冊が読み終わったところだけど、久しぶりにページをめくるのがもどかしくなるようなストーリー運びのうまさと 読んだ後の静かな感動(永遠の) すがすがしさ(BOX)に心をあらわれたわね。
わざわざここで比較の対象として名前を出すのも性格が悪いと思うが 最近実家に帰ったら、弟より 「ねーちゃん これ、おもしろいよ」と渡されたのは 去年の文春の「このミステリーがすごい」で選ばれていた 貴志OO氏の 「悪の経×」であった。厚い上下巻の本だが、確かにどんどん読み進める本であった。
サイコパスの高校教師が教え子を次々に殺していくというストーリー。描写もうまいし、やはり読み出したら止まらない面白さのある話なんだけど 読後感の悪い事・・・ 「あ~ 面白かった だけど なんなの?」
教師の鬼畜度が常軌を逸していて何も感情移入できないってところもあるけど、作者がこの殺戮話を通して何を伝えたいのかさっぱりわからず、刺激的な殺傷場面におしまいには頭の芯が疲れて「あっ もう読み返すこともないや」と思った。 考えてみるとバトルロワイアルの焼き直し感もあったしね。
しかし この百田氏の二冊。
ホントにいいよ。泣けたよ。感情移入できるよ。作られた登場人物ながら、「あ~ あなたたちに会えて良かった」と思える人たちに会えた気がする。
これは片っ端から私の気の合う人たちにおすすめしたい本である。
手始めに家族に 「読め 読め」とおしつけてある。
これについては もう一冊を読んでからそのうちここでまとめてみたいと思う。















 途中図書館で借りてきた三浦しおんに浮気したりして
途中図書館で借りてきた三浦しおんに浮気したりして

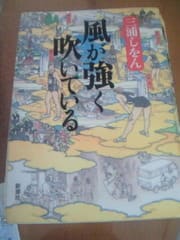



 ・・」 と返信すると
・・」 と返信すると ココ・アヴァン・シャネル ~ オドレイ・トトゥ主演の映画のパンフレット (関係ないが トトゥは息子の彼女に似ているw)
ココ・アヴァン・シャネル ~ オドレイ・トトゥ主演の映画のパンフレット (関係ないが トトゥは息子の彼女に似ているw) ココ・シャネル ~ シャーリー・マクレーン主演の映画のパンフレット
ココ・シャネル ~ シャーリー・マクレーン主演の映画のパンフレット ガブリエル・シャネル ~ 大地真央主演のミュージカルのパンフレット
ガブリエル・シャネル ~ 大地真央主演のミュージカルのパンフレット 獅子座の女シャネル ~ ポール・モラン著のシャネルの伝記
獅子座の女シャネル ~ ポール・モラン著のシャネルの伝記 シャネルの生涯とその時代 ~ エドモンド・シャルル・ルー著の資料集
シャネルの生涯とその時代 ~ エドモンド・シャルル・ルー著の資料集



 滝山コミューン1974 原 武史 著 講談社
滝山コミューン1974 原 武史 著 講談社










