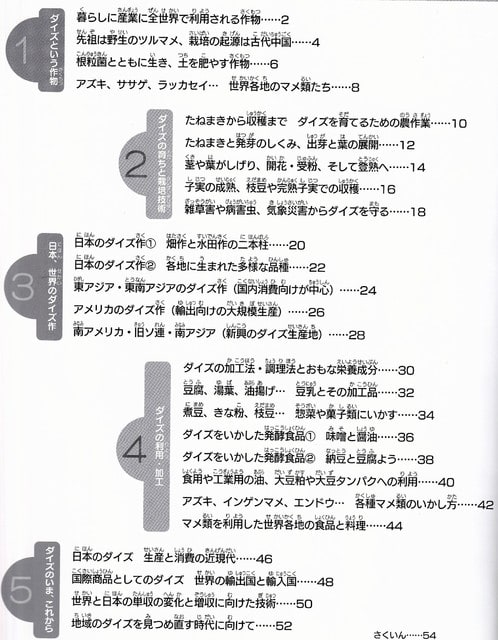昨年、在札の某研究所所長から、会報の特集記事「力強い北海道農業の構築に向けて」の執筆を求められた。その任にあらずと断っていたが、断り方が下手なため、下記のような拙文を公表することになった次第。後になってみると忸怩たる気持ちが残るが、想いは単純で「北海道農業の明日を拓くのは技術革新」「技術開発への投資が必要」と言いたいのである。
詳しくは掲載誌をご覧いただきたい・・・そして願わくば、当研究所の活動にもご理解賜り、北海道農業の応援団になって頂けると幸いである。


はじめに
北海道の耕地面積は全国の約4分の1を占め、多くの農産物生産量が全国1位です。全国生産量に対する道産の割合は、甜菜の100%を筆頭に、菜豆97%、小豆92%、馬鈴薯80%、小麦66%、生乳53%、蕎麦42%、大豆36%と高く、玉葱、南瓜、スイートコーン、長芋、大根、人参なども高い出荷量を誇ります(平成28年度)。また、冷涼な気象条件、昼夜の温度格差はクリーンで高品質な農産物生産に適し、北海道ブランドは高い評価を得ています。
このように、わが国食糧生産の多くを担うまでに発達した北海道農業ですが、その歴史は開拓から数えて僅か150年、険しい道程でした。発展の原動力となったのは、開拓から農業振興に携わった人々の弛まぬ自活への熱望と実践であり、寒地に適応する技術開発により北海道農業を支え続けた技術力でありました。
北海道は主業農家が7割を超え、1戸当たりの経営耕地面積が全国の15倍と大規模経営ですが、一方、地方の人口減少、高齢化や担い手不足など深刻な問題も顕在化し、先行きは必ずしも安穏ではありません。グローバル化の観点で物事が論じられ、混沌の時代だからこそ、敢えて、農業の拠りどころとなる技術開発の重要性を考えてみたいと思います。
1. 技術が先導した北海道農業の歴史
(1)稲作
北海道における稲作の歴史は、1692年(元禄5)文月及び大野村(現北斗市)での試作に始まります。しかし、高温作物である稲を寒地で栽培する試みは困難を極め、道南に稲作が定着したのは19世紀中頃でした。その後、1873年(明治6)に中山久蔵が島松沢で「赤毛」の試作に成功し、稲作は空知、上川へと広がりました。
当初は、北陸や東北地方から導入した稲籾の中から北海道で栽培可能な品種を選び、雑駁な集団から優良個体を見つけては増殖を図る繰り返しでした。「赤毛」「坊主」誕生については、苦難に満ちた闘いの記録が語り継がれています。明治中期に農事試験場が開設され、1913年(大正2)から交配育種が開始されると、品種改良は大きく進展します。従前の穂重型品種から短稈・穂数型の強稈品種へ、度重なる低温年での安定生産を目指して耐冷性強化、化学肥料の使用で多収を目指すようになると耐肥性や耐病性(いもち病)強化が図られるなど、時代に対応した改良が進められました。その結果、強稈多収の「富国」、耐肥・耐病・多収性の「農林20号」「栄光」、早生種の「しおかり」、機械移植の普及にともない「イシカリ」「ゆうなみ」など多くの品種が誕生し、農業発展に寄与しました。
しかし、1970年(昭和45)前後から国内産米が過剰基調となり(北海道でも123万トンの生産量を記録した)、時代は量から質への転換期を迎えます。食味が劣る北海道米は危機的な状況にありました。そこで、1980年(昭和55)に「優良米早期開発プロジェクト」を立ち上げ、低アミロース専用アナライザーの導入、暖地での世代促進栽培、葯培養による育種年限短縮、育種規模の拡大など関係者の総力を挙げた事業が展開されました。その成果は、「キタヒカリ」「ゆきひかり」の誕生を足掛かりに、「きらら397」「ほしのゆめ」、さらに「ななつぼし」「ふっくりんこ」「おぼろづき」「ゆめぴりか」など良食味品種として結実しました。
一方、栽培技術では、府県式水苗代から直播栽培へ、さらに安定生産のための温床苗代・畑苗代へと進み、第二次世界大戦後に農業資材(ビニール、肥料・農薬など)が投入されると昭和30年代は単収向上の時代でした。昭和40年代以降は機械化が進み、平成の時代に入ると極良食味米生産、省力・少資材栽培などが重要課題となり、栽培技術は一段と進展しました。
北海道稲作は、北限の地における安定生産への挑戦、府県産良食味米を凌駕しようと挑戦した歴史でありました。その推進者は生産者自身であり、行政、生産団体など関係者が一体となった推進力に負うところが大きく、新品種など技術革新の支えがあって成就したものと言えましょう。

(2)畑作
大豆の事例を見ましょう。北海道における大豆栽培最古の記録は1562年(永禄5)ですが、一般農家栽培は1870年頃(明治初期)道南で始まり、本道内陸の開拓にともない増加を続け、栽培の中心は道南から道央を経て十勝地方へ移行しました。全道の栽培面積は、1961年(昭和36)の大豆輸入自由化まで約50年間、6~8万haで推移しています。
大豆に関する試験は、明治初めに七飯開墾場、札幌官園、札幌農学校が導入品種の適否試験を実施していますが、実質的には1895年(明治28)十勝農事試験場が設置されてからと言えます。当初は、各地に適する品種選定試験が中心で、「大谷地」「石狩白」「鶴の子」「赤莢」などが選定され、純系分離育種法では「大谷地2号」「石狩白1号」「赤莢1号」等を選抜し普及に移しました。
1926年(大正15)から交配育種を開始し、当時被害が大きかったマメシンクイガ耐虫性を目標に「大粒裸」「長葉裸」など無毛茸(裸)品種を育成しました。また、第二次世界大戦直後に世に出た「十勝長葉」は、既存品種に比べ大幅な多収を示したことから栽培が拡大し、戦後の食糧増産に貢献した品種として記録に残ります。本品種は晩熟であったため度重なる冷害で被害を受け、耐冷性の「北見白」「キタムスメ」「キタホマレ」が育成されるとこれら品種に置き換わり、中粒褐目品種(秋田大豆銘柄)は道東地方及び道央水田転換畑の基幹品種として長く栽培されました。
昭和20年代には十勝地方の豆作率が50%を超え、シストセンチュウ被害が顕著となり、十勝支場では東北地方の在来種「下田不知1号」の抵抗性を導入した「トヨスズ」を育成しました。「トヨスズ」は短稈、耐倒伏性で作り易く、大粒白目の良質性が評価され急速に普及し、全道大豆栽培面積の50%以上を占めました。特筆すべきは、大豆輸入自由化後に国内生産が減少し続ける中、海外産で代替えできない良質性が輸入嵐の防波堤となった事実です。その後、「トヨスズ」の改良型である「トヨムスメ」「トヨコマチ」「ユキホマレ」が育成され、今も北海道を代表する品種となっています。さらに、中国原産の「Peking」からシストセンチュウ強度抵抗性を導入した「スズヒメ」「ユキシズカ」も開発されました。
一方、昭和40年代に入り農作業の機械化が進む中、豆類の収穫作業は機械化が遅れていました。十勝農試ではタイ国品種から難裂莢性遺伝子を導入した「カリユタカ」を育成し、その後の「ユキホマレ」「トヨハルカ」などコンバイン収穫を可能にしました。また、納豆用の「スズマル」「ユキシズカ」、枝豆・製菓用の「大袖の舞」、煮豆用として評価の高い「いわいくろ」など多様な用途向け品種が開発され、実需者の高い評価を得ています。
以上、北海道の大豆作は冷害や病害虫との戦いでしたが、収量及び品質の向上に加えて、耐冷性、センチュウ抵抗性、ダイズわい化病抵抗性、機械化適応性などが着実に進歩し、最近は重要特性を複合的に具備する品種が誕生しています。
大豆以外にも、歴史の分岐点となるような技術開発が数多くありました。例えば、小麦の耐病性及び加工適性向上、馬鈴薯のセンチュウ抵抗性や多様な食用加工用品種の開発、小豆の土壌病害抵抗性品種の開発などが挙げられます。北海道農業発展に果たした技術開発の貢献度は計り知れません。

(3)先人の言葉
これまで見てきたように、寒地気象条件への対応、各地域に適応する品種創出、病害虫への抵抗性付与、省力化のための機械化適性向上、実需や消費者が望む品質向上など、多くの努力の積み重ねがあって北海道農業は発展してきました。
北海道における農業研究は、札幌農学校や開拓使試作場(官園)の時代から「農は実学」との信条で進められてきました。現在も続く揺るぎない考えです。今から80年前、北海道農事試験場長、北海道農会長などを務めた安孫子孝次氏は、「・・・農村非常時に直面し農業合理化を叫ばれて居る今日、その合理化の基礎ともなるべき農業技術の改善は、一日も忽せにすべからざることを痛感せらるるのであります。(中略)凡そ健全なる農家、農村を建設せんとするには農業を経済的に経営するにあります。農業の経済的経営は各種の科学を取り入れ、優秀なる技術により合理的に応用するにあるのであります・・・(北農創刊号巻頭言、昭和9)」と、技術に支えられた農業の重要性を述べています。寒地農業は技術に裏付けられ、技術開発によって進展するとの考えは今に通じるものです。

2. 技術開発のこれから
(1)対応型育種から提案型育種へ
農耕を始めた当初から、人々は食料確保のために、収量の多い個体を選び次年度はその種子を播くというような作業を繰り返してきました。以来、育種目標は、生産性の向上、安定生産を基本に進んできました。広大な北海道では、地域ごとに適応する品種開発も重要でした。病虫害の被害が拡大すると抵抗性をターゲットに、品質や食味向上が求められるとそれらを目標に改良が進みました。いわば、「対応型育種」でした。
課題への迅速対応はこれからも重要ですが、その上で、新たな特性を付与した品種を開発し実需者に利用を促す、戦略育種を目標に加えるのは如何でしょうか。健康志向に沿った品種開発なども一例です。多様な用途を対象にした「提案型育種」の試みです。
(2)重要性を増す遺伝資源
交配育種の成否は母本の能力に掛かっていると言っても過言ではありません。どの品種を交配親に選ぶかは育種家の経験がものをいう場合が多く、多数の遺伝資源を保有していなければ勝負になりません。例えば、水稲では良食味改良のために、府県産やカリフォルニア産の良食味品種、低アミロース突然変異系統などが使われ、大豆のシストセンチュウ抵抗性育種では東北地方の在来種「下田不知1号」や中国原産の「Peking」、大豆の難裂莢性ではタイ国の「SJ2」などを利用し成果を上げています。海外からの導入遺伝資源を含め、多様な育種素材の蓄積が必要であることが理解できます。
わが国では農業生物資源ジーンバンク(農業食品産業技術総合研究機構遺伝資源センター、つくば市)が稲2万5千、麦3万、豆類1万6千など総計約11万点を保有し、利用に供しています。北海道でも道総研中央農業試験場遺伝資源部(滝川市)が約2万8千点を管理しています。生物の多様性条約(1993)が結ばれてから、植物遺伝資源の重要性の認識と共に権利意識が広がりました。世界各国とも、それぞれの国の責任において遺伝資源を保護しています。もし遺伝資源が一企業の財産となったらどうなるか、自由度は極めて制限されるでしょう。
(3)進化する育種手法
北海道における品種改良法は、在来種や導入品種の選定試験、純系分離育種を経て、およそ100年前から交配育種が開始され、現在も交配によって拡大した変異集団から有望個体を選抜する方法が主体となっています。一方、1990年代に遺伝子工学技術が開発され、大豆、玉蜀黍、棉などでは遺伝子組換え品種がUSA、カナダ、ブラジル、アルゼンチン、中国などで90%を超えるシエアを占める状況にあります(国際アグリバイオ事業団2011)
選抜手法の進化も著しいものがあります。医学や犯罪捜査でDNA鑑定が一般化したように、農業分野でもDNAの塩基配列の違いを目印(DNAマーカー)として利用する選抜法が急速に実用化されています(遺伝子組換えではありません)。北海道の研究機関でも病虫害抵抗性や障害抵抗性、加工適性等について判別可能なマーカーを開発し、育種事業の中で活用しています。シストセンチュウ抵抗性を導入した大豆「ユキホマレR」「スズマルR」、落葉病抵抗性を導入した小豆「エリモ167」、黄化病抵抗性を導入した菜豆「福寿金時」などが、マーカー選抜と戻し交雑法により育成されました。
従来は、現地選抜圃や人工気象室など選抜条件を設定して行うため時間と労力が掛かったのに対し、本法は茎や葉など組織の一部を用いて遺伝的な違いを調べることが出来るため効率的な選抜が可能になりました。現在、多くの作物でDNAマーカーが開発中であり、マーカーを利用した選抜は今後さらなる進展を見せることでしょう。
(4)蓄積される研究成果
北海道では開拓当初から大学や農事試験場が一体となって、寒地農業確立のための技術開発に邁進してきました。第二次世界大戦後に農業試験場は国立と道立の組織に分かれましたが、その後も両機関の研究者が集う会議(北海道農業試験会議)で具体的な試験設計や成果について真剣な議論を重ねています。この会議では民間育成の品種についても検討しています。
そして、研究成果は普及奨励、指導参考事項として普及に移されています。直近5年間で、普及奨励事項47課題、普及推進事項45課題、指導参考事項188課題が新たに公表されました。また、除草剤、殺虫剤、殺菌剤についても新資材試験の結果毎年100課題以上が認定されています。これら成果は新技術発表会、農業改良普及センター、技術情報誌、ホームページなどを通じ生産者の手元に届く仕組みになっています。
インターネットなど情報氾濫の時代ですが、試験条件が明らかで、成果の適応場面や注意事項が記された確かな情報選択が重要となっています。
(5)研究投資と連携
北海道農業は、行政、農業団体、生産者及び民間が協力して課題解決にあたってきた歴史があります。例えば、良食味米早期開発プロジェクト、道産小麦品質向上プロジェクト等は典型的な成功例です。また、豆類基金協会や澱粉工業会等の支援も技術開発を促進させました。技術開発投資の意義を再認識したいものです。
北海道には農学部を有する大学、国や道の試験研究機関、農業団体や民間の研究機関が揃っており、研究者層は厚く人材豊富です。共同研究プロジェクト推進は大きな成果をもたらすでしょう。生産現場からの積極的なアプローチが望まれます。
(6)育種は継続・総合・人間性
育種の現場にいた頃、育種は人間らしさの追求である、と考えていました。20世紀に私たちは化学肥料、農薬、除草剤を開発し、機械化を飛躍的に押し進めました。しかし結果として、化学資材への過大依存と作目の単純化が進み、病害虫の多発や土壌の病弊など農業が本来有していた「人間らしさ」を失いかねない状況にあります。私たちは今こそ、環境に優しい農業、活力ある農業経営、うるおいのある農村を目指して、人間らしく、品よく生きる術を身につけねばなりません。
育種家たちはこれまで「育種は持続型、育種は総合型、育種は生活型」との考えで取り組んできました。「持続型」とは、選抜の過程でふらふらしない選抜眼の継続性、先輩から後輩への育種心の継続性、さらには育種事業の継続性を意味しています。中断した育種を再開するときの何と無駄の多いことか。「総合型」とは、単一な特性がいかに良くても品種としては落第と言う意味での総合性、育種グループ全体で取り組むという総合性、環境や機械など関連研究分野が一体となる総合性、さらには生産者や実需者も含める総合性を意味します。そして「生活型」とは、人間を中心にして考えるという意味です。
育種事業は、遺伝資源部門(遺伝資源の収集保存、特性評価、情報提供)、育種部門(交配、選抜、固定、評価)、種子増殖部門(優良種子の維持増殖)、普及部門(地域性を考慮した栽培技術に合わせた普及)など専門技術者の一貫した協力で完結します。育種は膨大な数の材料を扱い、人員や時間をかけ、コストが掛かるが確率の低い事業です。自国の食に係る主要農作物の育種及び種子事業は、当然のことながら国家(公的機関)が主体的に関わらねばならぬ案件だと考えます。
しかし世界は今、市場原則重視の名のもと、大資本バイオ化学企業のGM品種が席巻する状態です。

3. GM大豆栽培が拡大する現場で体験したこと
(1)南米の事例
アルゼンチンは1996年にGM大豆(グリホサート耐性)の一般栽培を開始しました。監督官庁は農牧省で、農業バイオテクノロジー国家諮問委員会が科学的環境リスク調査を実施、食品の安全性については保健衛生・農業品質管理局のガイドラインに従うことになっています。GM大豆は急速に普及し5年後には98%に達しました。GM大豆普及では米国より先行した国として知られています。
しかし、GM大豆が拡大する過程で種子のロイヤリテイを回収できない状況が頻発し、種子会社は輸出先の港で陸揚げ時に徴収する提案までする有様した。その後、特許使用料に関する軋轢を抱えながらもGM大豆は定着し、現在、公的研究機関の育種も種子会社と共同で進められています。
ブラジルは当初GM大豆導入に慎重な姿勢をとっていました。1997年種子会社がGM大豆販売を申請し、翌年に国家バイオ安全技術委員会が安全性を認めると、消費者団体や環境保護団体が栽培の禁止を求めて提訴し勝訴します。以降、GM大豆を支持する農牧省や生産団体と、反対する環境省、消費者・環境保護団体、零細農家組織、NGO等が対立し、訴訟が繰り返され政治問題化しました。
こうした中、GM大豆はアルゼンチン及びパラグアイから非合法的に導入栽培され、膨大なGM大豆の在庫を抱えることになった政府は、やむなく在庫大豆に限って販売を認可、自家採取種子についても生産・販売を限定付きながら認め、その後も生産種子の利用、GM大豆産品の販売認可など、なし崩し的に認可することになります。
この過程で、GM非汚染州を標榜するパラナ州が州内へのGM大豆持込を禁止し、最大の輸出港であるパラナグア港への搬入路を閉鎖するなど強行措置をとったことから、連邦法との衝突、隣接州からの訴訟など混乱を生じ、パラグアイ産大豆のトラック搬送が阻止されるなど国際問題に発展したこともありました。そして、2005年に大統領は「バイオセキュリテイ法」にサインし、GM大豆栽培は合法化されました。現在、92%がGM大豆と推定されています。
パラグアイでは、1997年にアルゼンチンから非合法的に持ち込まれ、栽培が急速に拡大しましたが、当初は低収で旱魃に弱いなど適応性の低さが問題になりました(地域適応性試験を実施していないので当然のこと)。認可を求める農牧省及び生産者と、反対する環境省、環境団体、小農組織等が対立して政府の対応は遅れましたが、2001年に試験栽培を認可、2004年に品種登録が承認されました。
GM大豆栽培が拡大する中で、特許料を回収できない種子会社は出荷流通段階でロイヤリテイを支払うよう要求し、大豆生産者団体はこれを認めました。この額はシカゴ相場に対応して決められ、2006年産では1トン当たり4ドルを超えていました。なお、この額の10%をバイオ技術振興のための研究基金とすることも決められ、農業生物工学協会が組織され、公的研究機関は同協会の資金を得て育種を行っています。
(2)GM大豆の光と陰
南米でGM大豆が広まったのは、不耕起栽培、大規模経営であった事情があります。従来の除草剤体系に比べ環境負担が小さい、管理作業回数の減少により利益が出るなどの利点がありました。一方、除草作業の効率化にともない、1戸当り大豆栽培規模は拡大し、さらには放牧地や未開墾地を大豆畑化するのも容易になりました。環境破壊に連なるとの意見を受けて、政府は未開墾地の樹木伐採の禁止、農地面積に応じた植林の義務付けなど対応していますが、効果は大きくありません。
GM大豆の商業栽培が開始されてから20年が経過しました。これまで安全性に関するリスクは報告されていないと言うものの、耐性雑草の出現が大きな問題となっています。また、小農が大農に飲み込まれ、雇用されていた労働者が土地なし農民となって都市へ流れ込むなど社会問題も指摘されています。
(3)バイオ化学企業の寡占化
GM大豆導入過程で明らかになったことは、バイオ化学企業の寡占化です。今もなお合併を繰り返し巨大化しています。僅か数社の企業が、種子・農業資材・集荷流通を握る状況は、国家にとって安心と言えるのか、気象条件の異なる地域に適応する品種を揃えることが出来るのか、種子の安定供給が会社の都合に左右されないか、種子価格が高騰するのではないか、品種の単純化が進むのではないか(在来種や多様な品種の消滅、遺伝資源の抱え込みの危惧)など、考えさせられました。
数百、数千ha規模での輸出向け生産ともなれば、効率を優先したGM品種導入が当然の成り行きだったかもしれません。しかし今になって、これらの国々でも種子事業の危機感が論じられ、公的品種の役割を見直す動きが起きています。
一方、わが国は自給率が38%と低く、経営規模からしても進むべき道は当然異なります。多様性を尊重し、「安全性」「高品質」をキーワードにした戦略こそとるべき道でしょう。
4. 技術が明日を拓く
これまで述べてきたように、北海道の農業は技術開発に支えられて発展してきました。しかも、単なる外国や府県のコピー技術ではなく、北海道に根差した固有の先駆的技術です。北海道では30年前からクリーン農業を推進してきましたが、今では道産品の代名詞になっています。産地間競争、海外商戦を勝ち抜くには、戦いの素材である技術開発成果品があってのこと。これからも技術開発に期待するところが大きいと確信します。
育種に関して言えば、公的機関は育種システムの根幹を維持することに努め、民間活力を生かす工夫を考えたい。育種家も「育種は継続・総合・人間性」の理念を大事にして、常に農家の畑に立ち、消費者や実需者の声に耳を傾け、迅速な対応を心掛けたいものです。
技術は日々進化しています。生物工学技術、GPSを活用した栽培技術、IT技術が既に多くの場面で活用されています。また、人工知能の開発も進んでいます。間違いなく、技術革新は北海道農業の明日を拓くことでしょう。
参照:土屋武彦2018「技術が明日を拓く~品種開発の観点から~」地域と農業 第108号12-23、北海道地域農業研究所