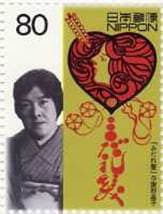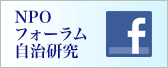写真:「鹿屋資料館」
一昨日の5月27日は海軍記念日。日露戦争の日本海海戦の勝利日を記念してのことです。そのことにも引きずられて、鹿児島市での教育長会議の折、海軍の特攻基地のあった鹿屋の航空資料館を訪れました。
陸軍の特攻基地である知覧が広く世間に知られているのに対し、海軍の鹿屋の特攻基地はほとんど知られてはいないようです。訪れた日も訪問客は3~4組という状況で、知覧の喧騒ぶりとは大いに様相を異にしていました。
『特攻と日本人の戦争』(西川吉光/扶養書房出版)。サブタイトル「許されざる作戦の実相と遺訓」。たまたま書店で見つけたこの一冊を脇に抱えての訪問です。著者が防衛研究所の研究室長の経歴を持った人物だけに、幅広い証言資料などが随所に用いられ、その内容に圧倒されていたものです。
「戦争中、軍高官、幕僚の多くは幾多の将兵に武士道と大和魂を説き、玉砕と特攻を強いながら、自らは戦後、瓦全の途を選んだ」(214p)。
「前途有為の若者は誰の命令、誰の責任の下に死んでいったのか、それを「志願」の一言で片付けられ、責任うやむやのままに戦後を迎える。誰も特攻作戦の責任を取るものがいない。そんな歴史を持つ国で、どうして日本の未来の若者が国のために奉仕しようとするであろうか」(211p)。
人為的政策の犠牲としての「特攻」。こう指弾する著作からは、怒りと無念とが切々と伝わります。それだけに、この本を携えての鹿屋の記念館訪問であれば、そこでの展示が余りにも清潔過ぎると感じてしまったことは否めません。