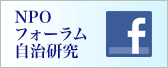写真:「広瀬神社(右後方に海軍旗も)」 本人撮影
夏も終わるにあたって、もう一つ、九州での旅の一端を綴っておきます。豊後竹田(たけたと濁らない)行。ここは同市の滝廉太郎が「荒城の月」を作曲したといわれる岡城址を抱える、静かな城下町です。訪れた所以は広瀬神社に久しく関心を持っていたからです。
広瀬神社は、いうまでもなく日露戦争での旅順港閉塞作戦を決行した広瀬武夫を祭った神社です。「杉野はいずこ」と姿が消えた部下を絶叫しながら探しつつ命を落とした軍人であり、その後軍神と称えられ、国民のだれもが小学校唱歌「廣瀬中佐」を口ずさんだといわれます。それだけに戦後70年近くなる今日、どのように神社が維持されているか、とても気になっていたのです。
長い階段を上ると、そこは広々とした境内となり、しかも荘重な神殿が大きく構えられていました。竹田の街が一望されるその境内の一角には、海軍軍艦旗が、日章旗とともに空高く掲げられていたのが印象的でした。
不明にも驚いたことは、終戦時の陸軍大臣阿南惟幾の顕彰碑が、その境内に置かれていたことです。揮毫は岸信介。広瀬と同じ竹田出身の軍人として、ここに存在することは不思議ではありません。しかし警戒するような違和感を覚えてしまったことは事実です。
阿南は終戦の8月14日の夜に割腹した陸軍大将です。介錯を受けず、しかも「一死ヲ以テ大罪ヲ謝シ奉ル」と遺書を残して逝ったことでも有名です。しかし原爆投下やソ連軍の侵攻を受ける事態になりながら、なお最後まで本土決戦に固執し続けた指導者として、日本人の記憶に苦い思いを植えつけているのも事実でしょう。
昨日今日、民主党の代表選挙で菅総理と小沢前幹事長との争いが熾烈を極めています。その小沢派の主張は、昨年のマニフェストの貫徹です。数兆円の財源不足が明確であろうがなかろうが、掲げた公約を主張し続けることが国民の信頼を得るなどと強調しているようです。
こうした威勢ばかりのいい貫徹主義を耳にすると、阿南惟幾の戦争続行、本土決戦の掛け声と重なってくるのは否めません。苦い歴史が、過去でなく現在もあることに、暑い夏が終わらないことを味わうというものです。