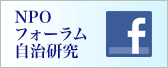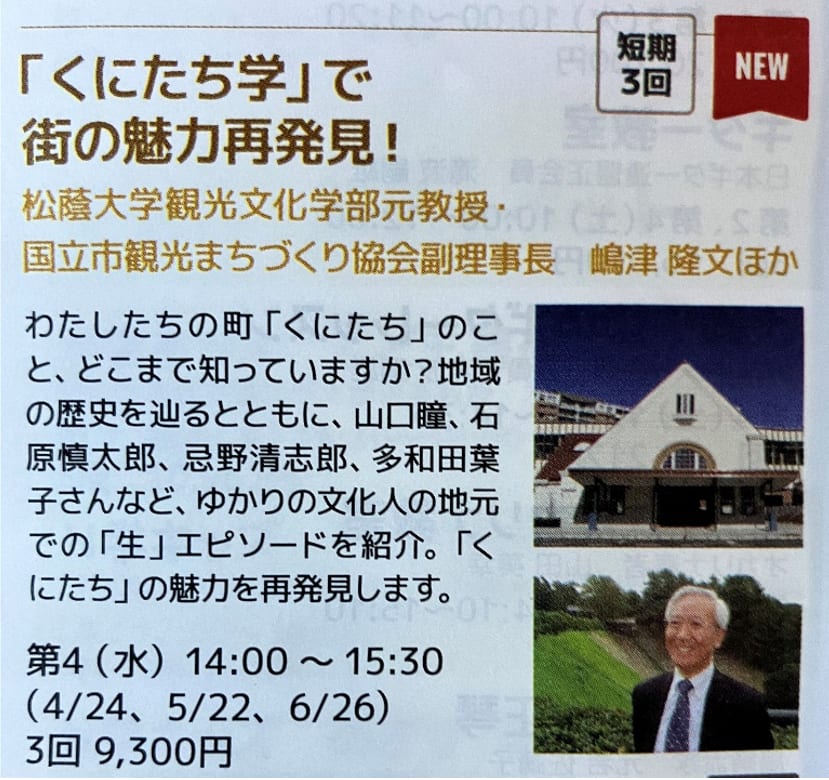

巨星、墜つ。平凡な表現とはいえ、この言葉が口に出ます。“世界のオザワ”が逝ってしましました。88歳は若い。どうしようもなく寂しいものです。
始めて演奏を聴いたのは40年前のボストンフィルの舞台。登壇し、瞬時にタクトを挙げたその自信と迫力に驚愕したものでした。夏のタングルウッド音楽祭での、家族とともに芝生に横たわって聴いた小澤指揮のチャイコフスキーなどは最高の贅沢でした。
しかし遠い存在だった彼が一挙に身近な存在となったのは、昨年から取り組んでいる『中央線沿線物語』の執筆がきっかけです。小澤征爾が家族とともに満州から移り住んだのは立川市柴崎。6歳の時です。そこで若草幼稚園、柴崎小と過ごし、6年後の12歳の時に立川を離れます。取材で訪れた若草幼稚園の園長さんの叔母がこんな思い出を語ってくれたのです。
「セイジちゃんと言えば、すぐ近くの空き地で10人くらいで戦争ごっこをやった時、エイコ上等兵行け!なんて命令されたことがありましたね。家に入ると、目の前に大きなピアノが置いてありました」。
地元の人が懐かしみを込めて語る小澤征爾。“世界のオザワ”は、ここ立川では“柴崎のセイジちゃん”なのです。地元の誇りです。そして間違いなく、立川在住の私にとっても誇りなのです。

小3になった孫が、頼朝や島津義弘あるいはチンギス汗など、洋の東西を問わず歴史に関心を持ち、あれこれ本をめくるようになった。歴史好きの私にしてみれば、何とも好ましい光景と目を悦んでしまう。
人生100年の終章をどう過ごすか。それこそ人さまざまだろう。が、私にはやはり時空を越えての人間ドラマの追求にこそ関心が向く。そんな趣味が一番の長寿薬とも思い始めている。
そう考えると、我が家近くは近現代史の宝庫のように思えてくる。陸軍立川飛行場跡や宇垣一成の揮毫碑、戦後では詩人草野心平、芥川賞作家の中上健次、あるいはロックの忌野清志郎の実家など、界隈は歴史の資料室である。正月には孫が来る。一緒に散策することとしよう。
しかしそんな私の期待ぶりを見て、「お正月早々、小さな子供に押し付けなどするとすぐ嫌われるわよ」と家人。歴史の長さとは違い、自らの居場所が狭くなるを痛感する、辰年新春の朝というものである。