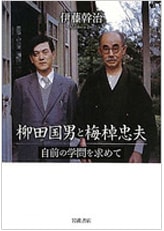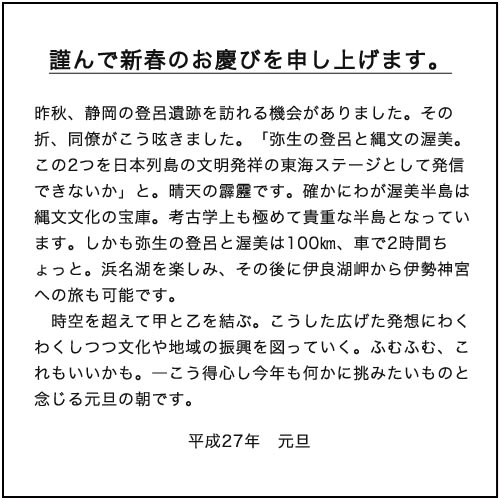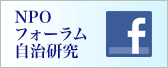「森繁自伝」
おぞましいニュースが連日流れています。「イスラム国」による日本人拘束と殺害。ふとテレビをつけようにも怯んでしまう残忍さです。「イスラム国」と称しながら決して国家ではないこの過激集団を政府はISISと呼ぶとしたようです。
そういえば昭和7年に誕生した満洲国もまったくの似非国家であったと戦後厳しく指弾されています。しかし終戦までの13年間、そこに悲喜こもごもの人生を送った多くの日本人のいたことは紛れもありません。
その一人に森繁久弥がいます。大正2年生まれ、早大中退後、満州新京でNHKアナウンサーに就きます。満映の甘粕正彦とも交流があったともいわれ、終戦後にはソ連軍に連行されるなど辛酸をなめ、昭和21年に帰国しています。
『森繁自伝』(中公文庫)を手にしたのは、昨今ひどく戦前に興味がわき、その一環で満洲国の歴史を生活者の目線から改めて追ってみたいと思ったからです。
読み終えて頭を銃で撃ち抜かれたような衝撃を受けました。ソ連兵による殺害や強姦など人間の欲望と残忍さが随所に描かれます。しかし驚くのは、その陰惨な殺戮や暴行の姿を軽妙洒脱に自伝のなかでは描いているのです。「滑稽の奥に悲哀を漂わせ、優しさの中に厳しさをたたえた筆致」(Amazon評)なのです。
今日も流れる「イスラム国」の残忍な映像。それに押しつぶされようとする自分の狼狽ぶりを見るとき、この軽妙な筆致に森繁久弥の、とてつもなく強靭で慈愛ある人としての深みを思い知らされるというものです。