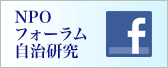始めにひとこと。市長が変わり、国立市政が曲がりなりにも駅周辺などのまちづくり整備に前向きになってきたことで、いよいよ“革新”ばなれが始まったのではと先般のブログ(9月24日)に書きつづりました。そしたらすぐに「状況認識が甘いのではないですか」との電話をいただきました。ジョークのつもりが真顔で指摘されて、苦笑させられている次第です。
さて一昨日の夜は「観光と地域振興」というテーマで、若林陽介内閣参事官(前の国交省の観光地域振興課長)らと懇話会をもちました。来春に「観光庁」が新設される運びになることに関連し、観光振興の重視は実は官僚サイドでなくむしろ官邸指導で進められたことを知らされました。これからの時代、観光が重要になるとの政治家の嗅覚というのはなかなか鋭いと感心したものです。
国立市では先般、観光まちづくり協会が発足し、人をよび寄せる知恵をあれこれ出し合いながら、地域おこしに取り組み始めているようです。先日の嵐山vs頑亭 という両巨頭の対談もその一環だったのでしょう。国立には花がいい。朝顔がいい。そんなやりとりも快く印象に残りました。
それにしても国立の観光資源って何がいくつあるのでしょうか。大学通り、谷保天満宮、そして・・うーん、すぐに指折りが止まってしまうのです。そうなのです。国立に物(ハード)だけ求めるのはきっと誤りなのです。文化や歴史、そして教育。やはり国立はソフトではないでしょうか。市民自治やいい行政実績さえ積めば市役所でさえ全国の人が視察に来る観光資源になる時代です。
もう一つ、今後の観光は一自治体のエリアで考えず、五日市憲法草案や武蔵国分寺や府中の歴史などと広域的なリンクがないともったいないですね、とは集まったメンバーの言でした。さらにこんな話もありました。地域おこしには3者(もの)が要る。必死でやる「ばか者」、それを支える「若者」、冷静に見る「よそ者」の3者です。国立にはこの人たちがいますかとも問われました。
ところで駅周辺のまちづくりも、観光振興や地域振興の視点からの検討も必要です。こういうと三角屋根の復活だけを思い浮かべそうですが、それに止まるものではありません。国立のブランドイメージから、教育産業や文化産業の小ぶりのシリコンバレーのような地域を形成してもよいのです。そのためのステージとして、南口公共施設用地などが活用されることも有効です。今回の駅周辺まちづくり計画作業はこんな面からも目が離せません。