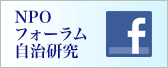【戦前の在独日本大使館】
戦後70年というのが節目であることを、この夏、御前崎近くに住む叔父の熊切三佐治(大正6年生れ)の死からも知らされました。
三佐治がドイツの日本大使館に海軍武官として赴任したのは昭和16年から4年間。横須賀通信学校高等科を出たこの叔父の、ベルリンでの任務は諜報活動でした。10年ほど前にその叔父の口から、「ドイツに向かう『イ52潜水艦』の誘導と交信を自分はやっていた」という話を聞いたとき、大いに驚いたものです。
『イ52潜水艦』は昭和19年の春、ドイツの新兵器技術や先進的な工業製品の獲得のため、金塊2トン、スズやタングステン228トンを積んで極秘のうちに日本を出港します。しかし米軍に通信を傍受されて攻撃され、乗員全員が太平洋に沈むのです。
「喜望峰から北上するイ52の進路は、連合軍のおびただしい航空機や鋭敏なソナー探知で極めて危険であり、息詰まるようだった」と三佐治は語っておりました。
この潜水艦は最近になって発見され、NHKで平成9年に『消えた潜水艦イ52』として特集され、放送されました。また吉村昭著『深海の使者』の素材ともなっている事件です。
歴史の生き証人がこうしてまた失われていきます。当たり前とはいえ、記憶と記録に留めることの大切さを歯がゆいままに感じるこの夏です。叔父の海軍の軍服も、棺とともに失われていきました。