
写真:「明け方の月」
今朝は早朝から目が覚めてしまいました。新聞を手にして冷気が小気味よい庭に出てみると、西の空にぽっかりと白い月が浮かんでいました。人間の生活を静かに、しかししっかりと見下ろしているのだなと、いささか厳粛な気持ちになったものです。
目を通していた読売の「論点」に、全国犯罪被害者の会の代表をやっていた岡村勲弁護士の寄稿がありました。10年ほど前は50人台であった未執行死刑囚の数が現在は120人になっている現状を挙げ、昨今の法相の姿勢を厳しく指弾しているものです。
「死刑は残虐な刑だ」という主張に「死刑囚が被害者を殺害した時の残虐非道さの比ではない」と詰り、「死刑に威嚇力はない」という意見にも「それは嘘だ、これほど怖い刑罰はない」と反論しています。86%が死刑容認との内閣府の意識調査も挙げています。説得力があると言うものです。
死刑執行命令は、判決確定から原則として6カ月以内でなければならない、というのが刑事訴訟法です。だが今の平岡秀夫法相もその前の江田五月法相も、死刑は慎重でなければいけないと強弁し、法に従う姿勢を持ちません。
岡村弁護士は、こうした状況が続くのなら死刑執行命令権を法相から取り上げ、これを検事総長に移すよう刑訴法を改正すべきだと、憤懣やるかたない思いを叫んでいたのです。身内を殺害された大勢の家族の悲痛さを受けて綴ったものに違いありません。正論であると大いに納得するものです。














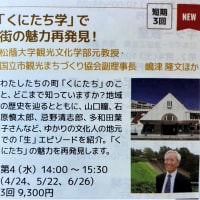
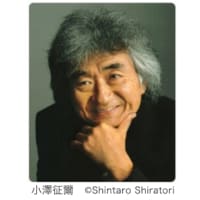





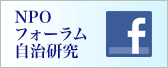





一方で、死刑の執行権を検事総長に移すということが違法状態を解消することにつながるのでしょうか。
考えたくありませんが、仮に死刑を執行された方が冤罪だった場合、国家は責任を取るのでしょうか。その場合の名誉回復、どのように行うというのでしょうか?(少なくとも、訂正記事の扱いが低いわが国の現状にあって、その名誉回復は相当な手段を必要とするでしょう。)
検事は、官僚であり、公益の代表者であるとともに、国民の権利を不当に制限することも可能な立場にあります(厚生省の局長の証拠ねつぞう事件は記憶に新しいところです。)。
死刑の執行について、法相がダメだから検事総長…というレベルの議論で良いのならば、法の規定に基づく執行なのだから、もはや誰が死刑を執行しても良いのではないでしょうか。
しかし、誰が死刑執行を行うにしても、国民のチェックが果たせるような制度であるべきです。
2.「「死刑に威嚇力はない」という意見にも「それは嘘だ、これほど怖い刑罰はない」と反論」→なっていませんね。刑事政策の研究書でも出せばいいのですが、ないんですよね、威嚇力があるという研究が。
3.「検事総長に移す」ということは、法務の最高責任者は関与できない、ということになります。国民・市民の命を奪うのに適当でしょうか?
岡村先生のストレスはよくわかるのですが、主張自体はストレスがもろに出ており、見聞に値するかは疑問だと思いました。「日本の論点」(文芸春秋)の最新版でも岡村さんの論文を見たのですが、戦争があるから死刑もあり、みたいな見解では、笑われるだけだと思います。