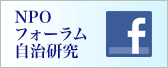国立駅の周辺まちづくりの基本計画(案)「中間のまとめ」が出され、先週から市民説明会が市内の何ヵ所かでもたれています。最終のとりまとめは後1~2カ月になるとのこと。10年近く、なおざりにされ、放置自転車などの混乱が続いてきた駅周辺整備であれば、その進捗は大いにまたれるところです。
しかし今回の「中間まとめ」を見る限り、不安は絶えませんし不満も募るばかりです。そのポイントはつまるところ2つです。1つは費用(財源)についての未計上ということであり、もう1つは時間についての無頓着さということです。
まちづくりにはお金がかかります。計画は財源が明確でなければ、市民として正しい選択肢を選ぶことが出来ません。いくら美味しそうなケーキがあっても、一個5万円もしては手が出ないのです。にも関わらず今回、ケーキばかり並べ、一つも価格が書いてないのです。これは行政として、無責任のそしりをまぬがれません。200億円とも300億円ともいわれる大プロジェクトの、費用(事業費とその財源)を無視した“夢”談義は、全市民を巻き込んでのから騒ぎに終わってしまいます。
しかも今回の「中間のまとめ」は、市民ニーズとして実に多くのメニューを掲載しています。駐輪場、駐車場、行政サービスセンター、図書館、集会所、保育所、音楽ホール、コンベンション機能、宿泊機能(ホテル?)、フィットネス、クリニック、商業施設、SOHO、定住機能(マンション?)などなど、ほとんど何でもござれのてんこ盛り状態です。これでは大金がかかるし、収拾もつきません。それにもかかわらず、“夢”イメージプランで心を弾ませるのは、小学校のホームルーム論議と同様の風景ではないでしょうか。
ところで中に一つばかり注目することがありました。それは、さすがにこれだけ山ほどの機能を入れるとなると小さな建物というわけにはいかないのか、イメージ図では南口公共施設用地に8階建ての大きな建造物をつくるようにしていることです。全体の巨額な財源を捻出する上でも、避けて通れない選択かもしれません。が、この高さは自民の某市議が主張している10階以上でもいいというかなり乱暴な考えに近いもので、大変驚かされました。「修復型まちづくり」(現在の3階以下?)しか行わないとこだわっていた共産党など与党諸兄の、その主張は一体どこへ行ってしまったのでしょう。
今回の計画づくりで、2つめに指摘しなくてはならないのは時間感覚の喪失です。時間とはお金(コスト)です。そもそも駅周辺のまちづくりについては、平成12年に周辺プランが出されました。それ以後上原市政下で数回にわたりプランが検討されました。早く案をつくれば、それだけ東京都やJRときちっとした交渉が出来るからというものでした。しかしたっぷりあった2期8年の期間、彼女は検討だけさせて、国立市としてのオフィシャル計画をつくらず駅のまちづくりを放棄しました。その遅れでコストはどんどん高くなっており、交渉もできず、市(すなわち市民)の背中には火がついているのです。
にもかかわらず、例えば「中間のまとめ」では、またまた作業が遅れようとしています。例えば平成22年の高架化完成時に公共施設用地などの事業計画(具体的計画)を確定するといっているのです。驚くばかりです。それまでの間、事業プランも持たず、次々に進むJRの工事に指をくわえていているのでしょうか。JRの工事が完成してしまって一体、何を交渉し調整しようとするのでしょう。
時間(スケジュール)管理というものが、この国立のまちでは一貫して欠落されてきています。平成16年の基本計画案でも、「南口公共施設用地の整備は平成21年か22年」と明記されていました。それが今回の「中間のまとめ」では、事業計画の確定そのものが平成22年の高架化工事完了後になっているのです。事前に調整すれば安くて済む工事変更も、完成した後ではすこぶる高くつくことは誰でも想像のつく話しです。スケジュール管理のない行政はコスト感覚がない、やる気もないといわれてもやむを得ないというものです。
財源と時間。いずれも国立市民の血税に直結するものです。この2つを意識して、基本計画と事業計画はとりまとめられなくてはなりません。とかく革新といわれる諸兄が軽視するこの2つのポイントを、これ以上いい加減にすることはできません。このままの絵空事の駅周辺整備計画では、JRにやられっ放しで、市民の意見の反映などはとても覚束なくなるからです。
しかし今回の「中間まとめ」を見る限り、不安は絶えませんし不満も募るばかりです。そのポイントはつまるところ2つです。1つは費用(財源)についての未計上ということであり、もう1つは時間についての無頓着さということです。
まちづくりにはお金がかかります。計画は財源が明確でなければ、市民として正しい選択肢を選ぶことが出来ません。いくら美味しそうなケーキがあっても、一個5万円もしては手が出ないのです。にも関わらず今回、ケーキばかり並べ、一つも価格が書いてないのです。これは行政として、無責任のそしりをまぬがれません。200億円とも300億円ともいわれる大プロジェクトの、費用(事業費とその財源)を無視した“夢”談義は、全市民を巻き込んでのから騒ぎに終わってしまいます。
しかも今回の「中間のまとめ」は、市民ニーズとして実に多くのメニューを掲載しています。駐輪場、駐車場、行政サービスセンター、図書館、集会所、保育所、音楽ホール、コンベンション機能、宿泊機能(ホテル?)、フィットネス、クリニック、商業施設、SOHO、定住機能(マンション?)などなど、ほとんど何でもござれのてんこ盛り状態です。これでは大金がかかるし、収拾もつきません。それにもかかわらず、“夢”イメージプランで心を弾ませるのは、小学校のホームルーム論議と同様の風景ではないでしょうか。
ところで中に一つばかり注目することがありました。それは、さすがにこれだけ山ほどの機能を入れるとなると小さな建物というわけにはいかないのか、イメージ図では南口公共施設用地に8階建ての大きな建造物をつくるようにしていることです。全体の巨額な財源を捻出する上でも、避けて通れない選択かもしれません。が、この高さは自民の某市議が主張している10階以上でもいいというかなり乱暴な考えに近いもので、大変驚かされました。「修復型まちづくり」(現在の3階以下?)しか行わないとこだわっていた共産党など与党諸兄の、その主張は一体どこへ行ってしまったのでしょう。
今回の計画づくりで、2つめに指摘しなくてはならないのは時間感覚の喪失です。時間とはお金(コスト)です。そもそも駅周辺のまちづくりについては、平成12年に周辺プランが出されました。それ以後上原市政下で数回にわたりプランが検討されました。早く案をつくれば、それだけ東京都やJRときちっとした交渉が出来るからというものでした。しかしたっぷりあった2期8年の期間、彼女は検討だけさせて、国立市としてのオフィシャル計画をつくらず駅のまちづくりを放棄しました。その遅れでコストはどんどん高くなっており、交渉もできず、市(すなわち市民)の背中には火がついているのです。
にもかかわらず、例えば「中間のまとめ」では、またまた作業が遅れようとしています。例えば平成22年の高架化完成時に公共施設用地などの事業計画(具体的計画)を確定するといっているのです。驚くばかりです。それまでの間、事業プランも持たず、次々に進むJRの工事に指をくわえていているのでしょうか。JRの工事が完成してしまって一体、何を交渉し調整しようとするのでしょう。
時間(スケジュール)管理というものが、この国立のまちでは一貫して欠落されてきています。平成16年の基本計画案でも、「南口公共施設用地の整備は平成21年か22年」と明記されていました。それが今回の「中間のまとめ」では、事業計画の確定そのものが平成22年の高架化工事完了後になっているのです。事前に調整すれば安くて済む工事変更も、完成した後ではすこぶる高くつくことは誰でも想像のつく話しです。スケジュール管理のない行政はコスト感覚がない、やる気もないといわれてもやむを得ないというものです。
財源と時間。いずれも国立市民の血税に直結するものです。この2つを意識して、基本計画と事業計画はとりまとめられなくてはなりません。とかく革新といわれる諸兄が軽視するこの2つのポイントを、これ以上いい加減にすることはできません。このままの絵空事の駅周辺整備計画では、JRにやられっ放しで、市民の意見の反映などはとても覚束なくなるからです。