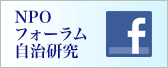写真:市ヶ谷のかつての極東軍事裁判の法廷
一昨日の4月26日の午後3時、東京高裁の825号室のドアを開けて、私は思わず立ち止りました。居並ぶ国立市のプロ市民と言われるメンバーの虚ろな表情が、終戦後に開かれた極東軍事裁判の被告らの表情と、二重写しになって目に入ってきたからです。
「大東亜光栄圏」のスローガンと同様、「景観を守る」という美名のもとに展開されたのが国立景観「戦争」です。市民同士を争わせ、後付けの立法でマンション業者を「非国民」のように攻撃し、弁護士費用を湯水のように使って「戦争」に突入していった国立のプロ市民たち。ルールを無視して暴走した軍部と二重写しになるのは否めません。
市民を扇動し続けた上原公子前市長と、その行動を支えた石原一子景観全国ネット代表、桐朋の某事務員ら。総体としての彼らの行動が市に3200万円の損害を与えたと地裁で判示され、その支払いがまさに決定されようとしているのです。そのメンバーの表情が虚ろになるのも当然です。
しかし法を犯せば、報いを受けなくてはならないのは世の道理です。
それなのに彼女たちの意向を受けたのでしょうか、一昨日、関口博市長は国立市役所で記者会見を開いています。そして言いました。「(新しい市長には)裁判が続けられるように、控訴を取り下げないよう求めます」(朝日新聞)と。
市長選挙のあいだ中、上原前市長は関口陣営の選挙カーのマイクでこう絶叫していました。「私は佐藤一夫のことをよく知っています。何故なら私の部下だったからです。だから分かるのです、彼は何も決められない男なのです!」。直接、耳にした人も多いでしょう。
こう口汚く攻撃していた当の「何も決められない」佐藤一夫新市長に、一転して控訴を下げないことを「決めて欲しい」と求めたのです。語るに落ちるとは、まさにこういう所作を称するのです。