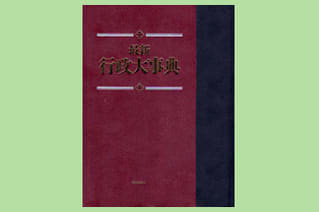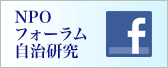厚木市の全景
今週始め26日の火曜日に、厚木市で「シティセールス戦略検討委員会」なるものが発足し、その委員長職に就きました。「あつぎブランド」を考案するとともに、その名を全国に売って、厚木市への企業誘致や交流人口増加の手立てを工夫していこうとする委員会です。
厚木市は人口22万人の中核都市。出席した小林常良市長の口を借りれば、「神奈川県央の雄都」となることが期待されています。日産やNTTなど有力企業が集まり、財政力指数も1.5近く(平成18年度)、全国のベスト10に入る優良自治体です。しかし商業、農業の伸び悩みは深刻で、駅前周辺の商店街さえ空き店舗を生じています。街としての印象の薄さも否めません。
委員会は、商店街の会長さんや農協の青年部長さん、ホテルや小田急の関係者など13人のメンバーで構成されています。昨秋B級グルメのグランプリ全国一で有名となったシロコロホルモンの探検隊長も加わってのスタートです。自分たちの町、厚木を何とか元気にさせたいとの、危機感と熱意が芬々としていました。 会議の中で、印象深かった一つに、行政と民間メンバーとの問題意識の違いがありました。事務局から今後のスケジュールとして、一年後の来年3月に「戦略プラン」なる報告書を出してほしいとの提案があったのですが、「そんなゆっくりする余裕はない、すぐにでも実施すべきだ」との発言が、メンバーの中から強く出されました。
行政は時間の感覚、すなわちコストの感覚が薄いと常々言われます。その問題性をストレートに指摘するメンバーの姿勢に、委員長としての私は思わず、「いや、分かりました、主テーマの議論は3ヶ月の内に決着することとしましょう」とノッタものでした。そして次回は集中的な議論を行い、反映すべきものは年度末の報告を待たず、すぐに実行することを確認し合ったのです。
こういう予期せぬ展開が生じた場合、シワ寄せで大変になるのは作業部隊たる事務局です。しかし厚木市の担当者の反応は、極めて柔軟でした。国と比べ、自治体の職員の瞬発力は評価されてきている昨今ですが、こうした前向きの姿を目の当たりで見せられると、たいへん納得するというものです。
この会議での盛り上がりと協調の姿勢は何としても持続させ、面白い提言としてとりまとめたいものと、けっこう気負って、市役所を後にしたものでした。