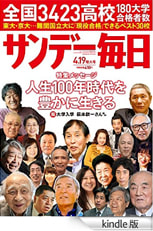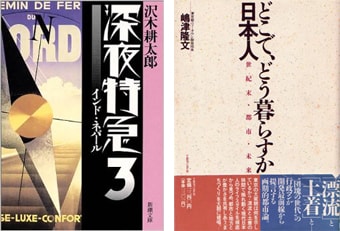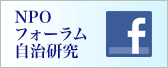【カトマンズのスワヤンプナート仏塔】
ネパールで大地震があり数千人の人たちが亡くなったとのニュースが流れています。大地震という言葉は、私に津波の直後の女川町で嗅いだ異臭を思い起こします。同時にカトマンズで嗅いだ強烈な異臭を思い出します。あらゆる建物や動物を水と泥でかき回して腐敗すると、こんなにも似た臭いを生んでしまうものかと、やりきれない悔しさを抱いたものです。
カトマンズを訪れたのは3年前の2012年3月のことでした。神々の住む美しいヒマラヤの一方で、地上の街カトマンズは人間の汚濁の中にありました。川という川には汚物が散乱し異臭が漂い、また道という道には車とオートバイが溢れ、大気の汚れに誰もがマスクを付着せざるを得ない状態でした。
「明らかにインフラが足りないのです」。そう地元の通訳ガイドが嘆いていました。「道路も水道も下水も何もかもこれからです。そのためには外国資本が必要であり、政権が安定し、憲法制定が行われなくてはなりません」。
ネパールは20年前に立憲君主制となり、2008年にはその王政さえ廃止され民主共和制へ移行しました。しかしマオイスト(毛沢東主義者)と議会派の内紛状態は解消されず、他方で中国、インドという周辺大国の進出に脅かされていたのです。
そうした人災というべき政治不安のなかでのネパールでの天災です。神の国に神はいない。そんな残酷な溜息を洩らさざるを得ない今次の大地震というものです。