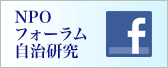先日、ある知人から「最近のブログ、ちょっと重いですね」といわれ、ハッと思いました。確かに明和マンション判決や国立駅周辺まちづくり計画案をめぐり、国立市の無様な対応にやや拘泥し過ぎてしまったかも知れません。そこで今日は、口直しのブログといたしましょう。
「団塊の世代」論を連載してくれませんか。先週、ある月刊誌からそう話しがありました。10回シリーズで、この6月号から約一年の掲載ということです。月刊誌名は「地方財務」(ぎょうせい)。ちょっと嬉しい話です。前々から団塊世代のあり様は、社会だけでなく、自分の生き方を考える上でも少し冷静に整理したいとしていただけに、大いにノッて書きたいものと考えています。
昭和22年から3年間に生まれた団塊世代。680万人の大量世代です。しかも人生90年ともいうべき社会になりました。団塊世代はあと30年は生きていくことになります。死なないのです。後期高齢の後半は疾病と老衰で多くの人は介護を必要としその負担は現在より社会保障費としては2025年に152兆円と66兆円増加するとも予想されています。
果たして沸々として、年寄り「お荷物論」、とりわけ団塊世代「お荷物論」が出てくるのは必然というものです。団塊世代の抱える構造的問題。それは負担を媒介にした、世代間の相克の問題が深刻化することです。まずそのことが、私の頭を一番初めによぎる課題といえます。その予兆はすでに見えてきています。団塊世代は、感情的にも経済的にも、後続世代から強い憎悪をもたれ始めているのです。2、3挙げてみよう。
「なかでも『団塊の世代』が一番ひどいと思う。最後まで年金を食い逃げして若い世代を苦しめて死んでいく。オレは『食い逃げ世代』と呼んでます」(金子勝「先行き不安だらけの日本」)。
「過剰意味づけ、自己主張、せっかち、リーダーシップなし、責任回避、被害者意識過剰、身勝手で傲慢、自分優先の人生」(由紀草一「団塊の世代とは何だったのか」)。
「『失われた10年』の間に業種・企業を問わず職場の合理化が進みました。「そのしわ寄せ」はとりわけ30代までの若者に最も大きかったと断じます。要は中高年による若年層への「つけ回し」が行われたわけです」(玄田有史「仕事の中の曖昧な不安」)。
私は20年前に「団塊の世代は殉死の世代、散華の世代になる」と自著で指摘したことがあります。すなわち、家族の負担や社会の負担を軽減するために、自発的に命を絶つことを期待され始めるのではないかということです。お爺さんが死ねば、お婆さんも後追いして逝ってもらう。そうしたことによって一挙に社会的コストを半減できる。そんなおぞましい風潮が醸成されるのではないかと懸念し、自嘲的に指摘したのです。
子孫と国家のために、自らの命を犠牲にする『自死』や『夫婦殉死』を美風とする。そうした価値観が、コストの逼迫化の下で台頭しかねないことを誰が否定できるでしょう。ちょっとした煽り立てとムードで、見境なくバッシングを始めるこの国の国民性を私たちは幾度も知らされてきているからです。現にそれを裏付けるかのように、昨今の後続世代からの憎悪の声が聞こえ始めてきたということなのです。
ここまで書いてくると、「どこが一体明るい話題のブログなのよ!」とくだんの知人に責められそうです。何とか暗い話しを、精一杯明るくする工夫を考えていかなくてはなりません。この連休は、そんな気負いをもっての原稿書きを、パソコンに向かって進めたいと心している次第です。
(追記)このブログをしたためている最中、衝撃的な連絡が入りました。明和マンション(明和地所)から賠償金の返還が提示されたということです。国立市に3000万円を寄付したいとのこと。感動的なことです。この間、極悪非道といわれてきた明和地所が、何と大人の対応をすることでしょう。こうなると前市長の姿勢が一層問われることとなります。私に責任はない、一銭も支払うつもりはないという、かたくなな対応ぶりは一体どういうなることでしょう。哀しい限りの、一人の女性の姿が浮かんでくるというものです。