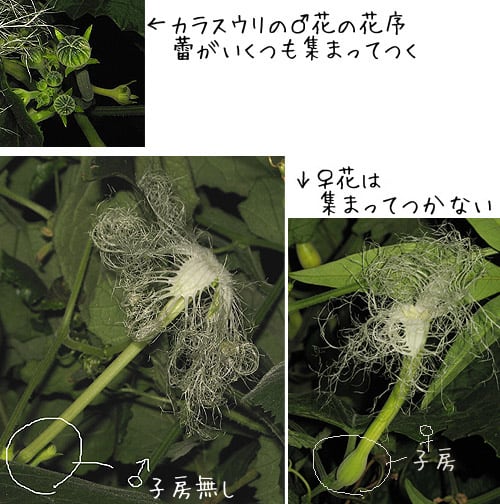「ルリマツリ(瑠璃茉莉)」はイソマツ(磯松)科ルリマツリ属の蔓性常緑小低木で、原産地は南アフリカの喜望峰地方と言われています。
春~秋にかけての長期間、涼しげな薄青色の花をたくさん咲かせますので、夏には欠かせない花で、夏の花として人気があります。
・我が家の庭のフェンスに咲いている「ルリマツリ」です。

この花の名前の由来は、花色が瑠璃色で、ジャスミン(茉莉花・マツリカ)に似た青い花を咲かせることから付けられたと言われています。
細長い茎の先端に、花筒の長さ約4cm、花径2cm~2.5㎝の高杯(たかつき)形の5弁の花を5~10輪集合させて咲かせます。

また、この花の別名は「plumbago(ブルンバコ)」と言います。
「plumbago(ブルンバコ)」は、鉛を意味するラテン語の「plumbum(プラムンバム)」が語源となっており、その由来は、この植物が鉛中毒の解毒に効くことからつけられたようです。
アフリカでは薬草として頭痛、イボ、骨折、皮膚の傷などの民間薬に利用されているとのことです。


この花は一般的に耐寒性が弱いとされていますが、0度以下でも地下茎は枯れることはなく越冬できるようです。

・「花言葉」 密かな情熱、同情
・なお、ルリマツリ(瑠璃茉莉)は9月2日の「誕生花」になっています。