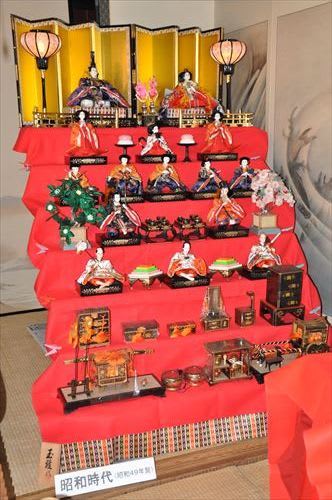私が卒業した小学校の同年会は毎年なにがしかの会合を行っていますが、今回は77歳を迎えたので、喜寿の祝いと祈祷をしていただき、健康で楽しい日々が来ることを祈りました。 それで、当ブログはその記録と、今までの歩みを少しまとめてみました。
私は昭和19年に小学校に入りましたが、その年の夏休みには第一回目の転居が始まり、小学6年間で実に6回もの転居を余儀なくされるという”住所不定”、”流浪”(?)の小児期を過ごしました。最も短かったのは、4年生の3学期のみの3ヶ月ということもありました。
原因は父が「駐在巡査」であったからとは言うものの、余程間に合わなく次々と変えさせられたのかもしれないと、引っ越しで友達もほとんど出来ず子どもの心には、大きな傷跡が残ったと感じているところです。 転校生として”いじめ”に似たことも・・・。
以前は三重県北部の山村をうろうろしていましたが、小学5年の夏休みに初めて、四日市市羽津町という沿岸部に出てきました。 今まで小さな川やため池でやってた魚釣りが海で出来ると喜んだ一面もありました。しかし所詮は田舎者、不安な面もありました。
昭和23年当時、羽津地区の小学生は隣の海蔵小学校に併合させられており、大変に遠い道のりを歩かされたものでした。お婆さんが編んでくれた新しい”わら草履”が夕方家に帰るころには、踵の部分はすり減るし、花緒が切れたりして、裸足同然で帰ったものです。
小学6年の春からは、羽津地区の小学校に通うことになり、安堵したものでしたが、私にとっては一年間のみお世話になったのが、下の写真の「羽津小学校」です。 当時を偲ぶものは、校門と二宮金次郎の像のみでした。

門の脇にあった、何も入っていない「奉安殿」がありましたが、今はその跡もありません。金次郎さんも奉安殿と同じ方向を向いていましたが、今は入ってくる児童を迎えるように、向きが変わったように思います。石の台は昭和11年建造と彫ってありましたがね?。

羽津小学校の校門を出て、ほんの1~2分学校の帰り道に遊んだこともある、「志氏神社(しでじんじゃ)」があります。 今回の祈祷はこの神殿で受け、その「参集殿」で懇親会を行うことになっています。





前方後円墳があり、市の文化財となっています。

私は前に書いたように、ここには小学5年の夏以降卒業まででしたが、そのあとの中学校は隣町の海蔵地区と合わせた「山手中学校」を卒業したので、同級生とは私の生涯でもっとも長い”5年近く”の付き合いのあった人達なので、私にはここが第一の故郷なのです。
羽津小学校を昭和25年卒業生は90名いましたが、、内30名はもうこの世にはいません。 その内の33名が今日ここに集まり、祈祷を受けました。

男子女子各一命が代表で玉串を奉納しました。

そのあと、参集殿にて懇親会が始まりました。 中には卒業以来つまり、六十何年ぶりかで会えた人もあり、楽しいひと時でありました。 老齢化により体の不自由な人もいるので、一泊の旅行スタイルでは参加できなきても、このような形であると参加者が増えるのでありました。

午前10時に集まり、幼馴染との会話が弾み、時の経つのを全く気にせずしゃべりまくり、やっと午後4時に散会となりました。 生きていてよかったと思える、ほんのひと時でした。今夜はぐっすり眠れそうだ!。 (2015.02.28(土) 撮影)