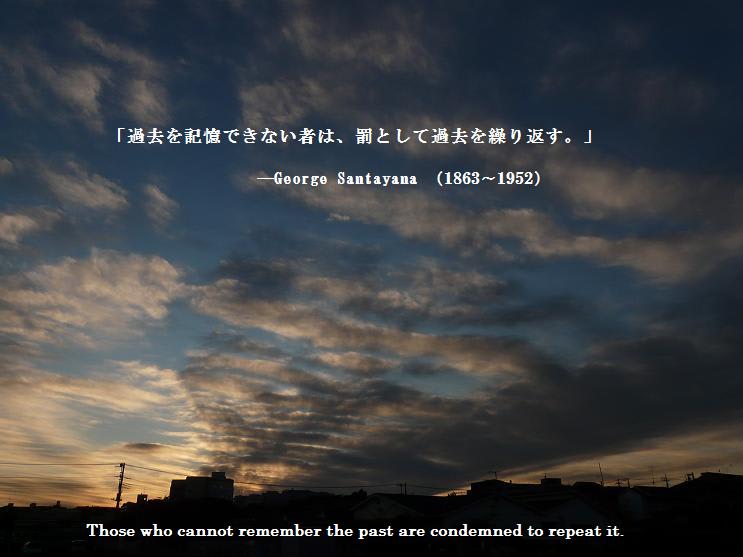「例えば掛け算という演算で支配されるグループを考えてみよう。
そこでは同一律を満たす要素は1ということになる。
そこで、もしこの演算を加算に変えたとしよう。
これは第二次変化を起こすことであり、
それは外部から持ち込まれるものであり、
グループ内部から決して生まれないものだが、
そこでは、異なった結果が得られることになる。
(中略)
前者はメンバーからメンバーへの変化の水準であり(※群内=第一次変化)、
そこでは実際、物事が変われば変わるほど、
それは同じままであるということだし、
後者ではグループの構造や秩序を支配する
一群のルールにおける変化をしようとするわけだ。
(中略)
第二次変化が常にその本質において不連続、
もしくは論理的に飛躍するような性質をもつことを考えるならば、
第二次変化を実践的なところで遂行することは、
非論理的で逆説的な外観を呈することを期待できる。」
「システムそのものの変化すなわち第二次変化を伴わないようなシステムを、
終わりのないゲームに陥ったシステムと呼ぶ。
それはそれ自体からはそれ自身の変化のための条件を生み出さない。
またそれ自身の変化のためのルールを生み出さないのである。」
「同じことを今少し哲学的にいうと、
我々自身を現実と呼ばれるルールに従うコマと考えるのか、
我々自身がそれを作り、受け入れている限りの「現実的な」ルールに従って
ゲームをやっているプレイヤーと考えるかの違いなのだ。
後者はしたがってルールの改変はいつだって可能なのだ。」
――ポール・ワツラウィック他『変化の原理 CHANGE』長谷川啓三訳