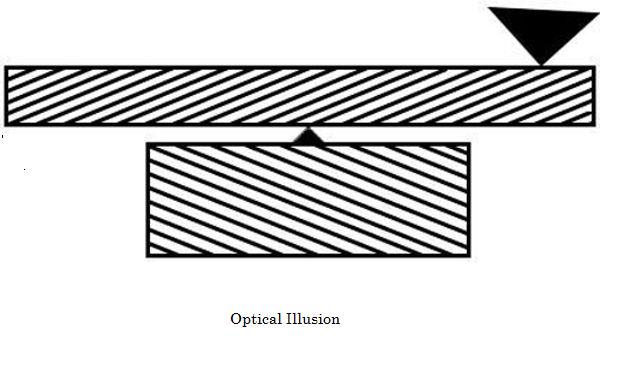先生の授業は、いつも挨拶抜きで開始される。
「本日の授業のテーマは〝重力〟です」
「では、はじめます」
昔、イギリスにアイザック・ニュートンという偉大な科学者がいました。
人類の歴史ではじめて重力を発見した人として知られています。
ニュートンは重力の性質を明らかにして、「万有引力の法則」と名づけました。
重力はモノとモノが互いに引き合うチカラで、宇宙全体に存在します。
手にしたリンゴを離すと地面に落下します。
これも地球とリンゴの間に作用する重力のためです。
地球は丸い形をしていますが、裏側にいても天に向かって落ちることはありません。
地球の中心に向かって引っ張る力が、すべての地上の物質に作用しているからです。
昔も今も、わたしたち人間は地上の重力の中で暮らしています。
ニュートンが重力の法則を明らかにしたことで科学は大きな力を獲得しました。
そして、人間の文明は歴史の歯車を大きく回転させることになったのでした――
あなたは、どう思いますか?
「なぜ重力があるのですか?」
「重力の性質は説明できます。けれども、なぜ重力があるかは誰にもわかりません」
「どうしてですか?」
「世界の様子については説明できます。けれど、なぜ世界があるかはわからない。それと同じです」
「ふ~ん」
「人間も自然も、すべてはなぜか存在している。とても不思議な出来事です」
「不思議なのかな」
不思議でないことが不思議でないとはかぎりません。
不思議さはそれぞれの人に、それぞれのカタチで訪れます。
そして不思議なことと不思議でないことがあるのは、
すべて世界を区切るぼくたちの心が決めていることです。
「世界を区切るって?」
「たとえば、良いと悪い、きれいときたない、本当とウソ、ストライクとボールなど沢山あります」
「境界線を引くということですか」
「はい。昔の西洋には人間と魔女という区切りもありました。今でいえば正常と異常とか」
「無数にありますね」
「そう。国境のような空間的なものから、アウトとセーフといった意味的な区切りもあります」
あるいは食べられるものと食べられないもの、敵と味方、なわばりとなわばりの外とか、
すべての生き物も世界を区切ることでモノを考え行動します。
そして、そうした区切り方は環境、時間の経過、個体の成長によっても変化する点も重要です。
「人それぞれにとっての世界の見え方や感じ方や意味も、またその時々によってもちがいます」
「どんなふうに」
「いつわりの世界、やさしい世界、無常の世界、美しい惑星、カオス的な複雑な世界」
「自分で勝手にそう感じているということかな?」
「そういうものだと感じる。そして同じ人間の中でもそう感じることが変化していく」
「どんなふうに」
「嫌いだったトマトやピーマンが、いつのまにか食べられるようになることもある」
「なぜだろう」
「世界と人の関係がつねに変化しているためです」
「動物もそうなのかな」
「子どものライオンにとってハイエナは天敵ですが、成長すると食糧にみえたりします」
何千年も遠い昔から、数えきれない人たちがこの世界の存在の不思議さについて、
ごはんも忘れるくらい、夜も眠れないほど一生懸命考えてきました。
同時にそれは、人間とは何か、世界とは何かについて考えることでもありました。
「ふ~ん」
「なぜ存在するのか―そこから先は形而上学といって、本当は誰も答えられない問いとされます」
「けいじじょうがくって何ですか?」
「世界の究極の真理について、ああでもないこうでもないと考えることを指してそう呼びます」
「究極の真理って?」
「世界にはじまりはあるのかないのか。人間は自由なのか。神さまは存在するのか、みたいなことです」
「誰も答えられない?」
「答えることはできます。けれどモノのように形がないので、科学の実験で確かめることができません」
「空想の世界?」
「そんなイメージでいいと思います」
観念、つまり考えや想像、イメージだけで出来た世界は、
木や石のように手に取ったり、匂いを嗅いだり、煮たり焼いたりできません。
現実にある存在と結びついた言葉、例えば木や小石なら言葉が一人歩きすることはありませんが、
愛や友情や神様や自由といった観念の世界だけに存在する言葉は、
科学のようにその定義について仮説を立てて、実験を通して確かめていくという、
多くの人が納得する結論を導くという方法が使えません。
「でも算数では同じ答えが出せます」
算数や数学は人間が決めたルールで動く、いわば特殊なゲームの世界といえます。
数学のルールが変化しないかぎり、1+1=2は千年後も1+1=2のままでしょう。
なので、数学ではルールに従いさえすれば誰もが納得できる結論を導くことができます。
けれども数学のようなゲームの中に世界の現実すべてを入れて説明することはできません。
なぜなら、ゲームの外では別のルールで動く別のゲームが無数に存在するからです。
「言葉では無理なのかな」
愛を数式で表わすことはできません。言葉で定義しても愛はすり抜けていく。
言葉の論理を数学のように厳密に組み立てて、一つの答えを導くことはできます。
けれども論理には、文脈ごとに変化する意味をすべて捕捉することはできない。
例えば「バカ」という言葉は、しばしば親愛の言葉であったりします。
生きられる現実の中で、「バカ」は罵倒や愛情や憎悪や冗談など多様な意味に分岐します。
論理的な正確さを優先して、これが「バカ」の正しい定義だと決めてしてしまうと、
逆に、言葉にそなわる豊かさや多様性を奪うことになります。
観念の世界では、多様な意味の解釈や言葉の定義、ルール、使用法が成り立つので、
誰もが納得する共通の結論を導くことがとても困難なのです。
一つの言葉の解釈について、どれが正しいかは事前に決定できません。
「どちらが正しいか、だれの意見が一番なのか決められない?」
もしも「どれが本当に正しいか」という問いを立ててしまうと、
この考えが絶対に正しい、いや別の考えが正しい、という喧嘩がはじまります。
ひどい場合には殺し合いさえ起こることがある。
人類の歴史にはそうした対立が引き起こした悲劇が数多く刻まれています。
物語が物語のまま、いわば仮説として保たれる、それが形而上学の世界の本質です。
なので、証明という作業を伴わないとりあえず説明、つまり物語を使って語るしかありません。
「よく出来た物語だなあ」と多くの人を納得させる、という形で世界の〝真理〟が創られます。
「神様の物語?」
「世界中に神様の物語は民族の数だけあるともいえます」
「どれが本当の神様ともいえないといえないのですね」
「本当の神様とウソの神様をわける根拠は誰も示すことができません」
このことから、一つだけ言えることがあります。
すなわち、「絶対の真実は存在しない。ただ人びとが納得できる物語だけがある」――
このことを深く了解することが賢明な態度、ということになります。
「オトギ話?」
「フィクションともいいます。信じることも信じないことも基本的に自由です」
「おもしろければいいかも」
「はい。なるほど、すごい、本当だ、だったらいいな、かもね、ほんとかな、で終始する世界ですね」
「好みだけがある?」
「それぞれの人の感じ方、考え方次第です。これが絶対という人も、あれが絶対という人もいる」
「宗教と同じかも」
「信じるか信じないかという意味で、宗教の世界とピタリ重なります」
「サンタクロースもそうかな」
「サンタクロースはある大きな物語の一部ですね」
科学はサンタクロースの世界には立ち入ることができません。
正しさを検証するために必要な素材が存在しないからです。
けれども、人間はなぜか世界の存在の根本について問いたくなる存在です。
カントという哲学者は、そうした形而上学的なテーマが永遠に結論の出ないことを示しました。
「どんなテーマですか」
「繰り返えすと、世界に始まりと終わりはあるか、人間は自由か、神は存在するのか」
「答えのない問題について考える愚かな動物が人間ですか」
「愚かで賢い、賢いけど愚か。どちらとも言えます」
「でも結論は出ない」
「ええ。これが正解だと信じる心があるだけです」
「なぜ正解と思うのだろうか」
「ある一つの物語が、その人にとって疑えない物語としてフィットするからです」
「フィット?」
「みずからの世界の区切り方に、正当性を与える物語だと感じるからでしょう」
でも一方に、そうじゃないと主張する人が必ずいます。
そして、それぞれの人の信じる動機は多様であっていいのですが、
信じることのちがう者同士が真正面から意見をぶつけ合えば対立は不可避です。
「困りましたね」
「信じることのちがう人同士は、そのままでは握手できません」
「対立を避けるにはどうしたらいいのだろう」
「第一には、手から槍を放すこと。つまり、自分が正しいという考えいったん横に置く」
「はあ」
「相手の正しさを頭から否定しない。そして、お互いが対等に話し合えるテーブルを用意する」
「クラス討論のようなものかな」
「はい。けれども本当は、もっと根本的なことがあります」
「なんですか」
「いくら考えても結論が出ない問題については考えることを止める。これが重要です」
「そうだと思うけど」
「考えるに値することについてだけ考えることを集中する」
「考えるに値することとそうでないことは見分けることができるのかな」
「科学の方法がお手本になりますが、原理として取り出しておく必要があります」
例えば、ぼくが自分のことを「正直者」と思っているとします。
けれど、誰かに「あなたはウソつきですね」といわれたらこの確信は大きく揺らぎます。
「あなたはウソつきだ」という人が親しい人であればあるほど、
そしてその数が多いほどダメージは致命的です。
つまり、自分が自分に抱くイメージは崩れ去り、深い傷を負うことになります。
「わかるけど、なぜなのかな?」
「その理由は、ぼくたちの心の成り立ち、構造にあります」
じぶんは正直者というぼく自身についてのぼくの確信は、
じつはぼくの心の中だけで完結することができません。
つまり、ぼく以外の人たちもぼくのことをきっと正直者だと思っているはずだ、
というもう一つの確信にぼくの確信が支えられているからです。
「他の人がどう思うかって、気にしすぎるのはおかしくありませんか」
「確かにへんですが、ぼくたちの心の成り立ちからいえば必然的にそうなります」
「一人で決めて一人で責任をもつだけじゃだめ?」
「そのことについてよく考えてみましょう」
人が抱く「このことは正しい確かなことだ」といった確信一般を内側からよくみると、
その人の勝手な思い込みだけではないことがわかります。
どういうことか。それは「このことは正しい」という確信というものには必ず、
「このことは他の人にとってもそうであるにちがいない」という信憑が伴っているからです。
「信憑?」
「はい。これは確かなことだという、心に訪れる確信の意識です」
「思い込みではない?」
「恣意的な思い込みではなく、疑うことができない事実として心に浮かぶものです」
「晴れた日は天気がいい、とか?」
「ちょっとちがうかな」
つまり、人間がものを考えるとき、一人だけ立つ場所で考えるのではなく、
いわば自分と他の人が〝共に立つ場所〟において考えているということです。
個人がそう信じている、確信しているというだけなら確信が揺らぐことはないはずです。
ところが、ぼくの世界はこうだといった確信はしばしば強まったり、弱まったりします。
ぼくが夕日の色を「赤い」と感じても、ほかの人たちが「ピンク」といえば、
ぼくは赤だと感じている自分の実感に自信がもてなくなります。
ぼくの中にあると信じられた世界という生きる舞台への信頼が揺らぐからです。
つまり、〝共に立つ場所〟との関係において自分の考えや信念が常に試されているわけです。
ぼくたちの言葉が通じ合うのも〝共に立つ場所〟に立つことを前提にしているからです。
もっといえば、このことは自然を含むさらに大きな〝共に立つ場所〟ともつながっています。
「よくわかりません」
「たとえば、役者と舞台みたいな関係を想像してみてください」
「はあ」
「一つの舞台の上に、あなたを含む多くの役者たちが存在している」
「演技をする場所ですか」
「そう。自分を含む大勢の人間が集う舞台があり、一人一人が役を演じている」
「共演者ですか」
「はい。同じ舞台に立つ役者同士という意識、つまりメンバーシップが全員に抱かれている」
「同じ劇を演じる仲間ということかな」
「それが舞台と役者の関係です」
「そこでお互いに言葉を交わし合う」
「まさしく。言葉はあなた自身のものですが、舞台にふさわしい言葉が常に選ばれていく」
「独り言でも?」
「独り言でも沈黙でも、舞台に展開する物語によって枠づけられています」
「そうかもしれない」
「現実の舞台ははっきりと形として見えませんが、人は常に舞台の上にいる」
「そしてみんなが参加する即興劇が演じられていく。そんな感じなのかな」
「はい。一方、モノとモノが出会っても自然の法則に従って反応しあうだけです」
「人間と人間との関係は単なる反応とはちがうかな」
「相互に関係しながら演技を繰り出し、相互に状態を変化させ、関係そのものを変化させていく」
「それが一つの舞台の物語みたいなものになるわけですね」
まとめると、自分にとっての世界と他人にとっての世界が、同じ一つのものである、
つまり共通の舞台を生きている――そうした意識のあり方を〝間主観性〟とも言います。
「かんしゅかんせい」
「あるいは〝共同主観性〟という言い方もあります」
「はあ」
「いわば人間同士の〝あいだ〟を結ぶ、お互いを関係づける大地のようなものです」
「結び合わせている大地」
「意識がそこから立ち上がり、そして生きられる舞台としての共通の大地」
「だから言葉が通じる、と信じられる」
「あるいは通じ合おうとする。この構造は、ぼくたちの世界経験すべての基礎となるものです」
人間にとって世界を経験するということは、この共通の大地に生きることでもある。
自己、他者、社会、モノ、そのカタチ、印象、感覚、感情……そこでいろいろな出来事に出会い、
関係を結び、相互に変化しながら関係を編み変えていくような〝共に立つ場所〟。
いわばそこを共通のキャンバスとして、ぼくたち一人一人が固有の〝絵〟を描いていく。
すると、ぼくの心は独立してあるというより、
人と人との関係、つまり〝あいだ〟に依存して立ち上がると考えたほうが妥当です。
〝あいだ〟は実体として三次元の空間にマップすることができません。
けれども、それが一人一人の経験や思考が立ち上がる場所として機能している。
そして舞台は一つではなく、無数の舞台が重なりあう形で生きられる点も重要です。
「このことは一人の性格について考えるとわかりやすくなります」
「どんなふうにですか」
たとえば、やさしい、慎重、頑固、短気、ネガティブ、気まぐれなど、人の個性はいろいろです。
普通、ぼくたちは性格を個人の属性として固定的に考えますが、本当にそうでしょうか。
ある人にとって慎重と見える人が、別の人にはノロマにみえ、さらに別の人には思慮深さになる。
一人の役者でも、舞台ごとに演じるキャラクターや役回りが異なるように、
ぼくたちは日常のそれぞれに関係する〝共に立つ場所〟ごとに、みずからを演じます。
一人の母は、妻であり、子であり、お客さんであり、国民であり、友であり、人類でもありうる。
つまり、舞台が変わるごとに一人の人間の意識のあり方や構えも変化していく。
「なるほど。舞台と役者か」
「はい。誰もがそうした構造の中で生きています」
正しくいえば、誰もがそういうふうに生きているはずだという、
ぼくが自分の心の中につくりあげている他者のイメージがそうだということです。
たぶんみんなも共通の舞台を生きているはずだ――という思いを意識の底に沈めて生きている。
ここから次のようなことが言えそうです。
世界という舞台はこういうものである、という一つの確信のイメージが訪れる。
そして誰にとってもそうにちがいないという、もう一つの確信がそこに伴っている。
この確信のイメージは「絶対の真実」とはちがって、
個別性や特殊性と対になる言葉――「普遍性」と呼ぶのがふさわしいと思います。
つまり、何かが正しい、絶対の正解という確信の意識を成り立たせているのは、
自分と他者が共同してつくる〝あいだ〟、〝共に立つ場所〟との関係にあるということです。
〝共に立つ場所〟が変化していくなら、それと共に絶対の正解も変化していく。
「そうすると、絶対の真実をめぐって争うのはまちがいですね」
「〝共に立つ場所〟を舞台と考えると、そこでの真実は物語の一部と捉えるが適切です」
「じゃあ、普遍性とは」
「普遍性はその舞台で成り立つ、舞台にふさわしい共通の了解と理解できます」
「絶対じゃない?」
「ええ。その舞台に参加する役者たちが創り上げる、物語のなかの真実です
「すると物語と共に真実も変化していく」
物語そして神話は、要するに、「わたしは世界をこんなふうに考える」という仮の説明です。
けれど、ある仮説が絶対に本当だとみんながみんな信じることができれば、
一つの集団や社会において、動かし難い真実として存在することになります。
つまり、「世界は神によってこうして創られた」といった〝真実の物語〟が出来上がります。
仮説が真実に格上げされて、それが信仰と呼ばれることもあります。
「けれども舞台はたくさん存在している」
「そう。唯一絶対の舞台というものは存在しない」
世界中のすべての人たちが、一つの〝真実の物語〟を信じれば何も問題はありません。
けれども、〝真実の物語〟があちこちで複数成立する場合、ある集団と別の集団のあいだには、
「どちらが真実か」という対立が必然的に生まれることになります。
お互いに証明することができない仮説なので、お互いの物語を尊重しあえば問題ないですが、
人間の歴史はそのような平和な方向に進みませんでした。
そう、対立点をめぐってお互いが血で血を争うがたくさんたくさん起きたのですね。
それが人間の歴史の悲しい現実でありつづけました。
カントという人の哲学は、そうした対立の悲劇を克服したいという動機から生まれました。
「動物はそんなこと考えないし、起こらないと思うな」
「そうですね。物語を求めるのは、人間という特殊な動物の特殊な性格のためです」
「答えの出ない問題について、なぜ人間は考えるのでしょうか」
「人間の意識は自由だからです」
「自由は自分勝手に考えたり、動いたりできることですか」
「いいえ。そうすると出口がなくなって独善に陥ります」
「自分こそ正しいということになる」
「要は、自分以外の人とのちがいを埋める手段が、暴力以外なくなってしまう」
自分の考えを絶対化すると、それ以外の考え方や感じ方がみずぼらしいものにみえてきて、
否定したくなったりします。
けれども、それが確かめようのない、検証しえないものであることが理解できれば、
そこにふさわしい〝物語〟を創り上げようという動機が生まれるように思います。
少なくとも、自分の信仰は絶対に譲れないという、出口のない頑なさは回避できるはずです。
「ねえ先生。人間はなぜ考えるのですか。動物とちがって言葉を使って考えるのでしょう」
「よりよく考えて、よりよく生きるためだと思います」
「よりよくって?どんなふうによりよくなのだろう」
人間も動物の一種です。考えるという能力も自然に与えられたものだと考えると、
自然という環境のなかで、より豊かに楽しく生きるためだと思います。
「正しいのはどっちだろう」と問うと、人間の思考はそこで行き止まりになります。
右か左かといった二項的な対立を前提にして相互に主張がせめぎあうと、
世界の区切り方が固定されて、それ以外の区切り方が発想できなくなるからです。
すると、それぞれの陣営に分かれて相互に否定しあうということが起こる。
そして、どっち側に味方しても対立の解消は相互の力関係によるほかなくなるでしょう。
そうではなくて、他にどんな区切り方があるのか、どんな関係の可能性がありうるのか、
対立しあう信念と信念の構造を乗り越えるにはどんな条件が必要だろうか――
本当はそう考えることのほうがずっと賢いやり方であり、理性的な態度なのです。
「なぜ存在するかを問うと、果てしなく考え続けるというブラックホールに入っていきます」
「でもそうしないでいられない?」
「心がそう出来ていると言うほかありません。一方では、それは人間の自由の本質であるともいえます」
「人間の自由」
「人間は言葉を使って無限に問いを発することができます」
「言葉…それが物語や宗教、いろいろな仮説をつくるのかな」
「たぶん言葉を獲得した時から、人間の世界は自然から少しズレた場所に移動した」
「はあ」
「具体的実在の世界から離脱した幻想の世界、自然のルールに縛られない言葉が創る自由の王国です」
「なぜ、なぜ、なぜ、…」というふうに問いを徹底すると、最後の最後に答えのない〝絶望〟の淵に沈みます。
いいかえると、この世界には最終的な根拠がどこにもないという虚しさ、
世界にある存在するの不思議さの極みに突き当たることになるでしょう。
この虚しさを抱えて生きることは耐えがたい。それゆえ、究極の真理を説明する物語が要請されていく。
つまりこうした苦悩を鎮めるために、人間は物語や神話を創り上げてきたのだと思います。
この世に最終的な根拠がないということは、最終的な救いがないということでもあるでしょう。
けれども、救いのなさに絶望するのは、救いを求める心があるからだともいえます。
「求める心があるから絶望があり、物語や神話も必然的に要請される」
「しかし物語の真実を言い張れば、別の人にとっての別の真実と対立する」
「ますます救われなくなる」
「ところが興味深いことに、ここに至ってはじめて気付かれることがあります」
「何でしょう」
「究極の答えのなさへの深い気づきから、別の思考のルートが開かれる契機が生じるということです」
「オトギ話、つまり物語や神話を使わないで?」
「はい。形而上学にわかれを告げ、新しい思考法、新たな思考の態度が見出されていく」
「絶望の果てに」
「つまり、物語をめぐる思考の限界が明示されることで、思考法そのものへの反省作用が訪れる」
「それもこれも絶望に直面したから?」
「ええ。みずからの思考の構えそのものがまちがっていたのではないか、という意識が萌す」
「意識そのもののあり方が対象化される」
「それは右か左かという発想の限界に気づくことでもある」
「そこからどう考えていけばいいのだろう」
「要するに、答えを縛る問いの拘束性から自由になる必要があります」
「考える対象の区切り方を変化させるということかな」
はい。一つの問いの立て方は、答えの内容と形式、その枠組みを指定します。
つまり、問うことは、世界のある区切り方の前提にしており、そのことに気づくことが大事です。
あれかこれかと問えば、あらかこれかという応答が接続される。
答えについて考えをめぐらせる前に、問い方の内容と形式が問われなければならない。
世界はなぜ存在するのか――そうした形而上学的な問いは、本来答えのない問いでしかない。
答えがどこかにあると考えると形而上学の世界であてどなく戯れることになります。
ただ、人間の意識の自由はそうした不可能な問いを発する権利をもちます。
そして、それぞれのフィットする物語を編み上げていく自由と権利もある。
けれども、そうした人間の自由の行使は同時に新たな対立を生みだす原因ともなりうる。
話を戻して、ニュートンとつなげてみましょう。
不思議でもなんでもないモノが落ちるということの不思議さにニュートンは気づきました。
ニュートンはどうして人が意に留めなかった重力の存在を対象化できたのか。
その答えは、ニュートンが世界を見る新しいゲームを見つけたことにあると思います。
どんなゲームか。それは一つ一つのモノや出来事、事象そのものではなく、
モノとモノ、事象と事象を結んでいる〝関係のパターン〟から世界を見るというゲームといえます。
「新しいゲーム」
「人びとが生きるゲームとは別のゲームのプレーヤーになったともいえます」
「誰も思いつかなかったゲームなのかな」
「すると、地上のすべてのモノとモノが引き寄せ合っている〝関係〟が見えた」
「モノそのものではない、モノとモノを結び合わせている関係を見るゲームか」
モノは誰にとっても等しく存在するといえますが、誰もが同じ見方で見ているわけではありません。
ぼくたちは無限の事実の重なりの中から、ごく限られた側面をピックアップして世界を見ます。
小さな石ころでも無限の見方、考え方、感じ方、色あいで捉えることができる。
もちろん無視することもできる。無視も含め事実と事実の重なりから情報をピックアップして、
世界をマップし、みずからを関係づけて組織化していく。
そうした一人一人の固有の方法、それが個性と呼ばれるものです。
「個性って実体じゃないわけ?」
「そう。それぞれの関心や目的、欲望のあり方と結びついた、世界を捉える方法、パターンといえます」
「形式、パターン?」
「世界の事象を固有の方法でマップして関係づけ自己を組織化する方法、それが個性の本質です」
一言でいえば、ある結び合わせるパターン。
このパターンに基づいて、モノとモノ、人と人、出来事と出来事が関係づけられていく。
結び合わせるパターンは実在的なものではなく、人を含む生命が世界と関係する構えともいえます。
そして、パターンは変化することも、消えることも、新しく生まれることもある。
「例えば、ある少女はお月さまと菜の花畑と電気を結び合わせて一つの俳句を創りました」
「はあ」
「菜の花が月のでんきつけました――小学2年生の俳句です。どうですか」
「いい。とても」
「生きることは、日々新たな結び合わせるパターンを創り上げる行為の連鎖ともいえます」
「生活すべてが?」
「そう思えなくても、つねに変化する環境で生きることがそのことを要請します」
「なぜ」
「生命はモノのようにそのまま自足することができず、つねに新たな組織化が必要なのです」
「ちょっと面倒な気もするな。新しい方法をみつけるにはどうしたらいいのだろう」
「陳腐に聴こえるかもしれませんが、謙虚になることです」
「謙虚って?」
「自分の見え方を絶対化しない。未だ知らない世界の見え方や考え方があることを認める」
「できるかな」
「簡単です。それは世界の豊かさにつながることで、とても楽しいことなのですから」
「ニュートンのように世界を外から見るといいのかな」
「世界を見るモードを切り替えれば外に出ることができます」
「どうやって?」
「当たり前のことを当たり前に見ている自分を対象化してみる」
「すると、当たり前が当たり前じゃなくなる?」
「当たり前と考えているせいで考えないでいることを、考えやすくなる場所が開かれる」
「それだけでOK?」
「キーワードは、事実と事実を結んでいる〝関係〟。そして、そのパターンへまなざしを向ける」
「関係と、そしてそのパターン」
「事実と事実は、見ることも触ることもできないパターンによって結ばれています」
「例えば?」
「心と心がやさしく寄り添うとき、結び合わせるパターンは〝愛〟と呼ばれる」
「あっ。怒りとか憎しみとかもそうかな」
「人間と人間、人間と自然、人間とモノ、モノとモノ、すべては透明な糸で結び合っています」
「見ることはできない」
「パターンはこの場所というふうに現実に位置づけることができません」
「〝愛〟は触ることができない」
「けれども、そうした無数の結び合わせるパターンによって世界は多彩に織り上げられている」
「う~ん。見えないパターンが無数にあるのか」
「無数の事象がランダムに重なりあう世界が、人間の眼には美しい季節の光景として映し出される」
「なるほど。その見えないパターンに感応するわけか」
「パターンは変化します。消えたり、新しく生まれたりする。このこともとても重要です」
「愛も変化していく。消えたり、生まれたり、復活したりする」
「パターンはそのものとして見ることも触ることもできない。けれど確実に世界を動かしていく」
「生命がいるからかな」
「そのとおり。だけど、人間はしばしばそのことに気づけなくなります」
単にモノが落ちるという事実だけに目を凝らしても重力には辿りつけません。
それは、一瞬だけ切り取られた世界の姿を静的に固定して捉えるまずいやり方です。
結び合わせている関係のパターンはつねに動的に変化していく。
そのことに気づくには、すべてが複雑に作用しあうネットワークから世界を捉える必要があります。
ニュートンは、モノとモノを結び合わせている普遍的なパターンを発見し、
そのしくみを解き明かして万有引力と名付けました。
なぜそうしようと思ったのかはわかりません。ひどく退屈だったのかもしれない。
けれど、そうすることがとても楽しかったのは事実だと思います。
「人間のまなざしには、習慣化した一定のフォームがあります」
「フォームって」
「ものの見方、感じ方、捉えカ、そして行動の仕方を決める自分自身の規則のようなものです」
「だったら、それは動物にもあるかな」
「あります。世界の見え方や感じ方は、生命それぞれの固有のフォームによって導かれます」
「ムカデの生きる世界と人間の生きる世界はちがう」
「ニュートンは世界を見る新しいフォームを生きたといえるかもしれません」
「エイリアン?」
「その可能性もあります」
「ちょっといやだな」
「けれども、そうなりたくなくてもなってしまうことが時として起こります」
「いやでも?」
「はい。そのことで新しい知恵の実に出会うこともある」
「でも苦しいかもしれない」
「かもしれない。けれど、フォームはつねに変化するものです」
「エイリアンと呼ばれたくはないな」
「わかりますが、エイリアンを嫌う理由はどこにもありません」
「はい」
エイリアンにとって、あなたはエイリアンでもある。
そのことの相互性に気づくことはとても大切です。
みずからとエイリアンとの区切るラインを絶対化すると、エイリアンとの関係は固定されます。
固定された関係のフォームからは、固定されたふるまい方だけが出力されるほかありません。
つまり、関係は変化することを封じられて、対立点を解消するチャンスが消えます。
では、何か質問があればどうぞ。
「先生!教えてください」
「どうぞ」
「結局、ニュートンはいいことをしたのでしょうか」
「とてもいい質問です。きわめて本質的な質問です」
「どう思います?」
「あなた自身の考えを語ってください」
「わかりません」
「ぼくにもわかりません」
「わからない」
「たぶん誰にもわからないでしょう」
少なくとも確実に言えることが一つあります。
新たなより良いゲームが生まれる可能性、そのための条件を問うことはできるということです。
ある一つのゲームが生みだす結果が人間にとってマイナスなら、別のゲームが要請される。
このとき行使されなくてはならないのが、人間にそなわる意識の自由という本質です。
新たな結び合わせるパターンの発見、そこから構成される新たなゲームの可能性――
そのすべにおいて人間の自由の本質が試されるだろうということです。
いいかえると、一つのゲームは別のゲームへ移行する可能性へ開かれたゲームでなければならない。
そしてそのことは人間の自由においてのみ担われるということだと思います。