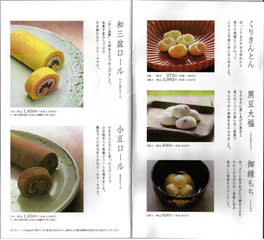「おいしいもの食べて温泉に入りに行こう」と意見が一致。
性格はかなり違うが、遊びにいく話はすぐにまとまる。
さいしょ、「五郎八でおうどんを食べて武芸川温泉」
と思ったのだけど、武芸川温泉「ゆとりの湯」は木曜休み。
ということで、西に行き先を変えて「モレラ」へ。

食べもののお店はたくさんあるのだけど、
最近ともちゃんが気に入ってるスパゲティの「にんにくや」。


ランチのお値打ちセットも食べてみたかったのだけど、
細めのスパゲティが大好物なので、と・・・
なんと、ふたりで大盛り3皿。
わたしはシンプルに、いつもの「トマトとにんにく」。
いつ食べてもおいしくて、これがいちばん気に入っている。



ともちゃんは、「熟成ベーコンのカルボナーラ」と
「なすとホウレン草のミートソース」。
余ったら責任を持ってたべるから、と「トマトとにんにく」も大盛り。
これだけ食べたら、お店の人に絶対覚えられたと思うけど、
大盛り3皿で、麺だけで400グラム分もある。

3対1くらいの割合で、わけっこして完食。
お気に入りの腰のある細麺で、
どれを注文してもはずれがないおいしさでした。
前回食べたのは、スパゲティ大盛り2皿と、一度食べてみたかった、



「はちみつトーストやみつきシナモンかけ」

愛用のデジカメと携帯はご愛嬌(笑)。


モレラでワインを買って、締めは「根尾川谷汲温泉」へ。

温泉までの道案内に、「つるつる美人の湯」と書いてあった通り、
「つるつるぬるぬる」のお湯で、お肌がすべすべになりましたした。
写真をクリックすると拡大。その右下のマークをクリックするとさらに拡大
最後まで読んでくださってありがとう

2008年も

 遊びに来てね
遊びに来てね 
 また明日ね
また明日ね



























 左の下の図をご覧いただきたい。厚生年金の加入者がこうして増えていけば、国民年金に入る人は半減し、ほぼ自営業者だけが残ることになる。
左の下の図をご覧いただきたい。厚生年金の加入者がこうして増えていけば、国民年金に入る人は半減し、ほぼ自営業者だけが残ることになる。 







 ■人物略歴
■人物略歴