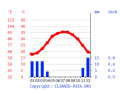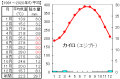江馬修(1889~1975)という作家がいる。読み方は「えま・しゅう」になっているが、本名は「なかし」なんだという。飛騨高山の生まれで、明治2年に故郷で起きた「梅村騒動」を描いた『山の民』という大作小説で知られている。一部では島崎藤村『夜明け前』を越える傑作と評価する人もいるようだが、文壇ではほぼ無視されてきた。文庫に入ったこともなく、僕も読んだことがない。代表作を読んでないぐらいだから、他の本も知らない。今ではほとんど忘れられた作家に近い。
ところが、8月のちくま文庫新刊で(金子光晴『詩人/人間の悲劇』とともに)、江馬修の『羊の怒る時』という本が出たのである。それが「関東大震災の三日間」と副題が付いた稀有のドキュメントなのである。もとは1925年に聚芳閣という出版社から出されたまま忘れられていた。1989年に影書房というところから再刊されたというけど、全く知らなかった。一般的には忘れられていた本だと思うが、これは大発見である。関東大震災理解の基礎文献として必読になると思う。

江馬修は今ではほとんど知られてないから、僕は「貧乏文士」だと思い込んでいた。ところが調べてみると、1916年の『受難者』という本がベストセラーになり、当時は人気作家だったらしい。震災当時は代々木辺りに住んでいた。もっと細かく言えば「初台」で、「自警団」の合言葉は「初」「台」だったと出ている。この本では「東京へ行く」、「東京では」という言葉が出て来る。今では世界に知られる新宿や渋谷だが、当時は豊多摩郡だった。東京市外だったのである。東京市が拡大され、35区体制になったのは震災後の1932年のことである。その辺りにはお屋敷も建ち並び、隣家は「I」という退役中将だった。
まず大地震が起きる。このままでは家がつぶれてしまう恐怖が描かれる。6歳と3歳の女児がいて、まず子どもを助けなければと思って、下の子を連れて庭に出た。前に書いたけれど、夏目漱石の自伝的作品と言われる『道草』では、主人公が地震の時に一人で庭に逃げてしまう。妻から「あなたは不人情ね。自分一人好ければ構わない気なんだから」と言われると、「女にはああいう時にも子供の事が考えられるものかね」と答える。このトンデモ主人公には驚いたが、さすがに当時の男でもそんな人ばかりではなかった。まあ江馬は「人道主義的作家」として有名だったらしいけど。
自分の家は何とかつぶれずに助かるが、周囲を見ると全壊した家もある。大変だと手助けに向かう。近くには交際があった朝鮮人学生もあり、無事だった朝鮮人たちが他の家を手助けしている。「李君」はついに壊れた家から幼子を助け出す。そんな民族を越えた助け合いが直後にはあったのである。遠くの空がなにやら怪しくなり、どうも東京市各地で火事が発生しているという噂が流れる。まだラジオもなく、新聞も発行できず、情報は「噂」と「警察」だけになってしまった。
 (江馬修)
(江馬修)
第1日が終わり第2日になると、「朝鮮人さわぎ」が起きてくる。朝鮮人も震災にあって逃げ回るだけなのに、その朝鮮人が放火などをして回っているという「噂」が流れる。「朝鮮人」が騒いでいるのではなく、日本人が騒いでいるだけだったので、本来は「日本人さわぎ」とか「自警団さわぎ」と呼ぶべきだろう。(これは袴田巌さんは無実なのに、「袴田事件」と呼ぶのがおかしいのと同じである。)しかし、当時書かれた文献には皆「朝鮮人さわぎ」として出て来るのである。
そして著者自身も「そういうことも無いでは無いだろう」と思う。著者自身が個人的に親しくしている朝鮮人は立派な学生ばかりだが、中には悪い人もいるだろう。近くには朝鮮総督を務めたT伯爵邸もあるから、この地域は標的にされるかもしれないと考えてしまった。これは初代朝鮮総督の寺内正毅と考えられる。つまり、日本人は朝鮮人から恨まれることがあると認識していたからこその恐怖なのである。一般民衆が「暴力」に囚われた理由は著者にもよく理解出来ない。著者自身も朝鮮人と疑われたりして、民衆の中にある恐ろしい「殺意」に恐怖を感じている。
その間に本郷にいる兄一家が心配で、危険を冒して訪ねたりしている。この兄は浅草区長をしていた江馬健という人だという。途中で大火災の実態と「朝鮮人さわぎ」で各町ごとに自警団による「結界」が作られている実情が語られる。東京市の西側で比較的被害が少なかった地区に住んでいた江馬ならではの観察が鋭い。ラスト近くでは兄を通して、浅草区の実情を視察している。兄は浅草寺が焼け残ったことを喜ぶとともに、「吉原復興」が急務だと考えている。
江馬は後に無事が確認された朝鮮人学生を匿っている。先に子どもを救った李君は、知人を探すために市内に出掛けて戻らない。助けて貰った恩義がある母親は何とか李君を探し回るのだが…。どうしてこんなことが起きたのか。結局、毎夜朝鮮人が押し寄せると言われて「自警団」に駆り出され、著者も周囲の人々も疲弊していく。火事に合わなかった江馬にとって、大震災の最大の恐怖は「朝鮮人さわぎ」だったのである。何故、こんなことになったのか、著者はこの段階では「同じ人間だ」という認識を持てるには「教養」が大切だと考えている。
その後の江馬は社会主義に近づいて行く。関東大震災を経て、「人道主義」では日本人は変わらないと考えて行ったのである。震災で苦労した妻とも別れ、その後は波乱の人生を送った。再婚した妻がいたが、戦後になって『綴方教室』で知られた豊田正子と暮らすようになり、晩年にはさらに別の女性と暮らしたという。1946年には日本共産党に入党したものの、1966年には中国派として離党した。これはウィキペディアの情報だが、興味深い経歴の人物である。ルポの観察力や文章力は確かで、この本は重大な出来事を後世に書き残した貴重な本だ。
ところが、8月のちくま文庫新刊で(金子光晴『詩人/人間の悲劇』とともに)、江馬修の『羊の怒る時』という本が出たのである。それが「関東大震災の三日間」と副題が付いた稀有のドキュメントなのである。もとは1925年に聚芳閣という出版社から出されたまま忘れられていた。1989年に影書房というところから再刊されたというけど、全く知らなかった。一般的には忘れられていた本だと思うが、これは大発見である。関東大震災理解の基礎文献として必読になると思う。

江馬修は今ではほとんど知られてないから、僕は「貧乏文士」だと思い込んでいた。ところが調べてみると、1916年の『受難者』という本がベストセラーになり、当時は人気作家だったらしい。震災当時は代々木辺りに住んでいた。もっと細かく言えば「初台」で、「自警団」の合言葉は「初」「台」だったと出ている。この本では「東京へ行く」、「東京では」という言葉が出て来る。今では世界に知られる新宿や渋谷だが、当時は豊多摩郡だった。東京市外だったのである。東京市が拡大され、35区体制になったのは震災後の1932年のことである。その辺りにはお屋敷も建ち並び、隣家は「I」という退役中将だった。
まず大地震が起きる。このままでは家がつぶれてしまう恐怖が描かれる。6歳と3歳の女児がいて、まず子どもを助けなければと思って、下の子を連れて庭に出た。前に書いたけれど、夏目漱石の自伝的作品と言われる『道草』では、主人公が地震の時に一人で庭に逃げてしまう。妻から「あなたは不人情ね。自分一人好ければ構わない気なんだから」と言われると、「女にはああいう時にも子供の事が考えられるものかね」と答える。このトンデモ主人公には驚いたが、さすがに当時の男でもそんな人ばかりではなかった。まあ江馬は「人道主義的作家」として有名だったらしいけど。
自分の家は何とかつぶれずに助かるが、周囲を見ると全壊した家もある。大変だと手助けに向かう。近くには交際があった朝鮮人学生もあり、無事だった朝鮮人たちが他の家を手助けしている。「李君」はついに壊れた家から幼子を助け出す。そんな民族を越えた助け合いが直後にはあったのである。遠くの空がなにやら怪しくなり、どうも東京市各地で火事が発生しているという噂が流れる。まだラジオもなく、新聞も発行できず、情報は「噂」と「警察」だけになってしまった。
 (江馬修)
(江馬修)第1日が終わり第2日になると、「朝鮮人さわぎ」が起きてくる。朝鮮人も震災にあって逃げ回るだけなのに、その朝鮮人が放火などをして回っているという「噂」が流れる。「朝鮮人」が騒いでいるのではなく、日本人が騒いでいるだけだったので、本来は「日本人さわぎ」とか「自警団さわぎ」と呼ぶべきだろう。(これは袴田巌さんは無実なのに、「袴田事件」と呼ぶのがおかしいのと同じである。)しかし、当時書かれた文献には皆「朝鮮人さわぎ」として出て来るのである。
そして著者自身も「そういうことも無いでは無いだろう」と思う。著者自身が個人的に親しくしている朝鮮人は立派な学生ばかりだが、中には悪い人もいるだろう。近くには朝鮮総督を務めたT伯爵邸もあるから、この地域は標的にされるかもしれないと考えてしまった。これは初代朝鮮総督の寺内正毅と考えられる。つまり、日本人は朝鮮人から恨まれることがあると認識していたからこその恐怖なのである。一般民衆が「暴力」に囚われた理由は著者にもよく理解出来ない。著者自身も朝鮮人と疑われたりして、民衆の中にある恐ろしい「殺意」に恐怖を感じている。
その間に本郷にいる兄一家が心配で、危険を冒して訪ねたりしている。この兄は浅草区長をしていた江馬健という人だという。途中で大火災の実態と「朝鮮人さわぎ」で各町ごとに自警団による「結界」が作られている実情が語られる。東京市の西側で比較的被害が少なかった地区に住んでいた江馬ならではの観察が鋭い。ラスト近くでは兄を通して、浅草区の実情を視察している。兄は浅草寺が焼け残ったことを喜ぶとともに、「吉原復興」が急務だと考えている。
江馬は後に無事が確認された朝鮮人学生を匿っている。先に子どもを救った李君は、知人を探すために市内に出掛けて戻らない。助けて貰った恩義がある母親は何とか李君を探し回るのだが…。どうしてこんなことが起きたのか。結局、毎夜朝鮮人が押し寄せると言われて「自警団」に駆り出され、著者も周囲の人々も疲弊していく。火事に合わなかった江馬にとって、大震災の最大の恐怖は「朝鮮人さわぎ」だったのである。何故、こんなことになったのか、著者はこの段階では「同じ人間だ」という認識を持てるには「教養」が大切だと考えている。
その後の江馬は社会主義に近づいて行く。関東大震災を経て、「人道主義」では日本人は変わらないと考えて行ったのである。震災で苦労した妻とも別れ、その後は波乱の人生を送った。再婚した妻がいたが、戦後になって『綴方教室』で知られた豊田正子と暮らすようになり、晩年にはさらに別の女性と暮らしたという。1946年には日本共産党に入党したものの、1966年には中国派として離党した。これはウィキペディアの情報だが、興味深い経歴の人物である。ルポの観察力や文章力は確かで、この本は重大な出来事を後世に書き残した貴重な本だ。