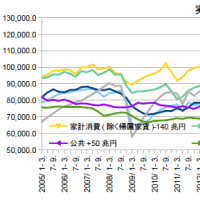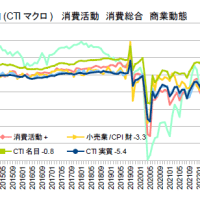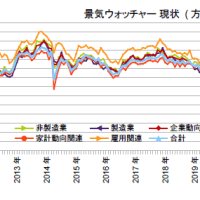日本は、物価、消費、賃金、投資、成長が停滞する「低温経済」である。物価は、需要と供給で決まるものなので、物価が上がらないのは、消費が乏しいからと、すぐに察しがつく。なぜ、消費が乏しいかと言えば、アベノミクスでは、消費税と社会保険料を引き上げ、徹底して消費を圧殺してきたことが主な要因として挙げられる。この間、一般政府の財政収支は、GDP比1%以上のペースで改善しており、緊縮が無関係だったとは、とても言えない。
消費が増えなければ、それを目指した設備投資が増えるはずもなく、国内での売上が伸びなければ、企業は賃金を上げられない。これでは、成長が停滞するのも当然で、低温経済には、何の不思議さも、「パズル」もない。ところが、「緊縮は経済に悪影響をもたらさない」という観念を持ってしまうと、理由が分からなくなって、「パズル」に見えてくる。そして、ひたすら、ミクロの生産性向上を訴えるようになるのである。
………
日本経済のマクロ分析をする上で、最も重要な数字は消費率である。下図で分かるのは、明らかに、好況には下がり、不況には上がることだ。すなわち、消費率は景気で決まり、ライフスタイルや人口構成に伴うミクロの選好の変化によらないことが示される。もし、それらが理由だとしたら、5年程の中期でたびたび屈折するのは不自然だろう。これが「経済は、ミクロの集積によらず、マクロで決まる」という具体的な意味内容である。
その消費率がどうやって決まるかと言うと、消費の残りが貯蓄であり、貯蓄=投資なので、投資の動きが消費を裏から決めている。実際、景気が良くなる局面では、まず、投資が加速し、遅れて消費が加速する。だからこそ、消費率とは裏返しで、投資率は、好況には上がり、不況には下がることになる。一般に「投資は景気の原動力」とされるが、こうした常識的な見方は、的を射たものだ。
(図)

問題は、投資がどのように決まるかである。理論を脇に置いて、戦後75年をつぶさに眺めると、いつも、輸出が景気回復の出発点になっている。輸出が設備投資を増やし、所得、賃金、消費へと波及していく。需要が需要を呼ぶのである。ただし、波及は、1997年を境に変わる。賃金と消費への波及が消え、デフレに陥ってしまう。これは、輸出で景気が回復しだしたところで、早々と緊縮を始め、波及を阻害するようになったためである。
バブル崩壊が一服した1995年からリーマンショック前の2007年までの13年間、設備投資は、2期前の輸出、住宅、公共の重回帰分析で、ほぼ完全に予測できた。ミクロの行動変化の要因を探るまでもない。その関係は、リーマンショックと東日本大震災で乱れるが、打撃から癒えた2012年以降は、再びパラレルな関係へと復している。設備投資は、輸出に強く影響され、追加的な3需要をなぞるように動くというのが経験的事実なのである。
実は、戦後75年の日本経済の歩みからすれば、そうしたパラレルな関係は異様なものだ。かつては、設備投資は、いつしか輸出から離れ、内需に反応して自律的に拡大して行ったからである。つまり、財政が早々と需要を抜くようになったために、内需に対する設備投資の反応が消え、輸出の動向から離れられなくなったのだ。パラレルであることは、需要が循環する自律的な成長へと発展できなくなり、デフレを脱せなくなった姿を描いてもいる。
………
個々の企業や労働者の生産性を向上させれば、より多くの生産ができ、豊かになれるという思考は、とても素直なものだ。それゆえ、一国の成長も、ミクロの集積で決まると直観してしまう。ここで、「成長は需要で決まる」というオールド・ケインジアンの見方を示されても、鶏と卵の循環論法を聞かされているようで得心がいかず、どこに論理の基礎を置き、議論の出発点にしているのかと、訝しんでしまう。
そうこうするうち、金利を下げ、法人税を軽くし、規制を緩和して、ミクロの収益性を高めれば、設備投資は増え、生産性が向上し、経済成長も実現すると信じ込むようになる。ところが、一歩、企業経営の現場に踏み込めば、いかに実態と乖離しているかが分かる。売上の動向ばかり気にして、収益性は二の次であり、逆説の「売ってはいけない」というビジネス本が注目される始末だ。現実には、事業利回りより需要リスクを遥かに重く見ているのである。
内需が見通せないのに、設備投資をするとか、賃上げや正規雇用を増やすとかしていたら、緊縮で内需が圧殺されたときには、あまりに危険だ。日本の経営者は、内需なき日本に見切りをつけ、海外に投資するようになっている。内需の成長がないなら、経営コストを下げてもらえたら、それで十分だ。経営者が消費増税や福祉削減に賛成なのは、そんな理由である。マクロでの緊縮は、経営者のミクロの成長志向まで変えてしまったのである。
………
地球に優しい緊縮財政は、経済社会を隅々まで腐らせてしまった。より豊かにという願いを挫いてばかりいたら、人心が病んでしまうのも仕方あるまい。しかし、理由さえ分かれば、脱する方法も明確に描ける。毎年の歳出増を高齢化による自然増の5000億円に限定するのをやめ、7000億円程を積み増し、緊縮を緩めれば良い。その中身を非正規への育児休業給付の実現などに充てれば、結婚が可能になり、少子化も改善されるはずだ。こうすれば、普通に成長すると、税収の自然増と見合い、財政は中立になる。つまり、締め過ぎて景気を悪くし、やおら経済対策を打つという「ブレーキ&アクセル」の不効率を改めるわけである。
今回のコラムは、タイトルで分かるように、若手の官庁エコノミストの著書に触発されて記したものだ。著書自体は、アカデミズムでも評価される立派な内容だが、現実は、また別である。理論と現実の乖離を痛感することが経済運営には必要だと思う。昔は、赤羽隆夫さんのように、ファクトファインデングで真っ向から主流派経済学に反抗したツワモノもいた。官庁エコノミストは、学者と違い、日本経済に責任を負う。データばかり見てきたオールドなケインジアンとしては、理論が目隠しする、需要が動かす経済の実態を知ってもらいたいと切に願うのである。
(今日までの日経)
ホルムズ海峡の船舶も イラン報復発言 衝突懸念 中東全域に。60代後半の就労、企業に努力義務 「70歳定年法」新たに4項目。
消費が増えなければ、それを目指した設備投資が増えるはずもなく、国内での売上が伸びなければ、企業は賃金を上げられない。これでは、成長が停滞するのも当然で、低温経済には、何の不思議さも、「パズル」もない。ところが、「緊縮は経済に悪影響をもたらさない」という観念を持ってしまうと、理由が分からなくなって、「パズル」に見えてくる。そして、ひたすら、ミクロの生産性向上を訴えるようになるのである。
………
日本経済のマクロ分析をする上で、最も重要な数字は消費率である。下図で分かるのは、明らかに、好況には下がり、不況には上がることだ。すなわち、消費率は景気で決まり、ライフスタイルや人口構成に伴うミクロの選好の変化によらないことが示される。もし、それらが理由だとしたら、5年程の中期でたびたび屈折するのは不自然だろう。これが「経済は、ミクロの集積によらず、マクロで決まる」という具体的な意味内容である。
その消費率がどうやって決まるかと言うと、消費の残りが貯蓄であり、貯蓄=投資なので、投資の動きが消費を裏から決めている。実際、景気が良くなる局面では、まず、投資が加速し、遅れて消費が加速する。だからこそ、消費率とは裏返しで、投資率は、好況には上がり、不況には下がることになる。一般に「投資は景気の原動力」とされるが、こうした常識的な見方は、的を射たものだ。
(図)

問題は、投資がどのように決まるかである。理論を脇に置いて、戦後75年をつぶさに眺めると、いつも、輸出が景気回復の出発点になっている。輸出が設備投資を増やし、所得、賃金、消費へと波及していく。需要が需要を呼ぶのである。ただし、波及は、1997年を境に変わる。賃金と消費への波及が消え、デフレに陥ってしまう。これは、輸出で景気が回復しだしたところで、早々と緊縮を始め、波及を阻害するようになったためである。
バブル崩壊が一服した1995年からリーマンショック前の2007年までの13年間、設備投資は、2期前の輸出、住宅、公共の重回帰分析で、ほぼ完全に予測できた。ミクロの行動変化の要因を探るまでもない。その関係は、リーマンショックと東日本大震災で乱れるが、打撃から癒えた2012年以降は、再びパラレルな関係へと復している。設備投資は、輸出に強く影響され、追加的な3需要をなぞるように動くというのが経験的事実なのである。
実は、戦後75年の日本経済の歩みからすれば、そうしたパラレルな関係は異様なものだ。かつては、設備投資は、いつしか輸出から離れ、内需に反応して自律的に拡大して行ったからである。つまり、財政が早々と需要を抜くようになったために、内需に対する設備投資の反応が消え、輸出の動向から離れられなくなったのだ。パラレルであることは、需要が循環する自律的な成長へと発展できなくなり、デフレを脱せなくなった姿を描いてもいる。
………
個々の企業や労働者の生産性を向上させれば、より多くの生産ができ、豊かになれるという思考は、とても素直なものだ。それゆえ、一国の成長も、ミクロの集積で決まると直観してしまう。ここで、「成長は需要で決まる」というオールド・ケインジアンの見方を示されても、鶏と卵の循環論法を聞かされているようで得心がいかず、どこに論理の基礎を置き、議論の出発点にしているのかと、訝しんでしまう。
そうこうするうち、金利を下げ、法人税を軽くし、規制を緩和して、ミクロの収益性を高めれば、設備投資は増え、生産性が向上し、経済成長も実現すると信じ込むようになる。ところが、一歩、企業経営の現場に踏み込めば、いかに実態と乖離しているかが分かる。売上の動向ばかり気にして、収益性は二の次であり、逆説の「売ってはいけない」というビジネス本が注目される始末だ。現実には、事業利回りより需要リスクを遥かに重く見ているのである。
内需が見通せないのに、設備投資をするとか、賃上げや正規雇用を増やすとかしていたら、緊縮で内需が圧殺されたときには、あまりに危険だ。日本の経営者は、内需なき日本に見切りをつけ、海外に投資するようになっている。内需の成長がないなら、経営コストを下げてもらえたら、それで十分だ。経営者が消費増税や福祉削減に賛成なのは、そんな理由である。マクロでの緊縮は、経営者のミクロの成長志向まで変えてしまったのである。
………
地球に優しい緊縮財政は、経済社会を隅々まで腐らせてしまった。より豊かにという願いを挫いてばかりいたら、人心が病んでしまうのも仕方あるまい。しかし、理由さえ分かれば、脱する方法も明確に描ける。毎年の歳出増を高齢化による自然増の5000億円に限定するのをやめ、7000億円程を積み増し、緊縮を緩めれば良い。その中身を非正規への育児休業給付の実現などに充てれば、結婚が可能になり、少子化も改善されるはずだ。こうすれば、普通に成長すると、税収の自然増と見合い、財政は中立になる。つまり、締め過ぎて景気を悪くし、やおら経済対策を打つという「ブレーキ&アクセル」の不効率を改めるわけである。
今回のコラムは、タイトルで分かるように、若手の官庁エコノミストの著書に触発されて記したものだ。著書自体は、アカデミズムでも評価される立派な内容だが、現実は、また別である。理論と現実の乖離を痛感することが経済運営には必要だと思う。昔は、赤羽隆夫さんのように、ファクトファインデングで真っ向から主流派経済学に反抗したツワモノもいた。官庁エコノミストは、学者と違い、日本経済に責任を負う。データばかり見てきたオールドなケインジアンとしては、理論が目隠しする、需要が動かす経済の実態を知ってもらいたいと切に願うのである。
(今日までの日経)
ホルムズ海峡の船舶も イラン報復発言 衝突懸念 中東全域に。60代後半の就労、企業に努力義務 「70歳定年法」新たに4項目。