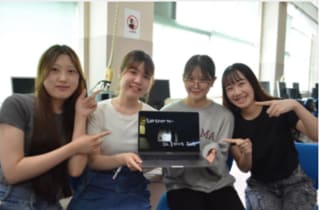クレア9/16(土) 9:02配信
現在、日本に約3,300基ある灯台。船の安全を守るための航路標識としての役割を果たすのみならず、明治以降の日本の近代化を見守り続けてきた象徴的な存在でもありました。
【画像】神威岩など周辺の海は奇岩も多い。
建築技術、歴史、そして人との関わりはまさに文化遺産と言えるもの。灯台が今なお美しく残る場所には、その土地ならではの歴史と文化が息づいています。
そんな知的発見に満ちた灯台を巡る旅、今回は2020年に『熱源』で第162回直木三十五賞を受賞した川越宗一さんが北海道の神威岬灯台を訪れました。
灯台にある深い思い出
灯台には深い思い出がある。
といっても、船乗りや灯台勤務をやっていたわけではない。
時は2019年、たしか2月だった。当時のぼくは北海道やサハリン、南極が舞台になる小説を書いていた。いずれも雪深い地だが、ぼくはずっと比較的温暖な場所に住んでいたから、雪については「白くて冷たい」くらいしか分かっていなかった。そこで遅ればせながらの取材を思い立ち、わざわざ冬を選んで北海道へ取材旅行に出かけた。
折悪しく、記録的な寒波が北海道を揉みしだいていた。歩道の左右は削られた雪の壁が背丈ほどの高さになっていたり、目的地のひとつだった墓地は除雪が追い付かず立ち入りできなかったりと、なかなか貴重な体験をした。
旅行の二日めか三日め、道北にある海辺の駅で下車した。窓には花のように美しい結晶が這い、海は凍っていた。寒さでバッテリーがいかれたスマートフォンは電源が勝手に落ちるから、撮りたい写真が撮れずに困った。
行きたかった先々を訪れたり断念したりしていると夕方になったので、その日の宿を目指して路線バスに乗った。ほかに乗客はおらず、外では雪が激しくなっていた。思わず、スマートフォンを両手で挟んで温めていた。
下車予定だったバス停に着いたころは日が暮れていて、停留所の標識を照らす明かりは吹きすさぶ濃密な雪にかすんでいた。これ歩けないだろ、と思った瞬間、プシュッとバスの扉が開いた。運転士さんの背は「今日も何事もない」と言わんばかりの落ち着きを見せている。地元の人にとって、これくらいの雪は日常茶飯事なのだろうか。
おそるおそるバスを降りる。低いエンジン音が遠のいてゆく。ぼくの周囲は雪が街灯に光る白い闇、その向こうは夜の黒い闇である。目指す宿までは歩いて五分もかからぬ距離だが、文字通り手探りで行くには遠すぎる。スマートフォンはいまのところ動作しているから地図アプリを見ればよいかもしれないが、いつまた電源が落ちるか分からない。
凍死、という言葉を我が身について覚えたのは、初めてだった。今となれば、雪に慣れぬ人間があわてていただけとも思えるが、その時はほんとうに怖かった。
ふと見上げた。水平方向に救いはない、という諦めだったかもしれない。かといって上方向には天国しかないのだが、などと考える余裕もなく、ともかく見上げた。
量感を伴った白い光が虚空に明滅していた。いかん走馬灯だ、と思い至るほどにまだ切羽詰まっていなかったが、不思議な現象に思わず見とれてしまった。
「道が分からなければ、灯台を目印にしてください」
宿の予約時に言われた言葉を思い出した。ぼくは灯台の光を目指して道を埋める新雪を踏み、幸いにも元気だったスマートフォンで位置と方向を確かめながら、なんとか宿にたどり着いた。
かくてぼくは生還し、小説も無事に書き上げることができた。うまく書けたかは心許ないが、最後まで書けたのは北海道の雪に学ばせていただいたおかげだし、書くための命は灯台の光がくれたようなものだ。
それから数年が経った。以上の思い出は関係ないはずだが、くだんの小説のおかげか、ぼくはリレー紀行「『灯台』を読む」に北海道担当として参加させていただくこととなった。
レンズ、北の地へ還る
6月下旬、ぼくが住んでいる京都市は晴れていれば気温30度超えの真夏日、そうでなくても蒸し暑い日が続いていた。
久しぶりの飛行機で降り立った新千歳空港は、涼しくて気持ちよかった。札幌で一泊した翌朝は、ありがたいことに快晴。担当編集者、カメラマン氏と合流し、灯台を巡る旅は始まった。
最初の目的地は神威岬灯台。日本海を望む積丹半島から突き出た岬の先端にある。札幌からはカメラマン氏がハンドルを握る車でだいたい西へ、二時間ちょっとである。
ちなみに積丹半島の海岸のほとんどは、国定公園になっている。青く澄み渡った海、寄せる波が作った崖や奇岩、海岸からすぐ立ち上がる優美な山。独特の景観が楽しく、車中はちっとも退屈しなかった。
神威岬の根元あたりでぐるりと湾曲する坂を上れば、広々とした駐車場とレストハウス「カムイ番屋」がある。ここから伸びる遊歩道を行けば神威岬灯台に至る。
まずカムイ番屋に入った。一階のお土産屋と食堂を眺めながら階段を上がる。灯台にまつわる展示があるという二階に至ったところで、ウワッと声を上げてしまった。
ほのかに青緑色を帯びたガラスの輪を、細い金属の骨で見上げる高さまで積み上げた巨大な構造物が、そこにあった。輪は上に行くほど小さくなり、全体は釣り鐘に似た形を成している(「釣り鐘」の言葉は説明書きから取ったが、ぼく自身はアポロ宇宙船を想起した)。レトロともSFチックとも言える不思議な佇まいだった。
構造物は第一等不動レンズと呼ばれている。凸レンズをばらばらにして薄く組み直したフレネルレンズがあり、その上下をプリズムで挟み、左右に引き伸ばして円柱の形に作っている。ようするに全周がレンズという代物だ。等級は厳密にいえば焦点距離を、おおまかには大きさを表し、第一等は最も大きい。展示されている不動レンズは高さ3.05メートル、直径1.85メートル。灯器が入っていたというレンズの中は、椅子と小振りな机を置いて原稿が書けそうなくらいの空間がある。こんな興趣あふれる部屋では気が散って原稿どころではないだろうけど。
この不動レンズは、生まれて百五十年近くの長い歳月を経ている。フランスで製造され、明治9年(1876)ごろに宮城県の金華山灯台で使われた。大正12年(1923)に神威岬灯台の二代目レンズとして移設され、昭和35年(1960)の灯台建て替え後は、遠く大阪のレジャー施設「みさき公園」に運ばれ、展示されていた。時の流れでみさき公園は運営会社が撤退していったん閉園の運びとなり、レンズは落ち着く場所を失う。これを知った地元の人々が運動して去年、約60年ぶりに神威岬に帰ってきた。長い時間を歩んだ不動レンズは、遺すべき貴重な産業遺産と言えよう。
しばしレンズに見惚れたあと、(なんと)積丹町の町長から灯台についていろいろご説明をいただいた。伺った内容はとても興味ぶかかったが、「灯台は町の誇りです」という言葉がとくに印象的だった。レンズの里帰りも、誇りを取り戻すための運動だったのかもしれない。
伝承と歴史が彩る岬
神威岬には、ひとつの伝承がある。
昔むかし、奥州にいた源義経は蝦夷地へ逃れ、神威岬から大陸へ渡った。義経を慕っていたアイヌの女性チャレンカは後を追うが、一行はもう出発していた。チャレンカは悲嘆に暮れ、「婦女を乗せてこの岬を過ぎる船はみな沈む」と言い残して岬から身を投げた。
時は下って江戸時代。蝦夷地を任されていた松前藩は、神威岬から東への女性の通行を禁じた。理由は不明だが、チャレンカの伝承を利用して統治しにくい遠隔地への和人の定住を防いだのでは、という推測もある。岬そのものも神罰を恐れて女人禁制の地となっていた。
そして幕末、ペリー提督の来航を受けた江戸幕府は国防のため蝦夷地を直轄化し、また神威岬以遠の女性渡航を解禁した。妻を連れて赴任する幕府の役人は、船上から「主君の命で通るのに、どうして神罰を受けねばならないか」という言葉と一発の銃弾を放って、岬の沖を通過したという。
近代という時代は、それ以前の感覚を「迷信」と呼んで切り捨ててゆく過程でもあった。近代とて優生思想や人種主義などの新たな迷信を生んだが、それはさておく。伝承が生まれ、その伝承が統治に利用され、のちに打ち砕かれ、やがて近代的な灯台が建てられたという神威岬の経緯には、人類史の要点が詰め込まれているような気がした。
さて、現在の神威岬は、灯台へ続く遊歩道「チャレンカの小道」が整備されている。その入り口には「女人禁制の地」と書かれた鳥居型の門がある。
門の手前、遊歩道を見渡せる場所で、ぼくはつい立ちすくんでしまった。
空も海も、澄んで青い。岬は海からこんもり盛りあがり、夏草と小さな花に覆われながら長く伸び、ところどころで削り取ったように岩肌を剥きだしにしている。眺めるだけなら、手を叩いて称賛したくなるほど良い景色である。
ただし、行くとなると話が変わる。遊歩道は岬の尾根を通っていて、けっこう起伏が大きい。左右は急斜面か崖で、大小の岩がごろごろ転がる海岸まで急な角度で落ち込んでいる。怖い、怖くないの二つに世界を分ければ、これからの道は確実に「怖い」に入る。
案内してくれる海上保安庁の柴山さんと並んで、こわごわ遊歩道に足を踏み入れる。強い風に揺さぶられ、足元がおぼつかない。
「神威岬も含めて、いまの灯台はほとんど無人です」
柴山さんがにこやかに説明してくれる。
「ときおり点検で人をやるくらいですが、だいたいの灯台は道が険しいか船で行くような場所にありますから、天候が荒れたときは点検を延期します」
「きょうもけっこう風が強いですよね」
ぼくはつい抗議めいた口調になってしまった。歩きにくい道で必死になっているぼくをからかうように、その日の風はぼくの身体を揺さぶっていた。
「これくらいの風で休んでたら、商売になりません」
柴山さんの笑い皺には、長かったという船上勤務で鍛えられた迫力のようなものがあった。ただ、ほんとうに危険なほどの強風であれば遊歩道が閉鎖されるから、たんにぼくが関西弁でいうヘタレだっただけであろう。じっさい、前後では観光のかたがたが悠々と歩いていた。
やっとたどり着いた神威岬灯台は、白く高い塔というイメージとは違う三階建てくらいの小振りな建物だった。一階は設備類があり、首のような短い灯塔があり、ガラス張りの灯室が載っかっている。いただいたメモによると、地面から灯台のてっぺんまでは12メートルに過ぎない。
「では、どうぞ」
柴山さんはこともなげに一階の扉を開ける。ふつうなら入れない場所に入れるということだ。ぼくはふだん「自分が書いているものが小説かどうか、よくわかっていません」などとコマシャクレたことを言っているのだが、このときばかりは「小説家になってよかった」と図々しい感慨を覚えた。
短い階段を使い、灯室に出る。金属製の土台があり、見上げるくらいの高さに灯器が載っかっている。
灯器は、丸窓がついただけの簡素な四角い箱だった。大人なら両腕で抱き込める程度の大きさだ。事前に巨大な第一等不動レンズを見ていたので、つい拍子抜けしてしまった。
だが、この素っ気ない金属の箱は17万カンデラの光を放つ。ろうそく1本のあかりがだいたい1カンデラらしいから、すさまじい。前述したとおり灯台そのものも小振りなのだが、小高い岬の上にあるから平均水面からは82メートルの高さがある。光が届く距離は21海里、約39キロメートル。もし皇居の大手門に同じ高さと光度の灯台があれば、その光は横浜、千葉、川越あたりまでカバーする。
柴山さんの説明を聞きながらふと目を落とすと、台の陰にガラスクルーの缶が2本あった。ホームセンターなどでよく見るガラス磨き洗剤だ。灯台の能力に圧倒されていたぼくは、異国で旧友に会ったような親近感を覚えた。
灯室の隅にある小さな扉から、這うように外に出た。風と陽光に一瞬ひるみ、こわごわ背を伸ばして手摺に手をかける。その美しさから「積丹ブルー」と呼ばれる紺碧の海が一望できた。ため息が出るほどの絶景だった。
海を守り、人に支えられ
日本に灯台が建てられた時代、気象や明暗を検知するセンサーなどなかった。機械の信頼性もいまよりずっと低い。また灯台はたいてい、通勤できない僻地にある。
だから昔の灯台には「灯台守」と通称される職員がいて、家族と職場に住み込んでいた。戦前はおおむね逓信省、戦後は海上保安庁に属する。戦前から戦後にかけて勤務した灯台守を主人公にした映画「喜びも悲しみも幾歳月」は、時代に合わせて変わる制服も見どころのひとつだが、そこを見ているのはぼくだけかもしれない。
さておき、神威岬灯台には当初3名、のち5名の灯台守がいた。彼らは家族に支えられながら、交代で機械をメンテナンスし、定時で気象データを記録し、日が暮れれば光を灯し、行き交う船の目印を守っていた。
必要な物資は船から補給されるが、それだけでは足りない。生鮮食品は釣りや自家栽培で補い、日用品は4キロ離れた余別まで買い出しに行く。今と違って遊歩道はなく、険しい尾根や波に洗われる海岸を行き来していたという。雪に閉ざされる冬は苦労も並大抵ではなかったし、誰かが病気をしたところで、医者を呼ぶにも連れていくにも一仕事だった。
大正元年、買い出しのため海岸を歩いていた灯台守の妻子3人が、大波にさらわれて亡くなる事故があった。現代の感覚なら仕事に家族を巻き込むなど論外とも思えるが、国家や職務に対する意識が全く違う時代だったことは留意しておきたい。変わらぬのは人情だから、家族を失う辛さは痛みを覚えるほど想像できる。神威岬灯台では、無人化される昭和35年までに87名の灯台守が勤務し、その家族が住んでいた。
「私にはとても灯台守などできませんな」
海上保安庁の柴山さんは、そう言った。命懸けで職務に当たった先輩諸氏への敬意と、その後輩であるという自負がひっくり返ったのか、照れたような笑顔を浮かべておられた。
ところで、灯台守の家族が波にさらわれた先述の事故のあと、事故を悼んだ地元の人々は、足掛け五年もの歳月をかけて波から身を守るトンネルを掘った。また時は無人化以降にくだるが、灯台守の暮らしを支えた漁師と元郵便局員が名誉灯台長に任命された。
灯台守と家族は海を守り、守られた海に生きる地元の人々は灯台守と家族を支える。そんな関係と、それゆえに生まれたエピソードの数々が、町長のおっしゃった「町の誇り」という感覚になっているのだろう。
神威岬灯台
所在地 北海道積丹郡積丹町
アクセス JR余市駅前から北海道中央バス神威岬行きで1時間33分、終点下車
灯台の高さ 12
灯りの高さ※ 82
初点灯 明治21年
※灯りの高さとは、平均海面から灯りまでの高さ。
海と灯台プロジェクト
「灯台」を中心に地域の海と記憶を掘り起こし、地域と地域、日本と世界をつなぎ、これまでにはない異分野・異業種との連携も含めて、新しい海洋体験を創造していく事業で、「日本財団 海と日本プロジェクト」の一環として実施しています。
11月1日から「海と灯台ウィーク」を開催!
「海と灯台プロジェクト」では、灯台記念日の11月1日(水)から8日(水)までを「海と灯台ウィーク」と設定。期間中、海上保安庁や全国57市町村の「海と灯台のまち」、さらに灯台利活用に取組む企業・団体と連携し、灯台参観イベントやオリジナル缶バッジプレゼント、コラボ商品の販売など、様々なキャンペーンを実施します。連載に登場した灯台の中にもイベントを開催するところがあるので、この機会にぜひ訪ねてみてください。
川越宗一
https://news.yahoo.co.jp/articles/457551e02dc1c246c9c535387848e6188f0e3696