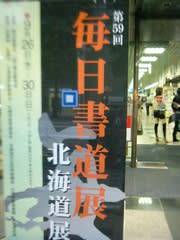読売新聞のサイトによると
今年は全国から漢字、かな、篆刻(てんこく)、調和体の4部門に計2万9506点の出品があり、道内からは入賞・入選に計297人が選ばれました。入賞(読売奨励賞、特選、秀逸)、入選作品(北海道関連分)、読売書法会役員から選ばれた読売大賞と準大賞、同会役員の新作計396点を展示します。
ということらしい。
毎日書道展を脱退した書家たちにより結成されてまだ四半世紀というのに、 . . . 本文を読む
札幌墨象会は年2回展覧会をひらいており、春は札幌市民ギャラリーで大作を、秋はコンチネンタルギャラリーで比較的小さな作品をならべています。
筆者がおじゃましたとき、三上禮子さんがいらっしゃいましたが、大小2つの展覧会を行うことで勉強になる-という意味のことをおっしゃっていました。
筆者は、わりとマメに見ている方だと思いますが、力強く、自由な作風の作品が多く、古典を知らない筆者のような人間に . . . 本文を読む
札幌在住の書家で、道書道展会員の安藤小芳(こよし)さんが主宰する「恵風会」の書展がひらかれています。安藤さんは、北海道女流書作家集団の代表でもあります。
なんと、書を教えはじめてから30年あまりになるというのに、これが初の展覧会なのだそうです。
生徒さんたちは以前から開きたがっていたそうですが、安藤さんは「公募展を卒業してから」。このほど、3人が北海道書道展で会友となったことを機に、開催 . . . 本文を読む
1932年、帯広生まれで、道内の前衛書をリードする書家のひとり、長沼透石さん(毎日書道展審査会員、奎星会同人会員・審査会員)。地元・帯広では何度か展覧会をひらいており、札幌では初となる個展です。
おなじく奎星会に属する札幌の竹下青蘭さんの師匠さんにあたるそうです。
「師匠でも、ぜんぜんわたしと違うでしょう?」
と竹下さんはおっしゃっていました。「展(2)」の、飛沫の散り方などをのぞけば、 . . . 本文を読む
日展とならび、国内最大の書展の地方展。
「わが県は◎◎が盛ん」「この地方は▲▲のメッカ」
というときは、時として割り引いて聞いたほうがよいこともあるけれど、北海道が書の盛んな土地であることは、本当らしいです。
毎日展も、審査会員が、首都圏1都3県に次いで多い部門もあります(つまり、大阪府や愛知県より多い)。
そのせいか、両会場に展示されているのは7部門1397点(26日夕刊の毎日新聞より) . . . 本文を読む
毎年書いていることだが、漢字が中心で、かながすくない。近代詩文もすくなく、篆刻はゼロ。
はたと気がついたのだが、道内に女性かな書家があまりいないわけではもちろんなくて、この展覧会に参加してない人がけっこう多いのだ。
出品者はつぎのとおり。「臨書」と記していないものは「創作」。
▼漢字
秋森麗子(札幌) 「回帰」
勢いを殺した、ぼくとつとした味わい。
阿部華雪(岩見沢) 「褒」
. . . 本文を読む
北海道書道展などには、2-4文字程度の漢字作品を出している札幌のベテラン書家、山田さん。今回は、スカイホール全室を用いた個展で、半分を、白居易(白楽天)の名高い漢詩「長恨歌」を主題にした作品が占めており、いつもとはちょっとちがう山田さんの面が見られる展覧会になっています。
もっとも、古典にしっかり軸足を据え、直球勝負の作品(楷書=かいしょ=という意味ではない)という山田さんらしさは変わっていま . . . 本文を読む
先に書いたとおり、この2団体が同時におなじ会場で展覧会をひらくのは、ここ何年かでは初めてだと思う。
いずれも、墨象の世界では、全国区の書家を擁する有力な団体であり、見ごたえも十分だ。
筆者は書壇の人間関係に疎いし、興味もまったくないから、このふたつの展覧会がどんなふうに対峙しているのかは知らないが、自分で勝手に、火花を散らしているんでないかと思ってみる。
今回も、書の情報では他の新聞を圧 . . . 本文を読む
日本を代表する近代詩文書の書家、中野北溟さん(札幌)の社中展。
ひとつの社中でこれだけのボリュームの作品がならぶということに、おどろいてしまいました。
ただ、この展覧会を見た人は、関係者以外には少なかったかもしれません。
というのは、道立美術館の年間日程というのは、年度が改まってから本格的な周知が始まるわけです。
ですから、新年度スケジュールを手にしたときには、年度はじめにわずか9日間 . . . 本文を読む
うーむ。なんだか、会場がさびしい。
金子鴎亭ら物故者の作品が見当たらないだけではない。
小川東洲も佐藤満もいないのだ。
それにくわえて、ことしは、これといった全体的な傾向がないように感ずる。たとえば、2004年のときに筆者が指摘していた、俳句を書いたかな書が多いとか、金文や甲骨文の流行といった目立った流れが、ことしは見当たらないようなのだ。
個々の作品が悪いというのではもちろんない。ただ . . . 本文を読む
青青社書展は、道内の前衛書の第一人者、竹下青蘭さん(札幌在住)が指導する社中による3年ぶりの展覧会。
漢字4点と、前衛書(文字でないものを書く)25点が展示されています。
けっして師風をそのまま引き継ぐのではなく、みなさんが自由な感性で伸び伸び筆を走らせているところに好感を持ちました。
大半の人は筆で書いていますが、なかには筆ではない物を用いている人もあるようです。
冒頭の画像、左側は . . . 本文を読む
札幌の書家で、読売書法展の理事・八巻水鴎さんが代表を務める書の社中展。メンバー37人のほか、日展会員の黒田賢一さんが賛助出品しています。
分野は、かなが圧倒的に多いですが、調和体もあります(読売系では「近代詩文書」といわず「調和体」と称する)。筆者のようなしろうとにとって、かな書の展覧会は、なにせ読めないので、あまり食指がうごかないのがほんとうのところなのですが、この会は、ただ「読めないかな . . . 本文を読む
「北海道高等学校書道教育研究会・展覧会」の略。
「道内の高校で書道を担当・愛好している教員の研鑽の場」だそうです。退職者が務めている顧問や参与をふくめ計67人が1点ずつ出品しており、なかなか見ごたえのある書展になっています。
めだった特徴としては、いわゆるかな書が1点しかないこと。漢字と近代詩文が断然多いです。
原田正光(増毛高校長)「明日」
平原綾香の歌詞。若いなあ。
武田博亭( . . . 本文を読む
スカイホール全室を使ったハイレベルの書展です。
全国団体「創玄書道会」の道内在住者でつくる「北海道創玄」の主催。
わかりやすい記事が毎日新聞北海道版に出ていたので、ちょっとだけ引用します。
北海道創玄は69年の旗揚げ。創玄創立者の金子鴎亭(01年没)の提唱で74年、次代を担う気鋭の書家が意欲作を発表する場として「北玄12人展」を設け、毎日書道展毎日賞受賞者を中心に開催してきた。30回の節目 . . . 本文を読む
3.良寛
この人について筆者は研究しているわけではないのですが、元祖ヘタウマというか、独特のポジションにある人だなと思います。小ざかしさを排した飄逸たる味わいは、そこそこの完成度を、笑い飛ばしてしまうようなところがあるのではないでしょうか。 . . . 本文を読む