1つ前の記事で、18世紀後期の実学者洪大容について、朝鮮実学の研究者・小川晴久二松学舎大教授の本を引用しました。
その記事でも少しふれましたが、小川晴久先生は20年近く前から北朝鮮の人権問題に取り組み、活動を続けてきた人です。
私ヌルボが小川先生のことを知ったのは、ミネソタ弁護士会国際人権委員会・アジアウォッチ((編集「北朝鮮の人権―世界人権宣言に照らして」(連合出版.2004)の翻訳者としてです。(川人博弁護士との共訳。)
この本の巻末に、小川先生の14ページに及ぶ解説が付いています。その最後の方に、北朝鮮の人権問題に対する世界の認識について、次のような記述がありました。
日本の認識の遅れをよく示すのは、政府を中心に六ヶ国協議が大事だとする声が大きいことである。方法としては包括的に諸問題を解決していくというやり方で、人権問題も諸問題の一つという位置づけである。
六ヶ国協議で危険なのは核問題で北朝鮮が要求する「体制の保障」をのんでしまうことである。金正日の体制を保障してしまったら、北朝鮮の人権状況の改善は二〇年も遅れてしまう。北朝鮮の民衆の苦難を二〇年も放置することになる。東アジアの平和確保が先決だとか、難民の大量流入は困るとか、いずれも自分の国のことしか考えない周辺国のエゴである。北朝鮮民衆を犠牲にする六か国協議は断じて許されない。戦争の防止は人権の保障である。北朝鮮の山の中の強制収容所を根幹とする人権抑圧状況こそ是正されていかねばならない。本書は何よりもそれを雄弁に語っている。本書を読まれた人ならば包括的解決方式が正しいか人権改善でいくべきかは、自ら明らかであろう。
今国内では、否東アジア世界では、北朝鮮に対する態度をめぐって、六ヶ国協議派と人権改善派とが真向うから対立している。小泉首相は二年以内に日朝国交を実現しようとしているが、とんでもないまちがいである。人権問題の解決なくして国交正常化はあり得ない。
このくだりを読んで、ヌルボは驚きました。心打たれた、といった方がいいかもしれません。
このようにはっきりと人権問題を最優先課題とする主張を目にしたのは初めてでした。とくに平和を追求する話し合いみたいでイメージ的にはよさそうに見える6ヵ国協議を批判するとは!
また、いわゆる「保守派」「右翼」等のように拉致問題をはじめ日本人の問題のみを突出して訴えたり、政治的観点から論ずるのではなく、世界人権宣言を拠り所により普遍的な観点から論を展開している点に共感を覚えました。
概して、韓国でも日本でも「進歩陣営」の人たちには平和的な交渉を積み上げていくことの大切さを主張する人が多いようです。
ヌルボも、「一般論としては」それが正しいとは思いますが、これまでの6ヵ国協議等で核問題は大きく取り扱われても、人権問題については重視されてきませんでした。むしろ、本ブログでも2011年8月25日の記事「北朝鮮の強制収容所についてのアムネスティのアクション(上)」の中で書いたように、「北朝鮮・韓国・中国・ロシア・アメリカ、そして日本の6ヵ国政府は、どこも政治的・軍事的な観点から現状維持を望んでいるようです。その中で多数の北朝鮮住民が犠牲になっています」という状態がずっと続いています。
ところが韓国の進歩陣営では、「北朝鮮人権問題の悪化原因には様々な要因が複合的に組み合わさっている」という(北朝鮮政府を弁護しているような)見方や、「国内外保守派(韓国の保守政権やアメリカ等)が北朝鮮人権問題を北朝鮮体制の崩壊のための手段としている」と韓国やアメリカでの北朝鮮人権法に異を唱え、小川先生が批判している「包括的解決方式」を追求する声が今に至るまで一般的なようです。
そんな「包括的解決方式」に立脚した本の1例として、玄武岩(ヒョン・ムアム)北大准教授の「統一コリア」(光文社新書)があります。およそ韓国の進歩陣営の立場に立った内容だと思いました。その中で、とくに人権問題について疑問に思った箇所を引用します。
「脱北者」を難民とみなして自国への亡命を認める、米国で制定された北朝鮮人権法(North Korea Human Right Act)は、かえって南北関係をこじらせる結果を招くとして憂慮されている。同法が結局は人権を名目にして北朝鮮の崩壊をもくろんでいることで、脱北支援活動が活発化されることが予想されるからであった。また「北朝鮮の住民は韓国の憲法によって享受する法的な権利によって、米国における難民地位や亡命資格の獲得に妨げられることはない」とする項目も、北朝鮮との和解・協力を重視する韓国政府(盧武鉉政権)を困惑させた。
人権問題の追及をすべて「名目」と捉えるのですか? また、人権よりも体制維持の方が優先されるのですか?
たんなる思想であれば、社会主義は韓国内での急進的な運動として花を咲かすことなく摘み取られた革新運動となんら変わりはない。しかし、全国民が不動産投機に走り、新自由主義的なグローバル化へのシンクロが進む韓国的な状況から照らし合わせてみても、破たんしたとはいえ一度は理想に向かって現実化した北朝鮮の住民と共存するなかで、そこから救い上げられるものはけっして少なくないはずである。また、その共存は、同胞たちが嘗めてきた多大な苦痛を理解し尊重するための課程(ママ)でもある。
それによってとっくに半世紀を超えてしまった分断の経験を無意味にすることなく、それぞれの時代の財産と教訓にして、「過程としての統一」に生かすことができるのである。
社会主義が北朝鮮で「一度は理想に向かって現実化した」と捉えていますが、政治学者として、かつてのスターリニズムの現実とそのたどった過程をどう理解しているのでしょうか? また北朝鮮の人々が政治的意見を持った市民で、またその意見が反映されるような社会だと思っているわけではないでしょうね!? ヌルボも昔から理想を語ったりもしてきましたが、ここまであまくはないですよ。
※玄武岩「統一コリア」については、→コチラのブログ記事で手厳しく批判されています。
彼の先生の姜尚中氏については、さるブログに次のような興味深い記事がありました。
「2003年8月16日の、佐高さんが客員教授を勤める東北公益文科大学での姜、佐高対談(角川文庫「日本論」に収録)で、対談後の質疑応答の時間に、ある学生さんが「姜教授は拉致問題の解決は6カ国間の協議で解決すべきだと言われるが、私はもっと国際的な手続きを重視べきだと思うがどうか」というような質問をしたところ、姜教授は「極端な話だが正義よりも平和を尊ぶべきだ」という答えを出されました。このことに川人弁護士は疑問を呈したのがそもそもの姜教授批判のきっかけとなったのですが、そのとき対談者の佐高信さんは特に反応しなかったということがありました。」
姜尚中氏は川人博氏の他、鄭大均・三浦小太郎両氏の著作でも名指しで批判されたりもしていますが、ここらでしっかりとした説得力ある反論、北朝鮮論を期待したいところです。(皮肉に非ず。)
また「日朝関係の克服」(集英社新書)等で一般読者からも厳しいコメントを書かれていますが(→コチラ)、やはり師弟とも北朝鮮認識は基本的に共通していますね。
※玄武岩「統一コリア」には、開城工団等韓国と北朝鮮の間の人的交流の拡大についても(とても肯定的に)書かれていましたが、これについてはいずれ別記事にします。
最初の小川先生の「6ヵ国協議批判」に戻ります。
人権問題を最重点課題とすると、北朝鮮に対して厳しくならざるを得ません。だからといって、それは軍事的圧力や経済制裁に直接つながるものではない、というのがヌルボの意見。
北朝鮮の人権の実態を伝える日本書や韓国書を各国語に翻訳したりして国際社会に広くアピールすること自体が力になるでしょう。脱北者も積極的に支援する。北朝鮮への食糧支援はすべきだとは思いますが、北朝鮮政府はの分配監視条件付き支援を拒否しちゃってるからなー・・・。(関連ニュース→コチラ。)
小川先生の文中でもうひとつ気になる言葉が、北朝鮮が要求する「体制の保障(証?)」。これはどういうことか、ちゃんとした説明は少し探しても見つかりませんでしたが、たとえば①アメリカや韓国等が軍事力を行使して北朝鮮の体制を倒したりはしないという保障、②北朝鮮の現体制が崩壊しないように支える(??)・・・の、①の意味なのか、それとも②まで含むものなのか?
小川先生の文章では「体制の保障」=「金正日の体制の保障」=「人権状況改善の20年遅滞」と捉えている、ということは②まで含むということのようですね。
それで間違いないとすると、「体制の保障」を北朝鮮政府が求めるとはなんと面妖な、と思わざるをえないのですが・・・。人権問題のような、現代では国のワクを越えた普遍性を持つと思われるような問題についてさえ「内政干渉だ」と反発するのに、国の体制のような、まさにその国の主権に関わる重要な事柄について他国が保障するといったものでもないでしょうに・・・。崩壊の瀬戸際に立たされている政権を他国が支えるとなると、それこそゆゆしき内政干渉でしょう。・・・よくわからん。
<アジアプレス>のサイト掲載の日本で暮らす脱北者女子学生の手記「リ・ハナの一歩一歩」の2009年の記事中に次のような内容の一文がありました。
米韓両政府が北朝鮮に対して「核の廃棄と引き換えに金正日体制、現体制の存続を保証する案を検討中」という新聞記事を読んで「今の北朝鮮の体制―金正日総書記、若しくはその子孫たちが君臨し続ける体制の存続を認めるというのは如何なものなんだろうか。その体制の下で苦しみ続ける庶民たちに対する何らかの保証はあるんでしょうか」ということが気にかかる、というものです。
こうした心配が的外れでないとすると、ヌルボも「体制保証」には当然反対です。
たまたま「本ばかり読むバカ」というジュニア向け歴史小説を読んだことが契機となって、小川晴久先生の北朝鮮関係の本もひもとくことになりました。
開明的な知識人としてはごくふつうに北朝鮮にプラスイメージを持っていた小川先生が北朝鮮の人権状況に目を開かされたのは、1993年に在日朝鮮人帰国者家族の証言を聞いたのが契機だったそうです。その後の先生の熱意と行動力には頭が下がります。
しかし、その時からもう20年近く経ってしまいました。
「北朝鮮の人権」の共訳者・川人博弁護士は、あとがきで「「北朝鮮はひどい国だ」ということについてはほぼ世論は一致している。ただ、だからと言って、北朝鮮の人権状況を改善しようとする活動が発展しているとは必ずしも言えない」と書いています。
そして今、状況はどのくらい変わっているのでしょうか?
韓国と、世界は近ごろそれなりに(不十分ながら)変わってきたかな、とヌルボには感じられます。ところが、総体としては北朝鮮や日本を筆頭にたいして変わっていないのではないでしょうか?
北朝鮮の人々の置かれた状況についての直接の責任は北朝鮮の支配者にあるにせよ、「6ヵ国」を構成する1国である日本国民にも、もしかしたら、いや、たしかに責任の一端はあると思いますよ。
その記事でも少しふれましたが、小川晴久先生は20年近く前から北朝鮮の人権問題に取り組み、活動を続けてきた人です。
私ヌルボが小川先生のことを知ったのは、ミネソタ弁護士会国際人権委員会・アジアウォッチ((編集「北朝鮮の人権―世界人権宣言に照らして」(連合出版.2004)の翻訳者としてです。(川人博弁護士との共訳。)
この本の巻末に、小川先生の14ページに及ぶ解説が付いています。その最後の方に、北朝鮮の人権問題に対する世界の認識について、次のような記述がありました。
日本の認識の遅れをよく示すのは、政府を中心に六ヶ国協議が大事だとする声が大きいことである。方法としては包括的に諸問題を解決していくというやり方で、人権問題も諸問題の一つという位置づけである。
六ヶ国協議で危険なのは核問題で北朝鮮が要求する「体制の保障」をのんでしまうことである。金正日の体制を保障してしまったら、北朝鮮の人権状況の改善は二〇年も遅れてしまう。北朝鮮の民衆の苦難を二〇年も放置することになる。東アジアの平和確保が先決だとか、難民の大量流入は困るとか、いずれも自分の国のことしか考えない周辺国のエゴである。北朝鮮民衆を犠牲にする六か国協議は断じて許されない。戦争の防止は人権の保障である。北朝鮮の山の中の強制収容所を根幹とする人権抑圧状況こそ是正されていかねばならない。本書は何よりもそれを雄弁に語っている。本書を読まれた人ならば包括的解決方式が正しいか人権改善でいくべきかは、自ら明らかであろう。
今国内では、否東アジア世界では、北朝鮮に対する態度をめぐって、六ヶ国協議派と人権改善派とが真向うから対立している。小泉首相は二年以内に日朝国交を実現しようとしているが、とんでもないまちがいである。人権問題の解決なくして国交正常化はあり得ない。
このくだりを読んで、ヌルボは驚きました。心打たれた、といった方がいいかもしれません。
このようにはっきりと人権問題を最優先課題とする主張を目にしたのは初めてでした。とくに平和を追求する話し合いみたいでイメージ的にはよさそうに見える6ヵ国協議を批判するとは!
また、いわゆる「保守派」「右翼」等のように拉致問題をはじめ日本人の問題のみを突出して訴えたり、政治的観点から論ずるのではなく、世界人権宣言を拠り所により普遍的な観点から論を展開している点に共感を覚えました。
概して、韓国でも日本でも「進歩陣営」の人たちには平和的な交渉を積み上げていくことの大切さを主張する人が多いようです。
ヌルボも、「一般論としては」それが正しいとは思いますが、これまでの6ヵ国協議等で核問題は大きく取り扱われても、人権問題については重視されてきませんでした。むしろ、本ブログでも2011年8月25日の記事「北朝鮮の強制収容所についてのアムネスティのアクション(上)」の中で書いたように、「北朝鮮・韓国・中国・ロシア・アメリカ、そして日本の6ヵ国政府は、どこも政治的・軍事的な観点から現状維持を望んでいるようです。その中で多数の北朝鮮住民が犠牲になっています」という状態がずっと続いています。
ところが韓国の進歩陣営では、「北朝鮮人権問題の悪化原因には様々な要因が複合的に組み合わさっている」という(北朝鮮政府を弁護しているような)見方や、「国内外保守派(韓国の保守政権やアメリカ等)が北朝鮮人権問題を北朝鮮体制の崩壊のための手段としている」と韓国やアメリカでの北朝鮮人権法に異を唱え、小川先生が批判している「包括的解決方式」を追求する声が今に至るまで一般的なようです。
そんな「包括的解決方式」に立脚した本の1例として、玄武岩(ヒョン・ムアム)北大准教授の「統一コリア」(光文社新書)があります。およそ韓国の進歩陣営の立場に立った内容だと思いました。その中で、とくに人権問題について疑問に思った箇所を引用します。
「脱北者」を難民とみなして自国への亡命を認める、米国で制定された北朝鮮人権法(North Korea Human Right Act)は、かえって南北関係をこじらせる結果を招くとして憂慮されている。同法が結局は人権を名目にして北朝鮮の崩壊をもくろんでいることで、脱北支援活動が活発化されることが予想されるからであった。また「北朝鮮の住民は韓国の憲法によって享受する法的な権利によって、米国における難民地位や亡命資格の獲得に妨げられることはない」とする項目も、北朝鮮との和解・協力を重視する韓国政府(盧武鉉政権)を困惑させた。
人権問題の追及をすべて「名目」と捉えるのですか? また、人権よりも体制維持の方が優先されるのですか?
たんなる思想であれば、社会主義は韓国内での急進的な運動として花を咲かすことなく摘み取られた革新運動となんら変わりはない。しかし、全国民が不動産投機に走り、新自由主義的なグローバル化へのシンクロが進む韓国的な状況から照らし合わせてみても、破たんしたとはいえ一度は理想に向かって現実化した北朝鮮の住民と共存するなかで、そこから救い上げられるものはけっして少なくないはずである。また、その共存は、同胞たちが嘗めてきた多大な苦痛を理解し尊重するための課程(ママ)でもある。
それによってとっくに半世紀を超えてしまった分断の経験を無意味にすることなく、それぞれの時代の財産と教訓にして、「過程としての統一」に生かすことができるのである。
社会主義が北朝鮮で「一度は理想に向かって現実化した」と捉えていますが、政治学者として、かつてのスターリニズムの現実とそのたどった過程をどう理解しているのでしょうか? また北朝鮮の人々が政治的意見を持った市民で、またその意見が反映されるような社会だと思っているわけではないでしょうね!? ヌルボも昔から理想を語ったりもしてきましたが、ここまであまくはないですよ。
※玄武岩「統一コリア」については、→コチラのブログ記事で手厳しく批判されています。
彼の先生の姜尚中氏については、さるブログに次のような興味深い記事がありました。
「2003年8月16日の、佐高さんが客員教授を勤める東北公益文科大学での姜、佐高対談(角川文庫「日本論」に収録)で、対談後の質疑応答の時間に、ある学生さんが「姜教授は拉致問題の解決は6カ国間の協議で解決すべきだと言われるが、私はもっと国際的な手続きを重視べきだと思うがどうか」というような質問をしたところ、姜教授は「極端な話だが正義よりも平和を尊ぶべきだ」という答えを出されました。このことに川人弁護士は疑問を呈したのがそもそもの姜教授批判のきっかけとなったのですが、そのとき対談者の佐高信さんは特に反応しなかったということがありました。」
姜尚中氏は川人博氏の他、鄭大均・三浦小太郎両氏の著作でも名指しで批判されたりもしていますが、ここらでしっかりとした説得力ある反論、北朝鮮論を期待したいところです。(皮肉に非ず。)
また「日朝関係の克服」(集英社新書)等で一般読者からも厳しいコメントを書かれていますが(→コチラ)、やはり師弟とも北朝鮮認識は基本的に共通していますね。
※玄武岩「統一コリア」には、開城工団等韓国と北朝鮮の間の人的交流の拡大についても(とても肯定的に)書かれていましたが、これについてはいずれ別記事にします。
最初の小川先生の「6ヵ国協議批判」に戻ります。
人権問題を最重点課題とすると、北朝鮮に対して厳しくならざるを得ません。だからといって、それは軍事的圧力や経済制裁に直接つながるものではない、というのがヌルボの意見。
北朝鮮の人権の実態を伝える日本書や韓国書を各国語に翻訳したりして国際社会に広くアピールすること自体が力になるでしょう。脱北者も積極的に支援する。北朝鮮への食糧支援はすべきだとは思いますが、北朝鮮政府はの分配監視条件付き支援を拒否しちゃってるからなー・・・。(関連ニュース→コチラ。)
小川先生の文中でもうひとつ気になる言葉が、北朝鮮が要求する「体制の保障(証?)」。これはどういうことか、ちゃんとした説明は少し探しても見つかりませんでしたが、たとえば①アメリカや韓国等が軍事力を行使して北朝鮮の体制を倒したりはしないという保障、②北朝鮮の現体制が崩壊しないように支える(??)・・・の、①の意味なのか、それとも②まで含むものなのか?
小川先生の文章では「体制の保障」=「金正日の体制の保障」=「人権状況改善の20年遅滞」と捉えている、ということは②まで含むということのようですね。
それで間違いないとすると、「体制の保障」を北朝鮮政府が求めるとはなんと面妖な、と思わざるをえないのですが・・・。人権問題のような、現代では国のワクを越えた普遍性を持つと思われるような問題についてさえ「内政干渉だ」と反発するのに、国の体制のような、まさにその国の主権に関わる重要な事柄について他国が保障するといったものでもないでしょうに・・・。崩壊の瀬戸際に立たされている政権を他国が支えるとなると、それこそゆゆしき内政干渉でしょう。・・・よくわからん。
<アジアプレス>のサイト掲載の日本で暮らす脱北者女子学生の手記「リ・ハナの一歩一歩」の2009年の記事中に次のような内容の一文がありました。
米韓両政府が北朝鮮に対して「核の廃棄と引き換えに金正日体制、現体制の存続を保証する案を検討中」という新聞記事を読んで「今の北朝鮮の体制―金正日総書記、若しくはその子孫たちが君臨し続ける体制の存続を認めるというのは如何なものなんだろうか。その体制の下で苦しみ続ける庶民たちに対する何らかの保証はあるんでしょうか」ということが気にかかる、というものです。
こうした心配が的外れでないとすると、ヌルボも「体制保証」には当然反対です。
たまたま「本ばかり読むバカ」というジュニア向け歴史小説を読んだことが契機となって、小川晴久先生の北朝鮮関係の本もひもとくことになりました。
開明的な知識人としてはごくふつうに北朝鮮にプラスイメージを持っていた小川先生が北朝鮮の人権状況に目を開かされたのは、1993年に在日朝鮮人帰国者家族の証言を聞いたのが契機だったそうです。その後の先生の熱意と行動力には頭が下がります。
しかし、その時からもう20年近く経ってしまいました。
「北朝鮮の人権」の共訳者・川人博弁護士は、あとがきで「「北朝鮮はひどい国だ」ということについてはほぼ世論は一致している。ただ、だからと言って、北朝鮮の人権状況を改善しようとする活動が発展しているとは必ずしも言えない」と書いています。
そして今、状況はどのくらい変わっているのでしょうか?
韓国と、世界は近ごろそれなりに(不十分ながら)変わってきたかな、とヌルボには感じられます。ところが、総体としては北朝鮮や日本を筆頭にたいして変わっていないのではないでしょうか?
北朝鮮の人々の置かれた状況についての直接の責任は北朝鮮の支配者にあるにせよ、「6ヵ国」を構成する1国である日本国民にも、もしかしたら、いや、たしかに責任の一端はあると思いますよ。












![韓国内の映画の興行成績 [8月11日(金)~8月13日(日)] ►「コンクリートユートピア」は期待してよさそう! ►日韓の港町のヤクザ文化(?)と「野獣の血」等のこと](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/6a/11/92d870b3e7abfcf50b59506f39b0cba6.jpg)
![韓国内の映画の興行成績 [7月28日(金)~7月30日(日)] ►「密輸」に続いて「ザ・ムーン」が公式公開前に10位にランクイン ►<サメのかぞく体操>って知ってますか?](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0e/c5/5e7496d2812629ef25604c3e9779b3f4.jpg)
![韓国内の映画の興行成績 [7月21日(金)~7月23日(日)] ►期待できそう! リュ・スンワン監督の新作「密輸」 ►最近観たドキュメンタリー「世界のはしっこ、ちいさな教室」は良かった!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/35/a0/12b1fedcdd7d44e3b5ae4cdde7c52ed4.jpg)
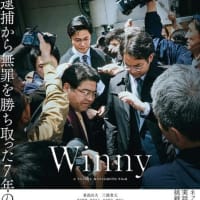
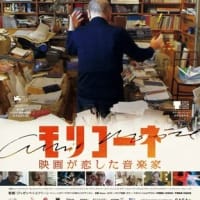
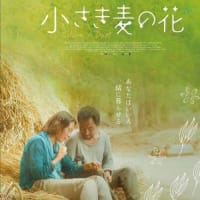
![韓国内の映画の興行成績 [7月14日(金)~7月16日(日)] ►韓国でも「ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE」の勢いがスゴイ! ►ハンガリーのアニメ「ピノキオ」ねー・・・](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/3f/97/23df6cbf19458fe4f08e5af9d4969562.jpg)
![韓国内の映画の興行成績 [7月14日(金)~7月16日(日)] ►韓国でも「ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE」の勢いがスゴイ! ►ハンガリーのアニメ「ピノキオ」ねー・・・](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/58/a7/37839be4ca432b6c9dabb103a6fa31b6.jpg)
![韓国内の映画の興行成績 [7月14日(金)~7月16日(日)] ►韓国でも「ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE」の勢いがスゴイ! ►ハンガリーのアニメ「ピノキオ」ねー・・・](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/71/b9/cb7ffe184f0640f4c629be5ba1de9724.jpg)
![韓国内の映画の興行成績 [6月30日(金)~7月2日(日)] ►韓国映画「君の結婚式」の中国版リメイク、韓国で上映! ►ウェス・アンダーソン監督の新作「アステロイド・シティ」、期待していいかな?](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/00/81/b0850e17282a4b2ef3dd13867cfce7de.jpg)





