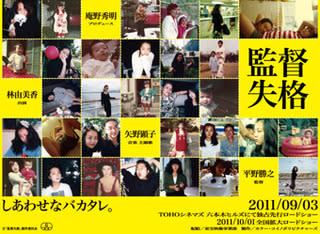(原題:The Band Wagon)1953年作品。子供の頃にテレビ放映で見たような記憶があるが、スクリーン上で接するのは今回のリバイバル公開(午前十時の映画祭)が初めてである。MGMミュージカルの仕掛人アーサー・フリードと「巴里のアメリカ人」などのヴィンセント・ミネリ監督が手掛けた傑作といわれる映画だ。
かつてはハリウッド・スターとして人気を誇ったトニー・ハンターだが、今や知る人も少なくなった。そんな彼が親友のマートン夫妻が執筆した舞台「バンド・ワゴン」でブロードウェイへの復帰を目指す。しかし演出家がミュージカルとは畑違いの時代劇専門。当然ながら要領を得ない舞台は酷評の嵐で、トニーは周囲のキャストともウマが合わずに興行は失敗に終わってしまう。このまま一線から退くわけにはいかないトニーは、脚本と楽曲を自分流に作り変え、地道にドサ回りから始める。やがて徐々に評判は高まり、成功への道筋が見えてくる。

これはまず、トニーに扮するフレッド・アステアの映画だ。洗練を極めた身のこなしと流れるようなダンス。特に相手役のシド・チャリシーと公園で踊るシーンは、ミュージカル映画史上に残るようなヴォルテージの高さを見せつける。そして使われるナンバーが泣けてくるほど素晴らしい。
前半とラストに流れる「ザッツ・エンターテインメント」は、言うまでもなく同名のアンソロジー映画のテーマ曲でもあるが、ミュージカルが幕を開けようとするそのウキウキとした気分を代弁するような名曲だ。他にも「シャイン・オン・ユア・シューズ」や「ダンシング・イン・ザ・ダーク」「あなたと夜と音楽と」といった、現在でもスタンダード・ナンバーとして歌い継がれている曲が満載。それらを聴いているだけでも、幸せな気分になってくる。
ハッキリ言ってこの映画はストーリーは大したことはない。しかし、それでいいのだ。小難しいプロットの積み上げなど、アステアの軽妙洒脱な芸の前では無力。約束通りのハッピー・エンディングに、これ以上何を望むのだという気分になってくる。
ミネリの演出はテンポが良く、マートン夫妻を演じるオスカー・レヴァントとナネット・ファブレー、そして舞台監督役のジャック・ブッキャナン等のコメディ・リリーフも嬉しい。この世の憂さも忘れてしまう、まさに快作というべき映画だ。
かつてはハリウッド・スターとして人気を誇ったトニー・ハンターだが、今や知る人も少なくなった。そんな彼が親友のマートン夫妻が執筆した舞台「バンド・ワゴン」でブロードウェイへの復帰を目指す。しかし演出家がミュージカルとは畑違いの時代劇専門。当然ながら要領を得ない舞台は酷評の嵐で、トニーは周囲のキャストともウマが合わずに興行は失敗に終わってしまう。このまま一線から退くわけにはいかないトニーは、脚本と楽曲を自分流に作り変え、地道にドサ回りから始める。やがて徐々に評判は高まり、成功への道筋が見えてくる。

これはまず、トニーに扮するフレッド・アステアの映画だ。洗練を極めた身のこなしと流れるようなダンス。特に相手役のシド・チャリシーと公園で踊るシーンは、ミュージカル映画史上に残るようなヴォルテージの高さを見せつける。そして使われるナンバーが泣けてくるほど素晴らしい。
前半とラストに流れる「ザッツ・エンターテインメント」は、言うまでもなく同名のアンソロジー映画のテーマ曲でもあるが、ミュージカルが幕を開けようとするそのウキウキとした気分を代弁するような名曲だ。他にも「シャイン・オン・ユア・シューズ」や「ダンシング・イン・ザ・ダーク」「あなたと夜と音楽と」といった、現在でもスタンダード・ナンバーとして歌い継がれている曲が満載。それらを聴いているだけでも、幸せな気分になってくる。
ハッキリ言ってこの映画はストーリーは大したことはない。しかし、それでいいのだ。小難しいプロットの積み上げなど、アステアの軽妙洒脱な芸の前では無力。約束通りのハッピー・エンディングに、これ以上何を望むのだという気分になってくる。
ミネリの演出はテンポが良く、マートン夫妻を演じるオスカー・レヴァントとナネット・ファブレー、そして舞台監督役のジャック・ブッキャナン等のコメディ・リリーフも嬉しい。この世の憂さも忘れてしまう、まさに快作というべき映画だ。