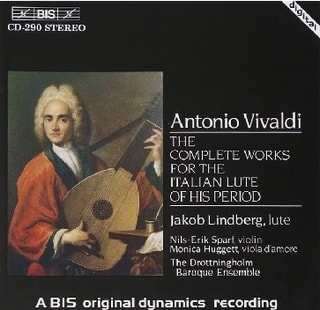(原題:GHOSTBUSTERS:AFTERLIFE)正直言ってあまり期待はしていなかったのだが、実際観てみると面白い。84年の第一作と89年のパート2、そして2016年のリブート版と比べても、クォリティは上だ。以前の作品群が単なる大味なドタバタ劇に過ぎなかったのに対し、本作は主題に一本芯が通っている。やはりこれは、脚本の妙に尽きる。
家賃を払えずに追い立てを食らったシングルマザーのキャリーと息子のトレヴァー、そして娘の女子中学生フィービーは、都会からキャリーの父が遺したオクラホマ州サマーヴィルの荒れ果てた農家に引っ越して来る。この地域では、活断層も無いのに原因不明の地震が頻発していた。ある日、フィービーは地下室で謎のハイテク装備の数々を発見。どうやら祖父が使っていたものらしいが、用途が分からない。そして床下にあった装置を誤って開封してしまうと、不気味な緑色の光に包まれたモンスターが出てくる。
実はフィービーの祖父イゴン・スペングラーはかつてのゴーストバスターズの一員であり、この地区の廃鉱山の奥に封じ込められていた魔神ゴーザを見張っていたのだ。ゴーストの封印が解けたことで、魔神復活による世界の危機が迫ってくる。フィービーはクラスメイトのポッドキャストたちと共に、祖父の遺したメカを駆使してゴーストに立ち向かう。
この映画の主要ポイントは家族劇である。早い話が、主人公がクリーチャーとのバトルを通して、自己のアイデンティティと家族の絆を確立するというビルドゥングスロマン(?)の体裁を取っている。行き当たりばったりにワチャワチャとゴーストと戯れていた過去の作品とは違う。
身持ちの悪い母親と、グータラな兄。しかも廃屋寸前のボロ家に押し込まれ、これでは人生投げてしまいたくなるのも当然のフィービーだが、祖父との繋がりを切っ掛けに自分を取り戻し、そして周囲の者たちとの折り合いを付けていくという筋書きは、大いに納得できる。田舎町を舞台に繰り広げられるゴーストたちとのチェイス、そして賑々しいバトルシーンはかなりの盛り上がりを見せ、監督のジェイソン・ライトマンは第一作と第二作を担当した父親のアイヴァンよりも実力は上だ。さらに終盤には“あの人たち”も登場し、お馴染みのテーマ曲も流れるのだから嬉しくなる。
フィービー役のマッケナ・グレイスは闊達な好演で、将来を期待させるものがある。キャリー・クーンやフィン・ウルフハード、ポール・ラッド、J・K・シモンズ、オリヴィア・ワイルドなどの脇の面子も良い。また、作品自体が今は亡きハロルド・ライミスに捧げられているのも感慨深い。続編が作られる可能性は大だが、チェックしたい気になってくる。