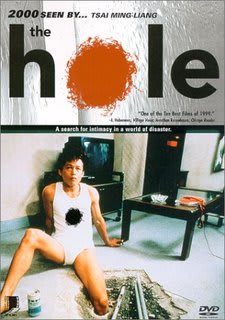(原題:追捕 MANHUNT)無駄に映画鑑賞歴が長いと、箸にも棒にもかからないシャシンにも少なからず遭遇する。ただし、本作みたいに始まって5分も経たないうちに中途退場したくなった映画はめったに無い(まあ、座った席が奥の方だったので容易に出られず、仕方なく最後まで観たのだが ^^;)。それほどこの作品はヒドいのだ。
大阪に滞在している中国籍の弁護士ドゥ・チウが目を覚ますと、隣に女の他殺体が転がっていた。現場には彼が犯人であることを示す証拠が山のようにあり、直ぐさま逮捕されてしまう。罠にはめられたことに気付いた彼は逃走するが、どうやらドゥ・チウが顧問弁護士を務めていた大手薬品会社が裏で暗躍しているらしい。
一方、府警の捜査一課所属の刑事・矢村は、独自の捜査でドゥ・チウを捕まえることに成功。だが、事件の概要に疑問を持った矢村は、身柄を府警本部に引き渡すことを拒否する。こうして成り行きで一緒に真実を追い求めることになった2人だが、製薬会社およびその協力組織が差し向けた殺し屋どもが大挙して襲いかかってくる。西村寿行の小説を高倉健主演で映画化した「君よ憤怒の河を渉れ」(76年)のリメイクだ。
冒頭、場違いな演歌をバックに、場違いにレトロな裏通りにある飲み屋にドゥ・チウが入ると、日本語の怪しい女将と店員が迎え、やがて乱入してきたヤクザ連中を殺し屋の正体を現した女将&店員が血祭りに上げるという、まさに場違いなシークエンスが映し出された時点で、すでに鑑賞意欲は失せていた(笑)。
さらに、思わせぶりに登場する矢村は、演ずる福山雅治の“何をやっても所詮フクヤマ”のルーティンを一歩もはみ出すことがなく、鼻につくキザったらしさが全開だ。
矢村がどうしてドゥ・チウを逃がすのか分からず、そもそも敵方がなぜわざわざドゥ・チウをハメたのか、明確な説明は無い。あとは脚本の不備を逐一指摘するとキリがないほどの、矛盾に満ちた作劇の連続。舞台は大阪(およびその周辺)ということになっているが、地理的な感覚がオカシイのは御愛敬としても、この薄っぺらで深みの無い風景描写は何とかして欲しい。
監督のジョン・ウーは“意味なく舞う白い鳩”や“横っ飛びでの銃撃”などの馴染みのネタを今回も披露しているが、そこにはかつてのような緊張感や高揚感は見られず、まるで売れなくなったコメディアンの昔の芸に付き合わされているようだ。ドゥ・チウ役のチャン・ハンユーをはじめチー・ウェイ、國村隼、竹中直人、ハ・ジウォン、池内博之といったキャストはパッとせず、矢村の部下に扮する桜庭ななみはアイドル演技だし、斎藤工や倉田保昭といったクセの強い面子も使いこなせていない。とにかく、早々に忘れてしまいたい映画である。