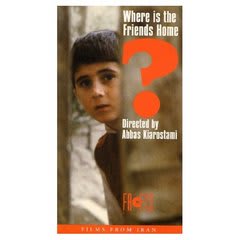(原題:Les Demoiselles de Rochefort)67年作品。贅沢な時間を過ごさせてもらった。「シェルブールの雨傘」の監督ジャック・ドゥミと音楽ミシェル・ルグランのコンビによるフレンチ・ミュージカルの傑作と言われている映画だが、私は本作に接したのは今回のリバイバル上映が初めてである。評判通り・・・・と言うより、それ以上の感銘を受けた。観客を楽しませるツボを熟知した、手練れのカツドウ屋としてのプライドが全編にみなぎっている。
フランス西部にある小さな街ロシュフォールで展開される双子の姉妹とその周囲の人々が織りなす恋模様・・・・などというストーリーには深く言及する余地はない。もとよりこの手の作品に複雑なドラマツルギーを期待すべきではないのだ。すべてが明るくハッピーに、収まるところに収まればそれでヨシ。あとはお決まりの歌と踊り、本作はその娯楽性の喚起力が極限レベルである。
往年のMGM製ミュージカルのような、名人級の力量を持った出演陣による精緻な振り付けやダンスの技巧の披露はほとんどない。ハッキリ言って“ゆるい”と思う。だが、自然光を活かした撮影と、街全体を巨大なセットとして捉えた舞台設定の絶妙さにより、まったく気にならない。それどころか、この映画の雰囲気としてはこういうゆったりとしたノリが不可欠であることが分かる。
カトリーヌ・ドヌーヴと、急逝した彼女の実姉フランソワーズ・ドルレアック、そしてジーン・ケリーとジョージ・チャキリス、さらにジャック・ペランやダニエル・ダリュー、ミシェル・ピコリなどの華のあるスターが顔を揃える。ルグランの音楽はもちろん最高だ。非凡な映像の色彩感覚、カラフルでいながらノーブルな衣装の数々、これ以上映画に何を望むのか。まさに夢のような2時間だった。
さて、この上映には通常のフィルムは使われていない。デジタル・リマスターされた画像をDLPで映写している。フィルム版をスクリーン上で観たことがないので比較は出来ないが、普通に鑑賞する限り何の違和感もない。もちろん、厳密に言えばフィルム映写の方が画質面で勝っているのだろう。だが、大きな劇場ではともかく本作を鑑賞したシネテリエ天神のようなミニシアターでは、その差は少ないと予想する。おそらくは予算的にもDLP映写は有利と思われ、今後は普及していくのかもしれない。
しかし、一般家庭でもDLPプロジェクターと120インチ以上のスクリーン及びそれなりの音響装置を揃えることは(数百万円は掛かるが)可能だ。そしてブルーレイディスクならば画質はかなりの水準まで追い込める。この状況で如何にして映画館ならではのアドバンテージを獲得してゆくか、それは今後の課題だろう。