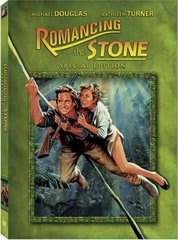2000年作品。第53回カンヌ国際映画祭にて国際批評家連盟賞とエキュメニック賞を受賞し、その長大な上映時間と独特の映像も相まって、封切り当時は話題になった映画だ。個人的には諸手を挙げての賞賛は出来ないが、作品の佇まいには惹かれるものを感じる。
福岡県のある町で凄惨なバスジャック事件が起こり、運転手の沢井と中学生の直樹と小学生の梢の兄妹だけが生き残る。それから2年後、心に傷を負ったまま彷徨っていた沢井は久々にその町に帰り直樹と梢を訪ねるが、彼らの家庭は崩壊して家にいるのは2人だけだった。そのまま家に居着いた沢井は、兄妹の従兄の秋彦と共に奇妙な共同生活を始める。

その頃、町では連続通り魔殺人事件が発生していた。暗い過去を持つ沢井を疑う者も少なくなく、それを振り切るように彼は小さなバスを手に入れると、直樹たちと旅に出る。しかし、彼らの行く先々で殺人事件が起こる。
沢井と幼い兄妹の価値観にはまったく賛同できないし、理解しようとも思わない。誰が何と言おうと、私は一般的な社会常識をわきまえた秋彦の側の人間だ。そもそも女性連続殺人事件のエピソードが必要だったのか大いに疑問であり、全体的な作劇のバランスを崩しているとも言える。しかしそれでもこの映画は観る価値がある。
青山真治監督の淡々とした演出タッチ。“クロマティックB&W”と呼ばれるセピア調の画面処理。美しいカメラワーク。3時間37分もの上映時間が醸し出す、ゆったりとした心象への旅の雰囲気が捨てがたい魅力を発している。悠然とした時の流れを映像化するには、この長さは不可欠だったのだろう。短縮版は作る必要はない。
沢井を演じる役所広司のパフォーマンスは狂気と正気との移ろいを感じさせて見応えがある。彼と国生さゆり扮する妻の別れのシーン(ロケ地は西中洲のエスカイヤクラブ ^^;)も泣かされた。直樹を演じるのは宮崎将だが、梢役の宮崎あおいの存在感が目立っており、本作以降は彼女の“快進撃”が始まる(笑)。アルバート・アイラーとジム・オルークによる挿入曲が効果的。たぶん十数年後に出所する通り魔殺人事件の犯人は、青山真治監督のデビュー作「Helpless」(96年)の光石研のように破滅への道を辿るのだろう。
福岡県のある町で凄惨なバスジャック事件が起こり、運転手の沢井と中学生の直樹と小学生の梢の兄妹だけが生き残る。それから2年後、心に傷を負ったまま彷徨っていた沢井は久々にその町に帰り直樹と梢を訪ねるが、彼らの家庭は崩壊して家にいるのは2人だけだった。そのまま家に居着いた沢井は、兄妹の従兄の秋彦と共に奇妙な共同生活を始める。

その頃、町では連続通り魔殺人事件が発生していた。暗い過去を持つ沢井を疑う者も少なくなく、それを振り切るように彼は小さなバスを手に入れると、直樹たちと旅に出る。しかし、彼らの行く先々で殺人事件が起こる。
沢井と幼い兄妹の価値観にはまったく賛同できないし、理解しようとも思わない。誰が何と言おうと、私は一般的な社会常識をわきまえた秋彦の側の人間だ。そもそも女性連続殺人事件のエピソードが必要だったのか大いに疑問であり、全体的な作劇のバランスを崩しているとも言える。しかしそれでもこの映画は観る価値がある。
青山真治監督の淡々とした演出タッチ。“クロマティックB&W”と呼ばれるセピア調の画面処理。美しいカメラワーク。3時間37分もの上映時間が醸し出す、ゆったりとした心象への旅の雰囲気が捨てがたい魅力を発している。悠然とした時の流れを映像化するには、この長さは不可欠だったのだろう。短縮版は作る必要はない。
沢井を演じる役所広司のパフォーマンスは狂気と正気との移ろいを感じさせて見応えがある。彼と国生さゆり扮する妻の別れのシーン(ロケ地は西中洲のエスカイヤクラブ ^^;)も泣かされた。直樹を演じるのは宮崎将だが、梢役の宮崎あおいの存在感が目立っており、本作以降は彼女の“快進撃”が始まる(笑)。アルバート・アイラーとジム・オルークによる挿入曲が効果的。たぶん十数年後に出所する通り魔殺人事件の犯人は、青山真治監督のデビュー作「Helpless」(96年)の光石研のように破滅への道を辿るのだろう。