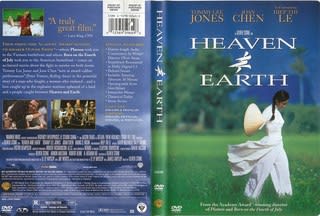(原題:La vie d'Adele - Chapitres 1 et 2 )薄味で、なおかつ上映時間が無駄に長い。第66回カンヌ国際映画祭において大賞を獲得した作品だが、主要アワードの受賞作が必ずしも良い映画ではないことを改めて実感した次第だ。
高校生のアデルは、マジメだがいまいち面白味の無いボーイフレンドや俗っぽい話しかしないクラスメート達との距離を感じ、満たされない日々を送っていた。そんな中、彼女は町で青く髪を染めた女を見かける。相手もアデルを見つめるが、その鋭い眼差しに魅了された彼女は、その女のことしか考えられなくなる。やがて美大生である青い髪の女エマはアデルにアプローチし、二人は深い関係になる。
数年後、アデルは画家になったエマのモデルをしながら彼女と一緒に暮らしていたが、平凡な教師であるアデルと、名が売れ始めた芸術家のエマとの間に溝が出来はじめる。
同性愛を興味本位の次元から大きく逸脱させ、広範囲な共感を会得させるには、切迫した内面描写と密度の濃いドラマ運びが不可欠だ。矢崎仁司監督の「風たちの午後」やアン・リー監督の「ブロークバック・マウンテン」といった秀作にはそれらが備わっていた。ところが本作には何も無い。ゲイが単なる新奇な“ネタ”としか扱われていない。もちろん、送り手としては素材を丁寧に描いたつもりなのだろう。しかし、このあまりにも平板な作劇は、対象を深く考察しないまま製作に入ってしまったことを示すものである。
主人公二人の間には、観る者をゾクッとさせる激しいパッションは感じられない。道ならぬ恋に走ってしまうのも道理であると思わせるような、妖しい空間が現出することもない。
アデルは日常が退屈だから、何となく同性愛を体験してみたというレベルだし、エマにしてもあえてアデルを選んだ理由がハッキリとしない。せいぜいが試しに一緒に寝てみたら思いのほか相性が良かったので、そのままズルズルと交際したという事情が見える程度だろうか。エマが別の女と“浮気”してどうのこうのという展開も、ありがちな話で面白くもない。
そもそも、主演の二人が魅力に乏しいのが致命的だ。アデル役のアデル・エグザルコプロスとエマに扮するレア・セドゥーは初めて見る女優だが、ルックス面でのアピールが弱い上に演技力にも見るべきものはない。アブデラティフ・ケシシュの演出はピリッとしたところがなく、アダルトビデオの真似事みたいな退屈な絡みのシーンで上映時間を水増しして3時間にも達してしまった。
劇中では数年の歳月が流れているはずなのだが、それがほとんど感じられずにいつの間にかアデルが教師になっているというドラマ運びにも、この監督の力不足が見て取れる。なお、カンヌ映画祭の審査員長はスピルバーグだった。心理描写が苦手なこの監督らしいセレクションではないかと、妙に納得してしまう(笑)。