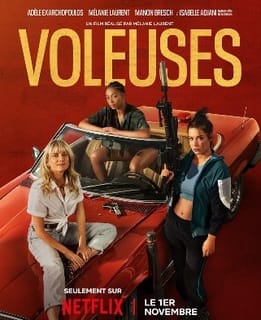性懲りも無く、2023年の個人的な映画ベストテンを勝手に発表したいと思う(^^;)。
日本映画の部
第一位 世界の終わりから
第二位 生きててごめんなさい
第三位 PERFECT DAYS
第四位 逃げきれた夢
第五位 アンダーカレント
第六位 ゴジラ-1.0
第七位 BLUE GIANT
第八位 愛にイナズマ
第九位 ハマのドン
第十位 恋のいばら

外国映画の部
第一位 エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス
第二位 SHE SAID シー・セッド その名を暴け
第三位 対峙
第四位 生きる LIVING
第五位 ジュリア(s)
第六位 アフターサン
第七位 To Leslie トゥ・レスリー
第八位 サントメール ある被告
第九位 シモーヌ フランスに最も愛された政治家
第十位 熊は、いない

2023年の映画界のトレンドワードは、ズバリ言って“マルチバース”だろう。もっとも前年までもこの概念は多用されていた。しかし、それはあくまでもハリウッド製アメコミ作品などに限った話だったと思う。つまりは荒唐無稽な設定を追い求めた結果、この新奇なネタにたどり着いたのだ。しかし2023年には、マルチバース自体を重要なドラマのモチーフとして持ち出したり、あるいはマルチバースの在り方に迫った作品が目立ってきた。日本映画の一位作品や、外国映画の一位および五位にランクインさせた作品群はその典型。特に「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」は、アメリカ映画そのものがマルチバースに突入したかのような様相を呈しており、オスカーを獲得したのも当然かと思わせた。
あと日本のエンタテインメント界で大きな話題を集めたのが、旧ジャニーズ事務所をめぐるスキャンダルだ。かなり重大な事件なのだが、この事務所の構成員は相変わらず映画やドラマに出まくっている。もしも欧米で同様なトラブルが持ち上がると、所属タレントはもちろんプロダクションごと抹消されてしまうだろう。このあたりが我が国の“後進性”を如実に示していると思う。
なお、以下の通り各賞も私の独断と偏見で選んでみた。まずは邦画の部。
監督:紀里谷和明(世界の終わりから)
脚本:山崎貴(ゴジラ-1.0)
主演男優:役所広司(PERFECT DAYS)
主演女優:杉咲花(市子)
助演男優:井浦新(アンダーカレント)
助演女優:吉本実憂(逃げきれた夢)
音楽:上原ひろみ(BLUE GIANT)
撮影:フランツ・ラスティグ(PERFECT DAYS)
新人:東野絢香(正欲)
次は洋画の部。
監督:ダン・クワン&ダニエル・シャイナート(エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス)
脚本:カズオ・イシグロ(生きる LIVING)
主演男優:ポール・メスカル(アフターサン)
主演女優:ダニエル・デッドワイラー(ティル)
助演男優:キー・ホイ・クァン(エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス)
助演女優:ジェイミー・リー・カーティス(エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス)
音楽:ロビー・ロバートソン(キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン)
撮影:ロジャー・ディーキンス(エンパイア・オブ・ライト)
新人:サッシャ・ガジェ(ザ・フラッシュ)
サラ・モンプチ(ファルコン・レイク)
フラン・クランツ監督(対峙)
毎度のことながら、ワーストテンも選んでみた(笑)。
邦画ワースト
1.月
2.銀河鉄道の父
3.首
4.アイスクリームフィーバー
5.BAD LANDS バッド・ランズ
6.春画先生
7.ほつれる
8.春に散る
9.658km、陽子の旅
10.高野豆腐店の春
洋画ワースト
1.TAR ター
2.インディ・ジョーンズと運命のダイヤル
3.キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン
4.ウーマン・トーキング 私たちの選択
5.マーベルズ
6.アダマン号に乗って
7.フェイブルマンズ
8.バビロン
9.イニシェリン島の精霊
10.ミッション:インポッシブル デッドレコニング PART ONE
邦画のワースト作品に関しては別にコメントすることは無い。とにかく例年通り“相変わらずの体たらく”である。洋画のワースト群は、やっぱり有名アワードを獲得したり、あるいは候補になった作品が必ずしも良い映画とは限らないということに尽きる。あと気になるのが、ハリウッド映画の上映時間が意味も無く長くなりつつあるということ。サブスク配信サービスに対する“配慮”なのかもしれないが、あまりホメられた話ではない。
ローカルな話題としては、福岡コ・クリエイティブ国際映画祭の発足があげられる。もっとも私はこのイベントには足を運べなかったのだが(汗)、2021年に終了したアジアフォーカス福岡国際映画祭の後継として発展することを願いたい。2024年にも開催されれば、観に行くつもりである。
日本映画の部
第一位 世界の終わりから
第二位 生きててごめんなさい
第三位 PERFECT DAYS
第四位 逃げきれた夢
第五位 アンダーカレント
第六位 ゴジラ-1.0
第七位 BLUE GIANT
第八位 愛にイナズマ
第九位 ハマのドン
第十位 恋のいばら

外国映画の部
第一位 エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス
第二位 SHE SAID シー・セッド その名を暴け
第三位 対峙
第四位 生きる LIVING
第五位 ジュリア(s)
第六位 アフターサン
第七位 To Leslie トゥ・レスリー
第八位 サントメール ある被告
第九位 シモーヌ フランスに最も愛された政治家
第十位 熊は、いない

2023年の映画界のトレンドワードは、ズバリ言って“マルチバース”だろう。もっとも前年までもこの概念は多用されていた。しかし、それはあくまでもハリウッド製アメコミ作品などに限った話だったと思う。つまりは荒唐無稽な設定を追い求めた結果、この新奇なネタにたどり着いたのだ。しかし2023年には、マルチバース自体を重要なドラマのモチーフとして持ち出したり、あるいはマルチバースの在り方に迫った作品が目立ってきた。日本映画の一位作品や、外国映画の一位および五位にランクインさせた作品群はその典型。特に「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」は、アメリカ映画そのものがマルチバースに突入したかのような様相を呈しており、オスカーを獲得したのも当然かと思わせた。
あと日本のエンタテインメント界で大きな話題を集めたのが、旧ジャニーズ事務所をめぐるスキャンダルだ。かなり重大な事件なのだが、この事務所の構成員は相変わらず映画やドラマに出まくっている。もしも欧米で同様なトラブルが持ち上がると、所属タレントはもちろんプロダクションごと抹消されてしまうだろう。このあたりが我が国の“後進性”を如実に示していると思う。
なお、以下の通り各賞も私の独断と偏見で選んでみた。まずは邦画の部。
監督:紀里谷和明(世界の終わりから)
脚本:山崎貴(ゴジラ-1.0)
主演男優:役所広司(PERFECT DAYS)
主演女優:杉咲花(市子)
助演男優:井浦新(アンダーカレント)
助演女優:吉本実憂(逃げきれた夢)
音楽:上原ひろみ(BLUE GIANT)
撮影:フランツ・ラスティグ(PERFECT DAYS)
新人:東野絢香(正欲)
次は洋画の部。
監督:ダン・クワン&ダニエル・シャイナート(エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス)
脚本:カズオ・イシグロ(生きる LIVING)
主演男優:ポール・メスカル(アフターサン)
主演女優:ダニエル・デッドワイラー(ティル)
助演男優:キー・ホイ・クァン(エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス)
助演女優:ジェイミー・リー・カーティス(エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス)
音楽:ロビー・ロバートソン(キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン)
撮影:ロジャー・ディーキンス(エンパイア・オブ・ライト)
新人:サッシャ・ガジェ(ザ・フラッシュ)
サラ・モンプチ(ファルコン・レイク)
フラン・クランツ監督(対峙)
毎度のことながら、ワーストテンも選んでみた(笑)。
邦画ワースト
1.月
2.銀河鉄道の父
3.首
4.アイスクリームフィーバー
5.BAD LANDS バッド・ランズ
6.春画先生
7.ほつれる
8.春に散る
9.658km、陽子の旅
10.高野豆腐店の春
洋画ワースト
1.TAR ター
2.インディ・ジョーンズと運命のダイヤル
3.キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン
4.ウーマン・トーキング 私たちの選択
5.マーベルズ
6.アダマン号に乗って
7.フェイブルマンズ
8.バビロン
9.イニシェリン島の精霊
10.ミッション:インポッシブル デッドレコニング PART ONE
邦画のワースト作品に関しては別にコメントすることは無い。とにかく例年通り“相変わらずの体たらく”である。洋画のワースト群は、やっぱり有名アワードを獲得したり、あるいは候補になった作品が必ずしも良い映画とは限らないということに尽きる。あと気になるのが、ハリウッド映画の上映時間が意味も無く長くなりつつあるということ。サブスク配信サービスに対する“配慮”なのかもしれないが、あまりホメられた話ではない。
ローカルな話題としては、福岡コ・クリエイティブ国際映画祭の発足があげられる。もっとも私はこのイベントには足を運べなかったのだが(汗)、2021年に終了したアジアフォーカス福岡国際映画祭の後継として発展することを願いたい。2024年にも開催されれば、観に行くつもりである。