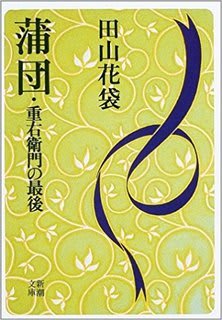面白くない。一番の敗因は、漫才を題材にしているにも関わらず、肝心の漫才が少しも笑えないことだ。主人公達だけではなく、周りの芸人のネタも全然ウケない。本職の芸人もキャスティングされているのに、この体たらく。それはひとえに、ネタの内容の精査と見せ方を工夫することを作者が怠っているためだろう。ならば漫才以外の場面は良く出来ているのかというと、それも違う。とにかく弛緩した時間が流れるだけの、観て損したと思えるシャシンだった。
高城ヒトミと本田アカコによる漫才コンビ“アカコとヒトミ”は結成5年目を迎えても、ほとんど売れていない。小さなライヴハウスで少ない観客を相手にする日々を送るのみだ。だが、少しずつマネージャーの尽力が功を奏し、2人にチャンスが舞い込むようになる。バラエティ番組に初出演が決まり、舞台のポスターの表示も大きくなる。しかし、元より生い立ちや芸に対するスタンスも違う2人の間に、大きな溝が出来始める。山本幸久の同名小説(私は未読)の映画化だ。
主人公達のキャラクターが気に入らない。何より、どうして漫才師になりたかったのか、その背景が見えない。学園祭のアトラクションで少しばかりウケた程度で、芸人という不安定な世界に飛び込めるとは思えないのだ。2人は“ボケとツッコミ”という役割分担こそあるが、基本的にあまり違いは無いように思える。つまり、どちらも気難しくてヘタレで“付き合いきれない女”なのである。
劇中で登場人物の一人から“辞めるのと逃げるのは違う”というセリフが発せられるが、彼女達は何かと理由を付けて逃げようとしているとしか思えない。これは周囲の若造連中も同様で、いずれも人生に対して及び腰だ。こんな者達が画面上をウロウロしてているだけでは、全然盛り上がらない。
飯塚健の演出は平板でキレもコクも無く、目新しさを出そうと時制をバラバラにしてシークエンスを組み立てようとするが、これが上手くいっておらず、観ていて鬱陶しい限りである。
主演は清水富美加と松井玲奈だが、映画内の設定としては27,8歳ながら、2人の実年齢も見た目もそれより若いので、かなり違和感がある。それでも演技の勘の良さでは定評のある清水はまだ良いとして、松井のパフォーマンスはいただけない。悪ぶってギャーギャー騒ぐだけでは“演技”にはならないのだ(ハッキリ言って、AKB一派は映画に出ないで欲しい)。
落合モトキや荒井敦史、浜野謙太、前野朋哉といった脇のキャストも精彩が無い。良かったのは諏訪太朗や岩松了といったベテラン陣だけだ。それにしても、ラストに流れる楽曲の凡庸なこと。映画自体が低調ならば、せめて音楽だけでもキチンとして欲しかった。