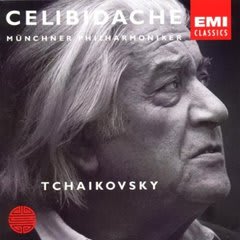地域伝統芸能の存在意義について考えたくなる一編だ。長野県の小さな山村・大鹿村。この村には300年以上続いてきた伝統の行事・大鹿歌舞伎がある。ここで鹿肉の料理店を営む風祭善は長年その歌舞伎の主役を演じてきたが、18年前に妻が仕事仲間の治と“駆け落ち”してしまい、今では寂しい一人暮らしだ。ところがある日、妻と駆け落ち相手が村に帰ってくる。妻は認知症を患っており、持て余した治は善にカミさんを“返しに”きたのだった。
トラブルの元は善とその妻の問題だけではなかった。善が雇い入れたアルバイトの若者は、人当たりは良いがワケありで、大きな悩みを抱えている。村はリニア新幹線の誘致で賛否両論乱れ飛んでおり、もちろん過疎地としての課題を抱えている。
しかし、このようにミクロ的にもマクロ的にも問題が噴出しているのは、現代に限った話ではない。いずれの時代においても、人々は悩み社会問題は存在していたのだ。放っておけば各個人も共同体もバラバラになってしまう。本作は“それを阻止するのが地域伝統芸能なのだ!”と言い切っているようだ。
どんなゴタゴタを抱えていても、大鹿歌舞伎のシーズンになると人々は結束し、トラブルはひとまず棚上げされ、一致団結してイベントを成功させようとする。そしてそれが終わると人心はリセット状態になり、新たな気持ちでまた問題に向き合うのだ。本作の送り手は、そんな構図に(映画を含めた)芸能の原初的な姿を投影したのだろう。
この映画は原田芳雄の遺作になってしまった。まさに鬼気迫る熱演・・・・と言いたいところだが、最後の仕事になってもいつもの飄々とした持ち味で作劇をしっかりと支えている。さすがだ。彼のように並はずれて存在感が大きい俳優は、いてくれるだけで画面が引き締まる。企画自体も彼の提案によるものだという。
鈴木清順監督「ツィゴイネルワイゼン」での原田との共演が強烈な印象を与えた大楠道代をはじめ、岸部一徳、松たか子、佐藤浩市、石橋蓮司、瑛太、三國連太郎など配役はかなり豪華だ。これら個性の強い素材に対しオーバーアクトを極力廃して的確な業務配分を施した阪本順治の演出は、久しぶりに冴えている。ギャグの振り方も万全で、よく笑えた。
脚本担当の荒井晴彦は、阪本とのコンビ作「KT」での不調ぶりとは打って変わったスムーズな仕事を披露。山村の風情も相まって、観賞後の気分は上々である。