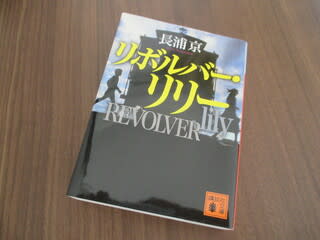同じく石井裕也監督が手掛けた「月」が本作に先立って公開されているが、この2本を観比べると石井監督の資質が明確に認識できる。前にも書いたが、彼の作風は変化球主体だ。よって、シリアスなアプローチが不可欠な時事ネタを扱った「月」などという映画は一番不向きである。対してこの「愛にイナズマ」は石井自身のオリジナル脚本であることもあって見事にオフビートな内容と手法がフィットしている。今年度の日本映画を代表する快作だ。
折村花子は映画監督になる夢を抱いて上京し、長い下積みを経てやっと劇場用長編デビュー作を撮れるチャンスが巡ってきたように思えた。しかし、悪徳プロデューサーにだまされて企画もシナリオもすべて奪われ、無一文で放り出されてしまう。そんな折、彼女は得体が知れないが何となく魅力がある舘正夫と出会って意気投合。自身の家族を題材にした映画を撮るべく、正夫と共に約10年ぶりに実家を訪れる。花子は音信不通だった2人の兄と父親を交えてカメラを回すのだが、父親の治はある秘密を抱えていた。

花子は映画製作一筋という、この年代の女子にしてはまあ変わったタイプなのだが、そんな彼女がマトモに見えるほど周りのキャラクターがキテレツだ。得体の知れない愛嬌めいたものがある正夫をはじめ、世間慣れしていることを世間離れするほどに自慢している長男の誠一と、性格がちょっとアレなのになぜか聖職者として教会に勤めている次男の雄二、そして治は地元では有名な暴れん坊だ。なお、花子たちの母親はとうの昔にヨソの男と一緒に家を出ている。
この“どうしようもない家族”に向かってカメラを回す花子だが、そんなイレギュラーな面々を描いていると、不思議なことに本来の家族の絆がペーソスたっぷりに活写されてくるあたりが玄妙だ。治の置かれた立場と、それに対峙する子供たち(および正夫)の関係性が浮かび上がり、終盤には感動巨編になってしまう。
この、変化球の連投の中に時折ストレートを織り込むという石井監督の得意技が活かされるには、「月」のようなシリアスな原作ものではなく、自身が企画・脚本まで手が掛ける本作が的確だろう。散りばめられたギャグも鮮やかに決まり、2時間半近い長い尺もテンポの良い演出で気にならない。主演の松岡茉優は若手屈指の実力派だけあり、大熱演を繰り広げながら絶対にオーバーアクトにならないクレバーさには脱帽だ。
正夫役の窪田正孝、兄たちに扮する池松壮亮と若葉竜也、そして治を演じる佐藤浩市ら、皆さすがの“腹芸”を見せる。加えて仲野太賀にMEGUMI、三浦貴大も怪演を披露し、趣里や高良健吾をチョイ役で起用するという贅沢な御膳立ても見逃せない。主な舞台になる海沿いの街はロケ地はどこか分からないが、そのローカル色豊かな佇まいには感心した。
折村花子は映画監督になる夢を抱いて上京し、長い下積みを経てやっと劇場用長編デビュー作を撮れるチャンスが巡ってきたように思えた。しかし、悪徳プロデューサーにだまされて企画もシナリオもすべて奪われ、無一文で放り出されてしまう。そんな折、彼女は得体が知れないが何となく魅力がある舘正夫と出会って意気投合。自身の家族を題材にした映画を撮るべく、正夫と共に約10年ぶりに実家を訪れる。花子は音信不通だった2人の兄と父親を交えてカメラを回すのだが、父親の治はある秘密を抱えていた。

花子は映画製作一筋という、この年代の女子にしてはまあ変わったタイプなのだが、そんな彼女がマトモに見えるほど周りのキャラクターがキテレツだ。得体の知れない愛嬌めいたものがある正夫をはじめ、世間慣れしていることを世間離れするほどに自慢している長男の誠一と、性格がちょっとアレなのになぜか聖職者として教会に勤めている次男の雄二、そして治は地元では有名な暴れん坊だ。なお、花子たちの母親はとうの昔にヨソの男と一緒に家を出ている。
この“どうしようもない家族”に向かってカメラを回す花子だが、そんなイレギュラーな面々を描いていると、不思議なことに本来の家族の絆がペーソスたっぷりに活写されてくるあたりが玄妙だ。治の置かれた立場と、それに対峙する子供たち(および正夫)の関係性が浮かび上がり、終盤には感動巨編になってしまう。
この、変化球の連投の中に時折ストレートを織り込むという石井監督の得意技が活かされるには、「月」のようなシリアスな原作ものではなく、自身が企画・脚本まで手が掛ける本作が的確だろう。散りばめられたギャグも鮮やかに決まり、2時間半近い長い尺もテンポの良い演出で気にならない。主演の松岡茉優は若手屈指の実力派だけあり、大熱演を繰り広げながら絶対にオーバーアクトにならないクレバーさには脱帽だ。
正夫役の窪田正孝、兄たちに扮する池松壮亮と若葉竜也、そして治を演じる佐藤浩市ら、皆さすがの“腹芸”を見せる。加えて仲野太賀にMEGUMI、三浦貴大も怪演を披露し、趣里や高良健吾をチョイ役で起用するという贅沢な御膳立ても見逃せない。主な舞台になる海沿いの街はロケ地はどこか分からないが、そのローカル色豊かな佇まいには感心した。