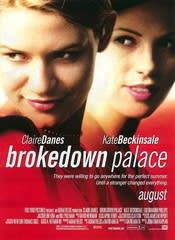(原題:Thirteen Days )2000年作品。楽しめる映画だ。公開当時は“出来事が乱発的に発生し、ドラマの核心が見えない。もっと脚本を絞るべきだ”という評も散見されたようだが、歴史的事実を実録的に描くためにはヘタにエピソードを一点に収束させると全体像が見えなくなる。そもそも歴史とは重層的・多面的なものであり、その多面性をそのままリアルな形で押し出したこの映画の方法は正解である。
1962年10月、ソ連がキューバに核兵器を持ち込んだという知らせがホワイトハウスに届く。時の大統領であったケネディは、直ちに緊急の危機管理チームである国家安全保障会議緊急執行委員会(エクスコム)を設置。討議を進めるが、閣僚の間では“空爆すべし”との強硬論が支配的であった。

しかし、ヘタに軍事行動を起こすと第三次世界大戦の勃発につながる危険がある。何としてもそれは避けたい大統領は、弟の司法長官ロバートや親友の大統領特別補佐官ケネス・オドネルらと共に、平和的解決の方法を探る。が、それでもキューバのミサイルは発射準備を整えつつあり、大統領は最後の決断を迫られる。キューバ危機に揺れた13日間を描く実録サスペンス編だ。
キューバ危機の全貌が過不足無く描かれ、歴史好きの観客にアピールすると共に、劇中ほとんどの画面を占める政府閣僚たちの深刻そうな面相のオンパレードは、いかにも“男のドラマ、硬派の映画”という雰囲気を盛り上げて壮観だ。立場や主張はどうあれ、登場人物たちが皆“世界レベルの危機を回避するのだ”という使命感に燃えている様子がありありと見える。
ひるがえって我が日本の現状を見るとお寒い限りだ。既得権益分野からの雑音や近隣諸国に対する過剰な気兼ねにより、国益をメインにした求心力をほとんど発揮できないのだから(タメ息)。一時期騒がれた集団的自衛権の問題も、話が空理空論の方向に行ってしまい、具体的な国防のあり方に対して政府関係者は何一つ言及できなかったのには呆れたものだ。
オドネルを演じたケヴィン・コスナーは38歳という設定には無理はあるものの(笑)、まずは手堅い好演。大統領役のブルース・グリーンウッド、司法長官に扮したスティーヴン・カルプ、いずれもシッカリとした仕事ぶりだ。ロジャー・ドナルドソンの演出は実に堅牢で、弛緩した部分が見当たらない。トレヴァー・ジョーンズの音楽も効果的で、これは当時を代表するアメリカ映画の佳篇だと思う。
1962年10月、ソ連がキューバに核兵器を持ち込んだという知らせがホワイトハウスに届く。時の大統領であったケネディは、直ちに緊急の危機管理チームである国家安全保障会議緊急執行委員会(エクスコム)を設置。討議を進めるが、閣僚の間では“空爆すべし”との強硬論が支配的であった。

しかし、ヘタに軍事行動を起こすと第三次世界大戦の勃発につながる危険がある。何としてもそれは避けたい大統領は、弟の司法長官ロバートや親友の大統領特別補佐官ケネス・オドネルらと共に、平和的解決の方法を探る。が、それでもキューバのミサイルは発射準備を整えつつあり、大統領は最後の決断を迫られる。キューバ危機に揺れた13日間を描く実録サスペンス編だ。
キューバ危機の全貌が過不足無く描かれ、歴史好きの観客にアピールすると共に、劇中ほとんどの画面を占める政府閣僚たちの深刻そうな面相のオンパレードは、いかにも“男のドラマ、硬派の映画”という雰囲気を盛り上げて壮観だ。立場や主張はどうあれ、登場人物たちが皆“世界レベルの危機を回避するのだ”という使命感に燃えている様子がありありと見える。
ひるがえって我が日本の現状を見るとお寒い限りだ。既得権益分野からの雑音や近隣諸国に対する過剰な気兼ねにより、国益をメインにした求心力をほとんど発揮できないのだから(タメ息)。一時期騒がれた集団的自衛権の問題も、話が空理空論の方向に行ってしまい、具体的な国防のあり方に対して政府関係者は何一つ言及できなかったのには呆れたものだ。
オドネルを演じたケヴィン・コスナーは38歳という設定には無理はあるものの(笑)、まずは手堅い好演。大統領役のブルース・グリーンウッド、司法長官に扮したスティーヴン・カルプ、いずれもシッカリとした仕事ぶりだ。ロジャー・ドナルドソンの演出は実に堅牢で、弛緩した部分が見当たらない。トレヴァー・ジョーンズの音楽も効果的で、これは当時を代表するアメリカ映画の佳篇だと思う。