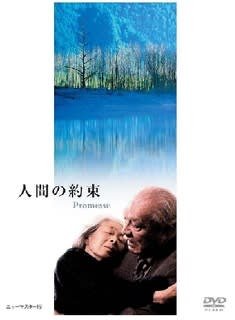(原題:THE PERFECT FIND)2024年6月よりNetflixから配信された黒人キャスト中心のラブコメ編。率直に言って、映画の内容は少しも面白くない。気合いの入らない筋書きが、メリハリの無い演出に乗って漫然と流れるだけ。しかし、観て損したかというと、断じてそうではない。本作の“外観”は、中身の密度の低さを補って余りあるほど魅力的だ。こういう映画の楽しみ方も、たまには良いものである。
ニューヨークのファッション業界で腕を振るっていたジェナは、事情があって長らく一線を退いていた。そのブランクを経て、やっとファッション編集者として復帰した彼女はある日、パーティーで出会った年下の青年エリクと仲良くなる。ところが後日、その彼は新しい職場の同僚であることが判明。しかもエリクは上司であるダーシーの息子だった。途端に上役との関係はぎこちないものになり、ジェナの復帰計画に暗雲が立ち込める。
そもそも、いくらジェナが年齢の割にチャーミングでナイスなルックスの持ち主とはいえ、エリクみたいな若い男と簡単に懇ろになるとは思えない。実際、ジェナに扮するガブリエル・ユニオンとエリク役のキース・パワーズも、30歳以上もの年齢差がある。しかも終盤にはジェナが妊娠してどうのこうのというネタまで用意されており、さすがにそれは無理があろう。
また、エリクがダーシーの息子だという取って付けたようなモチーフには我慢できても、そこからドラマティックな展開に繋がるわけでもなく、何やら微温的なハナシが漫然と続くのみ。ジェナには個性が強そうな友人が複数いるが、それらが本筋に大きく絡んでくることも無い。ラストなんて、観ている側は“いつの間にそうなったんだ?”と呟くしかない状態だ。ヌーマ・ペリエの演出はどうもピリッとしない。
しかし、アミット・ガジワニによる衣装デザインと、美術担当のサリー・レビの仕事ぶりは目を見張るほどヴォルテージが高いのだ。センス抜群のオープニング・タイトルから始まり、カラフルな街中の風景、そして登場人物たちが身に纏う服のクォリティの高さには感心するしかない。結果、あまり気を悪くせずに鑑賞を終えることが出来た。
まあ、映画館でカネを払って観るのは厳しいレベルだが、配信による視聴ならば許せる。主演のユニオンとパワーズの他にも、アイシャ・ハインズにD・B・ウッドサイド、ラ・ラ・アンソニー、ジーナ・トーレスと、馴染みは無いが“絵になる”キャストが揃っている。アマンダ・ジョーンズによる音楽と既成曲の扱いも万全だ。