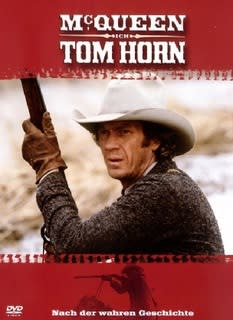いわゆる“ご当地映画”であり、多大な期待を寄せるのは筋違いであることは分かる。ストーリーはもちろんキャラクター設定も予定調和であり、大仰なメッセージ性やドラマティックな展開とは無縁である。ならば全然面白くないのかというと、そうでもない。たまにはこういうマッタリとした雰囲気に身を置くのも悪くは無いと思わせる。ローカル色豊かな点も捨てがたい。
主人公の向田康彦は、福岡県南部の地方都市で妻の恭子と小さな理髪店を営んでいる。ある日、東京で働いていた息子の和昌が突然帰郷する。勤めていた会社が肌に合わず辞めてきたらしい。そして、店を継ぐつもりだという。和昌は理容学校の学費を稼ぐために、近所の運送会社でバイトを始める。一方、市が主導する地域振興会議に出席した向田親子は、過疎化対策に関して住民の意見がまとまらず、前途多難であることを痛感する。そんな中、突然この町で映画のロケが敢行されることが決まり、住民たちは浮き足立つ。

奥田英朗の同名小説の映画化で、原作の舞台は北海道だが九州に置き換えられている。一応、どこの地方都市でも抱える過疎化や少子高齢化、介護問題、結婚難などの社会ネタは網羅されている。しかし、ハッキリ言ってそれらは表面的であり、深い考察は成されていない。作品のコンセプトからすれば当然のことであり、誰しも“ご当地映画”を観てヘヴィな気分になりたくはない。
よく見れば、主人公は自身もUターン組であったという屈託はあるものの、気の置けない友人が複数いて地域にも溶け込んでおり、比較的恵まれた立場にいることが分かる。現実には孤立している世帯も多いはずだし、状況はより深刻だ。そして、映画製作が当地で行なわれるという“突発的な事態”で全てが好転に向かう兆しを見せるのも都合が良すぎる。
ただし、切迫した状態に直面せずにそこそこ幸せな生活を送っている地方在住者や、作品のコンセプトを承知した上で割り切って接することが出来れば、不快な気分にならずに最後まで付き合えると思う。森岡利行の演出は目覚ましい部分は無いが、堅実な仕事だろう。康彦に扮する高橋克実は好演だが、意外なことに本作が映画初主演だ。彼のようなベテランでも、主役が回ってこないことがあるのは興味深い。
富田靖子に板尾創路、白洲迅、近藤芳正、筧美和子、根岸季衣などの他のキャストも悪くない。ロケ地の福岡県大牟田市の風情はよく出ていたし、各登場人物が話す方言もあまり違和感が無い。なお、エンディング曲としてHKT48のナンバーが突然流れて面食らってしまった。メンバーも2人出演している(運上弘菜と矢吹奈子)。まあ、考えてみれば“そっち方面”とのコラボは有り得ることだ。
主人公の向田康彦は、福岡県南部の地方都市で妻の恭子と小さな理髪店を営んでいる。ある日、東京で働いていた息子の和昌が突然帰郷する。勤めていた会社が肌に合わず辞めてきたらしい。そして、店を継ぐつもりだという。和昌は理容学校の学費を稼ぐために、近所の運送会社でバイトを始める。一方、市が主導する地域振興会議に出席した向田親子は、過疎化対策に関して住民の意見がまとまらず、前途多難であることを痛感する。そんな中、突然この町で映画のロケが敢行されることが決まり、住民たちは浮き足立つ。

奥田英朗の同名小説の映画化で、原作の舞台は北海道だが九州に置き換えられている。一応、どこの地方都市でも抱える過疎化や少子高齢化、介護問題、結婚難などの社会ネタは網羅されている。しかし、ハッキリ言ってそれらは表面的であり、深い考察は成されていない。作品のコンセプトからすれば当然のことであり、誰しも“ご当地映画”を観てヘヴィな気分になりたくはない。
よく見れば、主人公は自身もUターン組であったという屈託はあるものの、気の置けない友人が複数いて地域にも溶け込んでおり、比較的恵まれた立場にいることが分かる。現実には孤立している世帯も多いはずだし、状況はより深刻だ。そして、映画製作が当地で行なわれるという“突発的な事態”で全てが好転に向かう兆しを見せるのも都合が良すぎる。
ただし、切迫した状態に直面せずにそこそこ幸せな生活を送っている地方在住者や、作品のコンセプトを承知した上で割り切って接することが出来れば、不快な気分にならずに最後まで付き合えると思う。森岡利行の演出は目覚ましい部分は無いが、堅実な仕事だろう。康彦に扮する高橋克実は好演だが、意外なことに本作が映画初主演だ。彼のようなベテランでも、主役が回ってこないことがあるのは興味深い。
富田靖子に板尾創路、白洲迅、近藤芳正、筧美和子、根岸季衣などの他のキャストも悪くない。ロケ地の福岡県大牟田市の風情はよく出ていたし、各登場人物が話す方言もあまり違和感が無い。なお、エンディング曲としてHKT48のナンバーが突然流れて面食らってしまった。メンバーも2人出演している(運上弘菜と矢吹奈子)。まあ、考えてみれば“そっち方面”とのコラボは有り得ることだ。