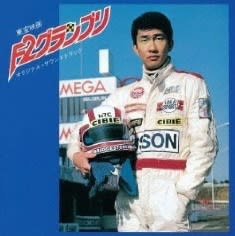(原題:FLOW)第97回米アカデミー賞では長編アニメーション賞を獲得し、世評もかなり高い映画ではあるが、個人的にはどこが良いのかサッパリ分からなかった。設定が意味不明で、展開も行き当たりばったり。アニメーション技術はハリウッドや日本の足元にも及ばず。観終わってみれば、せいぜいが“作者はかなりの猫好きなのだろう”ということしか伝わらない。正直、時間の無駄だった。
世界が大洪水に見舞われ、文明が消え失せた世界が舞台。1匹の猫が当て処もなく彷徨っている。流れてきたボートに乗り込んだ猫は、一緒に乗りあわせたカピバラやゴールデン・レトリバー、ワオキツネザルらと共に困難を乗り越えて行くというのが筋書きらしい。だが、この世界観には全く入り込めない。

出てくるのが動物ばかりで、セリフが無いということもあるが、少しは何がどうなってこういう状態になったのか、最低限度の言及はあって然るべきだ。人間が住んでいたような痕跡は散見されるものの、どう見ても人類の歴史上の遺物ではない異形のものばかり。ならばここは別の天体か、あるいはパラレルワールドなのかという想像は出来るが、映画はこちらの憶測を無視して勝手に進んでいく。
猫たちを時折襲う津波の発生要因は何なのか。そして洪水状態になったと思ったらいつの間にか水が引いていく、このメカニズムに関しての説明は無い。しかも、水害が起きたにもかかわらず水は澄んでいるという不思議。唐突に現われるヘビクイワシの群れは、果たしてドラマ上の存在意義があるのだろうか。さらには、そのうち一羽が“謎の退場”を遂げるに及び、いい加減バカバカしくなってきた。
監督はギンツ・ジルバロディスなる人物で、製作国はラトビアとフランス及びベルギー。そのせいかどうか分からないが、作画のクォリティは低い。猫の仕草こそ丁寧に扱われているが、全体的にキャラクターの仕上げが雑で、皮膚(毛並み)の質感なんか手抜きも良いところだ。
一説には猫がラトビアの立場を表現していて、他の動物は周辺諸国の暗喩だという捉え方もあるらしいが、それは牽強付会に過ぎないだろう。救いは上映時間が85分と短いことで、もしもこの調子で2時間以上も引っ張られたならば、途中退場していたかもしれない。
世界が大洪水に見舞われ、文明が消え失せた世界が舞台。1匹の猫が当て処もなく彷徨っている。流れてきたボートに乗り込んだ猫は、一緒に乗りあわせたカピバラやゴールデン・レトリバー、ワオキツネザルらと共に困難を乗り越えて行くというのが筋書きらしい。だが、この世界観には全く入り込めない。

出てくるのが動物ばかりで、セリフが無いということもあるが、少しは何がどうなってこういう状態になったのか、最低限度の言及はあって然るべきだ。人間が住んでいたような痕跡は散見されるものの、どう見ても人類の歴史上の遺物ではない異形のものばかり。ならばここは別の天体か、あるいはパラレルワールドなのかという想像は出来るが、映画はこちらの憶測を無視して勝手に進んでいく。
猫たちを時折襲う津波の発生要因は何なのか。そして洪水状態になったと思ったらいつの間にか水が引いていく、このメカニズムに関しての説明は無い。しかも、水害が起きたにもかかわらず水は澄んでいるという不思議。唐突に現われるヘビクイワシの群れは、果たしてドラマ上の存在意義があるのだろうか。さらには、そのうち一羽が“謎の退場”を遂げるに及び、いい加減バカバカしくなってきた。
監督はギンツ・ジルバロディスなる人物で、製作国はラトビアとフランス及びベルギー。そのせいかどうか分からないが、作画のクォリティは低い。猫の仕草こそ丁寧に扱われているが、全体的にキャラクターの仕上げが雑で、皮膚(毛並み)の質感なんか手抜きも良いところだ。
一説には猫がラトビアの立場を表現していて、他の動物は周辺諸国の暗喩だという捉え方もあるらしいが、それは牽強付会に過ぎないだろう。救いは上映時間が85分と短いことで、もしもこの調子で2時間以上も引っ張られたならば、途中退場していたかもしれない。