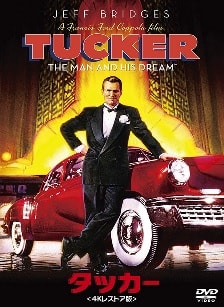(原題:ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD )終盤のバイオレンスシーンこそ盛り上がるが、それ以外は何とも要領を得ない、平板な展開に終始。しかも上映時間が2時間41分。無駄なシークエンスも多く、題材にあまり興味の無い観客は、早々にマジメに鑑賞するのを諦めてしまうだろう。
1969年のハリウッド。テレビの連続西部劇の主役で人気を得たものの、その後は悪役ばかりのリック・ダルトンは、将来に不安を抱き酒に溺れる毎日だった。そんな彼を、親友でありスタントマンのクリフ・ブースが支え続ける。リックの家の隣に越してきたのが、売り出し中の映画監督ロマン・ポランスキーと、その妻で若手女優のシャロン・テートだ。前途洋々に見える2人に対し、リックはジェラシーを覚える。
だが、脇役として出た映画でのパフォーマンスが認められ、リックはマカロニ・ウエスタンの主演者として半年間イタリアで暮らすことになる。一方、ハリウッドにはヒッピー達も入り込むようになり、中でもチャールズ・マンソン率いる“ファミリー”は不穏な動きを見せていた。
69年当時はリックみたいな境遇の俳優は少なくなかったと思われるが、それは今でも同じこと。役者稼業には“保証された確実な将来”なんてものは無い。クリフの立場はちょっと興味深いが、よく見るとリックとの関係性は十分描かれてはいない。この、あまり思ったほどキャラが立っていない2人が遭遇する出来事は、監督および脚本を担当したクエンティン・タランティーノにとっては思い入れがあるのかもしれないが、普遍性には欠ける。加えて、ドラマ運びが冗長かつメリハリが無い。盛り上がることもなく、時間ばかりが過ぎていくという感じだ。
そして最も疑問に思ったのは、アメリカン・ニュー・シネマに対する言及がほとんど無いこと。69年には「イージー・ライダー」および「明日に向って撃て!」「真夜中のカーボーイ」が作られ、「俺たちに明日はない」や「卒業」は前年までに公開済だった。タラン氏はこういった作品群には興味が無いのかもしれないが、映画ファンとしては不満が残る。
シャロン・テート事件に関するラスト近くの扱いはアッと驚く展開で、暴力描写も冴え渡っているが、ここに至る過程が退屈な小ネタの連続では、いい加減面倒くさくなる。
主演のレオナルド・ディカプリオとブラッド・ピットは、まあ“いつも通り”で、特筆するようなものはない。アル・パチーノやブルース・ダーン、カート・ラッセルといった面子も単なる“顔見せ”だ。しかし、シャロン役のマーゴット・ロビーは良かった。たぶん実際にシャロンはこういう人だったのだろうという、説得力がある。マンソンの一味に扮するマーガレット・クアリーとダコタ・ファニングも良い味を出している。
そして一番のハイライト(?)は、撮影所でリックを励ましていた子役の女優を演じたジュリア・バターズだ。現時点でまだ10歳だが、ノーブルな容貌と達者な立ち振る舞いに驚くばかり。子供の頃のD・ファニングよりもインパクトが大きい(笑)。