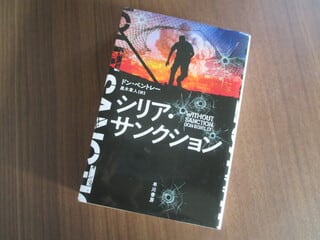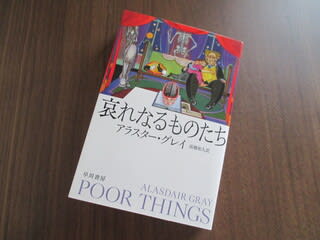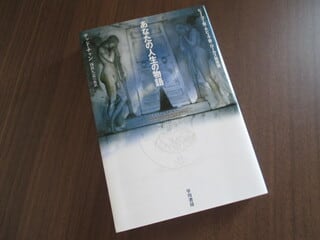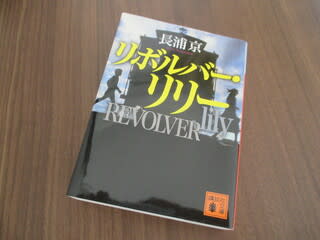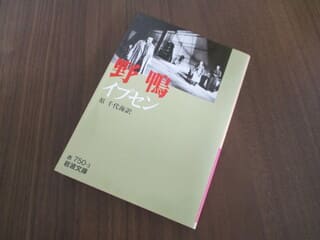アメリカの代表的なSF作家であるハインラインが、1965年から66年にかけて発表したもの。世評はかなり高く、67年のヒューゴー賞長編小説部門を受賞している。ただし、実際に読んだ感想としては芳しいものではない。とにかく長いのだ。文庫本にして670ページほどあり、しかも文面には段落が少なく、ぎっしりと書き込まれているといった案配。ならばストーリーが面白いのかといえば、起伏が少ない上に展開が遅くてアピール度は低い。正直、何度か途中で放り出そうと思ったほどだ。
2076年、人類が月へ入植者を送り込んでからかなりの時間が経過し、すでに月世界には大規模な植民地が形成されていた。ところが相変わらず地球政府にとっては月は流刑地であり、単なる資源の産出地に過ぎず、自治独立など認められていない。この状況に対して声を上げたのが、コンピュータ技師のマヌエル・ガルシア(通称マニー)と仲間たちだ。彼らは革命運動家のベルナルド・デ・ラ・パス教授を代表にして、地球側と真っ向から対立する。
各キャラクターは十分に屹立しており、筋立ても横暴な大国と搾取されるばかりの植民地との抗争という平易な様相を示しているのだが、これが一向に盛り上がらない。これはひとえに冗長な語り口と、どうでもいいモチーフが多すぎることに尽きる。あと、ひょっとしたら翻訳が上手くないのかもしれない。回りくどい言い回しが目立ち、読んでいてストレスが溜まるばかりだ。かといってわざわざ原書で読み直すほどの訴求力も感じられない。
とはいえ、興味を惹かれる箇所が2つばかりある。ひとつはマニーをフォローするスーパーコンピュータのマイクの造型だ。意志を持っており、各局面で主人公たちのピンチを救う。また、複数の“人格”を使いこなすあたりも面白い。あとひとつは月側が地球への攻撃に使う“隕石爆弾”である。同じ威力を持つ核ミサイルよりも数段安上がりで、しかも原料は無尽蔵。この仕掛けは説得力がある。
余談だが、2015年に本書はブライアン・シンガー監督によって映画化されることが発表されたらしい。しかし、その後の経過は聞かない。もっとも、シンガー自身あまり力量のある監督とは思えないので、たとえ映画製作が軌道に乗ったとしても、大して期待の持てるものではないと思う。