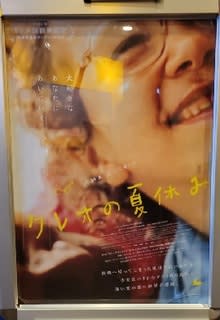(原題:DEADPOOL & WOLVERINE)20世紀FOXがディズニーに買収された件を茶化しているあたりは面白かった。ただ、それ以外はまったく楽しめない。要領を得ない話の連続で、観ているこちらはどう対応して良いか分からず、出るのは溜め息だけ。前作(2018年)のヴォルテージが高かっただけに、残念でならない。
アベンジャーズへの加入を希望したものの失敗したデッドプールことウェイド・ウィルソンは、ヒーロー業を引退して中古車セールスマンとして平穏な生活を送っていた。ウェイドの誕生日、時間変異取締局(TVA)のエージェントたちが自宅に押し入り、彼は連行されてしまう。TVA幹部のミスター・パラドックスによると、ウェイドたちが存在する時間軸において最も主要な存在だったウルヴァリンことジェームズ・“ローガン”・ハウレットが死亡したため、時間軸自体の消滅が迫っているという。

ウェイドをTVA側に引き入れた後に分岐時間軸の剪定を敢行しようとしているパラドックスに賛同できないウェイドは、パラドックスのタイム・パッドを奪うと、別のマルチバースからローガンを引っ張ってくる。これに対してパラドックスは2人を虚無の世界(ヴォイド)に転送する。
マルチバースという概念を採用してから、マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)のクォリティは低下していると思う。コアなマニアは喜ぶのかもしれないが、一般の観客は置き去りにされる。しかも、配信番組を含めた関連作品をチェックしないと分からないモチーフも遠慮会釈無く挿入され、ますます“一見さん”にとって敷居の高いシャシンになっている。
ウェイドは相変わらずの口八丁手八丁だが、前回からネタの繰り出し方もアクションのパターンも進歩しておらず、あまり盛り上がらない。終盤の“各界デッドプール全員集合”の場面も、果たして必然性があるのか疑問だ。そもそも、ウルヴァリンの話は「LOGAN/ローガン」(2017年)で区切りよく終わっていたのではなかったか。いくら多元時間軸だからといって、結了したエピソードを強引に掘り起こす筋合いなど無いと思う。
監督ショーン・レヴィの仕事ぶりは、同じくライアン・レイノルズと組んだ「フリー・ガイ」(2021年)と比べて精彩が無い。やっぱりアメコミ物などの枠組みが確定した企画では、マッチしない演出家もいるのだろう。レイノルズをはじめヒュー・ジャックマンにエマ・コリン、マシュー・マクファディン、モリーナ・バッカリンといったキャストは悪くはないのだが、作品の性格上あまり機能しているように見えない。とにかく、マルチバースというのは御都合主義と隣り合わせである。よっぽど話を練り上げないと訴求力のある映画にはならない。
アベンジャーズへの加入を希望したものの失敗したデッドプールことウェイド・ウィルソンは、ヒーロー業を引退して中古車セールスマンとして平穏な生活を送っていた。ウェイドの誕生日、時間変異取締局(TVA)のエージェントたちが自宅に押し入り、彼は連行されてしまう。TVA幹部のミスター・パラドックスによると、ウェイドたちが存在する時間軸において最も主要な存在だったウルヴァリンことジェームズ・“ローガン”・ハウレットが死亡したため、時間軸自体の消滅が迫っているという。

ウェイドをTVA側に引き入れた後に分岐時間軸の剪定を敢行しようとしているパラドックスに賛同できないウェイドは、パラドックスのタイム・パッドを奪うと、別のマルチバースからローガンを引っ張ってくる。これに対してパラドックスは2人を虚無の世界(ヴォイド)に転送する。
マルチバースという概念を採用してから、マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)のクォリティは低下していると思う。コアなマニアは喜ぶのかもしれないが、一般の観客は置き去りにされる。しかも、配信番組を含めた関連作品をチェックしないと分からないモチーフも遠慮会釈無く挿入され、ますます“一見さん”にとって敷居の高いシャシンになっている。
ウェイドは相変わらずの口八丁手八丁だが、前回からネタの繰り出し方もアクションのパターンも進歩しておらず、あまり盛り上がらない。終盤の“各界デッドプール全員集合”の場面も、果たして必然性があるのか疑問だ。そもそも、ウルヴァリンの話は「LOGAN/ローガン」(2017年)で区切りよく終わっていたのではなかったか。いくら多元時間軸だからといって、結了したエピソードを強引に掘り起こす筋合いなど無いと思う。
監督ショーン・レヴィの仕事ぶりは、同じくライアン・レイノルズと組んだ「フリー・ガイ」(2021年)と比べて精彩が無い。やっぱりアメコミ物などの枠組みが確定した企画では、マッチしない演出家もいるのだろう。レイノルズをはじめヒュー・ジャックマンにエマ・コリン、マシュー・マクファディン、モリーナ・バッカリンといったキャストは悪くはないのだが、作品の性格上あまり機能しているように見えない。とにかく、マルチバースというのは御都合主義と隣り合わせである。よっぽど話を練り上げないと訴求力のある映画にはならない。