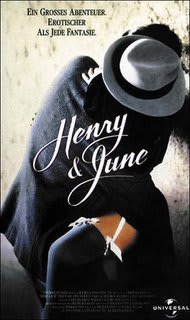(原題:SPIDER-MAN:HOMECOMING )随分と“軽い”仕上がりだ。今回からアベンジャーズ陣営に正式参加するための措置かと思ったのだが、アベンジャーズ関連作品もけっこうハードな題材を扱うこともあるので、理由はそれではないだろう。いわば“二軍扱い”の若造のエピソードに過ぎないということか。そう割り切って観れば、楽しめるかもしれない。
15歳の高校生ピーター・パーカーは、スパイダーマンとしてのパワーを身につけてからアイアンマンことトニー・スタークの経営する会社に研修生として出入りしている。とはいってもアベンジャーズの面々のように世界的な危機に対峙することは出来ず、担当する仕事は町内のトラブルを解決するぐらいだ。一方、ロキとの戦いの後始末を任されていた産廃処理会社の経営者エイドリアン・トゥームスは、トニーの意向で仕事から外されたことに納得が出来ない。腹いせにチタウリの残骸を再利用したハイテク兵器を開発し、ギャングどもに売り込むという闇稼業を始める。そして自らは怪人バルチャーとしてニューヨークの裏社会に暗躍する。トゥームスの組織の取引を偶然目撃したスパイダーマンは、トニーの忠告も無視してバルチャーとの全面対決に挑む。
ピーターがスパイダーマンになった経緯や、ベンおじさんが非業の死を遂げたことも省略されている。だからピーターの内面の屈託が全然描かれておらず、最初からチャラい野郎として出てくる。スパイダーマン作品に初めて接する観客には不親切だが、作る側は“そんな設定は誰でも分かっているじゃないか”というノリで押し切っているようだ。
このような“中身があまり無いヒーロー”が動き回る活劇編としては、そこそこ上手く出来ている。ジョン・ワッツの演出はテンポが良く、アクション場面もソツなくこなす。主役のトム・ホランドが軽量級である分、アイアンマン役のロバート・ダウニー・Jr.や、敵役のマイケル・キートン、メイおばさんに扮するマリサ・トメイといった存在感のあるキャストが適宜フォローしているという感じだ。
とはいえ、学生としてのピーターを取り巻く面子はどれもいただけない。正体を知ってしまうネッド(ジェイコブ・バタロン)はコメディ・リリーフとしてまあ良いが、 ローラ・ハリアー演じる片想い相手のリズや、ゼンデイヤ扮するMJに至っては、お手軽学園ドラマみたいな雰囲気で愉快になれない。「アメイジング・スパイダーマン」シリーズのエマ・ストーンのレベルは無理としても、もう少し魅力のある役者を引っ張ってくるべきだった。
さて、晴れてアベンジャーズの“一軍”に取り立ててもらえそうになったピーターだが、斯様なライト感覚では他のメンバーとの“格差”が気になるところ。次回以降でどのようにアプローチしてくるのか、多少の関心はある。