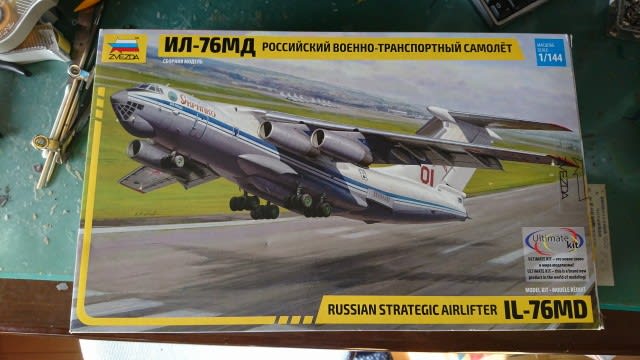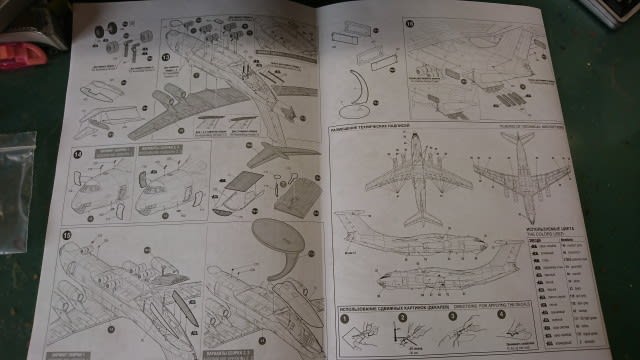引き続き屋外展示物を見て行きます。飛行機以外にも戦車も置いてあるんですね。雑な置き方をされていますが・・・。
これは
M3A3スチュアート軽戦車。ガルパンには登場してないからよく知らないですね、はい。でも劇場版で名前だけ出てきたような。
アメリカ製の戦車ですがイギリス軍でも運用されていました。スチュアートというのはイギリス軍呼称が定着したやつですね。
実戦投入もイギリス軍の車両が初めてだったんですが、ドイツ軍の戦車には敵わず速攻で第一線から撤退。それでも軽戦車ゆえの軽快性を活かして偵察車や輸送車に活路を見出したとか何とか。
一方太平洋では極東の田舎侍相手に無双していた模様。日本の機甲部隊ってホント・・・。
 ダッジWC54野戦救急車
ダッジWC54野戦救急車
1942年から生産された3/4tトラックのひとつで、WC51~WC64までの型式があります。全部で26万台造られたとかで・・・。ダッジの生産能力もおぞましいなと。
WC54は密閉式荷室を備えた野戦救急車です。そういえばビクトリアのパレードで見たかな。
 フォードM151マット
フォードM151マット
ご存知陸軍の馬車馬ことウィリスMB/M38ジープの後継車なんですが、人類の151%はM151もこれらと一緒くたにしてジープと呼んでるんじゃないのかしら。
グリルの格子が横向きになっているのに注目です。(M151は別にジープじゃないんですけど)ジープと言えば縦向きの格子がトレードマークなわけですが、これはウィリスが商標登録しているのでフォード製のM151では使えないわけです。この意匠権は所有者を転々としながら今も生きていて、ジープの車に丸目と共に現在でも採用されているのです。以上豆知識でした。
 M114装甲偵察車
M114装甲偵察車
キミ誰やねん?という車。ベトナム世代の装甲車だそうな。軽量高機動が魅力の装甲車なんですが、ベトナムで使ってみるとこれが仇になってジャングルを突き進んだりする不整地走破能力に難ありとみなされて、途中でM113と交代したそうな。失敗作ですかね・・・。
プラモデル化もされていないっぽいですし、知名度低いのね・・・。
 M4A1シャーマン中戦車
M4A1シャーマン中戦車
ご存知アメリカ軍の戦車です。車体が丸っこいのでA1型でしょう。これ好きなんですよ。
戦車系はこんなところです。
日本の戦車が置いてあるって聞いてたんですけど、はてどこかいったかな?
まあたいしたもんじゃないそうなので、特にダメージ無し。

航空機見分に戻ります。これは
ダグラスA-4Bスカイホーク(10分ぶり3機目・通算134機目)
最初の量産型です。A型は先行量産型とでも言うべきものです。給油プローブもなにもないさっぱりした外観。
 ロッキードT-33Aシューティングスター
ロッキードT-33Aシューティングスター(1日ぶり2機目・通算135機目)
ご存知、航空博物館の常連第2号です(第1号はT-6テキサン)ほんとどこにでもいるね。
アメリカを始め西側諸国で使われていた練習機です。既に何回も紹介しているので解説はいいでしょう(手抜き

T-33は機首の上下方向が絞られてないのでなんだか野暮ったいイメージがあるんですが、正面から見ると左右方向はけっこう絞られていてカッコイイなと。たぶん上から見てもかっこよく見えるはず。
 リパブリックF-84Fサンダーストリーク
リパブリックF-84Fサンダーストリーク(2時間40分ぶり2機目・通算136機目)
ヤンクスで見たF-84Eサンダージェットの改良型ということになってますが、実際のところは全くの別ものと言っていいでしょう。
当初主翼が直線翼だったサンダージェットでしたが、後退翼の性能が認められるとサンダージェットも後退翼化されたのでした。それがF-84Fなのです。ご丁寧に名前もサンダーストリークに変わっています。
ただし、主翼だけでなく胴体も微妙に形状が変わっています。風防より後ろの胴体や垂直尾翼が顕著です。もう別の機体みたいなものなんですが、サブタイプの変更で済ませています。
同様の事例はこの頃のアメリカ空軍機にはよく見られたもので、F-86DやF-94C(どっちもそのうち出てくる)もほとんど新型機でしょってくらい別ものなんですが、やはりサブタイプの変更だけです。
財布を握る議会から予算を獲得するために「これは新型機じゃなくて既存機の改良型だヨ。だから予算承認してネ」という対策をしたから・・・というのが通説になっていますが、まあ本当のところは知らんです。
ちゃんと比較用の写真を次の日に撮ってあるので比較はその時にでも。
ただ、同型機と押し通すにはもっと苦しい機体がすぐ隣にいましてね。
 リパブリックRF-84Kサンダーフラッシュ
リパブリックRF-84Kサンダーフラッシュ(20秒ぶり3機目・通算137機目)
同型機ちゃうやろ言っといて飛行機カウンターは同型機として数えているのはまあ、杓子定規に型式を基準に数える仕様なので。
上のF-84Fを偵察機にするとこうなります・・・。機首に偵察用カメラを搭載したんですが、F-84の空気取り入れ口は元来機首にあるので、これじゃ飛べません。そこで取入口を左右の主翼の根本に移して解決したのでした。でもこの口って小さいけどもちゃんとエンジン動いていたのかな?
というふうに機首と空気取り入れ口にドえらい設計変更がされていて、いくらなんでも同型機と言い張るのはムリなんじゃ・・・。
RF-84Fは700機くらいが造られたんですが、中でもここの機体はK型というちょっと特別というか珍しい個体なのです。一見地味なので私も後で気付いたのですが・・・。
K型というのはFICON計画で使うためにRF-84Fから派生した写真偵察機なのです。K型は通常のF型と異なり、風防の前にフックが付いていること、水平尾翼が下に大きく曲げられていることが挙げられます。
FICONというのはFIghter CONveyor; 戦闘機運搬の頭文字でして、要約して説明するとB-36戦略爆撃機の爆弾倉の中に戦闘機を収容して目的地の近くまで運んでしまおう、という計画でした。
当時はまだ空中給油機も無く、ジェット戦闘機の燃費は極悪ですから、航続距離が極めて短いです。そうなると、アメリカ本土からモスクワを核爆撃するため超長距離飛行するB-36を護衛する戦闘機がいなくなってしまいます。第二次世界大戦で長距離戦略爆撃には護衛の制空戦闘機が不可欠だ、というのを学んだアメリカ空軍ですから、護衛機を付けないわけにはいきません。
さて悩んだ戦略空軍がひねり出した案がそのFICONなのでした。戦闘機を爆撃機に積んで目的地の近くまで運んで空中で切り離し、迎撃に出てくる敵戦闘機をやっつけ、帰りはまた爆撃機に空中で収容して基地に帰還する・・・という魂胆でした。ガンダムかよ・・・。
最初は専用の寄生戦闘機(Parasite Fighter)XF-85ゴブリンを開発してたんですが(これがまたすごい外見なのだ、画像検索すべし)、エンジンに羽と操縦席を付けただけのようなよくこんなので飛べるなという見た目になりました。戦闘機としての性能ではなくB-36に収められることを前提とした設計なので性能はアレでして、試作機の域を出ることはありませんでした。
それでも引っ込みのつかない戦略空軍は寄生戦闘機をF-84に変更します。さすがにB-36には収容できんので下半分がはみ出る格好になったんですが。
でも、そうは言っても数機の戦闘機を護衛に付けたところで意味なくね?というよく考えれば当たり前じゃんという答えに気付いてまた困る。
そこで攻撃任務じゃなくて偵察任務に変更。RF-84Fを改造したRF-84Kを載せることにしたのでした。機首のフックはB-36に付けられた拘束具と繋がるためのものなのです。大きく下がった水平尾翼は水平尾翼がB-36とぶつかってしまうのでそれを避けるための措置でした。
ちなみにRF-84Fは偵察機とは言え爆撃も出来たはずなので、いざとなればこれに戦術核爆弾を載せて核爆撃するつもりもあったと思われ。戦闘爆撃機であるところのF-84系列が選ばれたのもそこら辺が理由かもですね。
なおこの計画の肝と言える空中分離、空中結合ですが上手くいかなかったことの方が多かったらしく、まあそりゃそうだよねと。
後継のU-2偵察機の登場や空中給油が実用化されるとFICONはソッコーで姿を消しました。残当。ロマンはあって好きですけど、ロマン兵器って尽く実用化されんな。
長くなりましたが、そういう珍しい機体なのです。ここを含めて3機しか残っていないので、もうちょい丁寧に扱ってもいいんじゃないかと。
 ノースアメリカンFJ-3フューリー
ノースアメリカンFJ-3フューリー(1951年・138機目)
F-86セイバーのアメリカ海軍版といったところで、よく似た機体です。海軍の艦上戦闘機ですので、主翼の折りたたみ機構とアレスティングフックの設置、武装を20mm機関砲*4門に変更(この機体はなぜか片側1門ずつ塞がれているようだが)、といったところです。後は前脚が長くて離着艦時に迎え角が取れるようになってますかね。
FJ-3、つまりFJの3型は
午前中のヤンクスで見たFJ-1(つまりFJの1型)の改良型ということですが、別モノの機体です。主翼が直線翼から後退翼に変更されたのを始め胴体の形状からエンジンまで何から何まで変わってます。なので別型式(F2J)にしてもいいと思うんですけど、そこはやはり空軍と同様議会対策ということですかね?
FJ-1を開発した後、アメリカ陸軍からもFJ-1の陸軍版であるXP-86の開発を受けていたんですが、そんな中ドイツから入手した航空機の先進的データを基に主翼を後退翼に設計変更してXP-86を完成させたわけです。
これの制式版がF-86になったのですがこれの性能が良かったわけでして、海軍もF-86の艦上戦闘機版が欲しくなったのでFJ-2として採用したわけです。FJ-3はそれのエンジン換装型です。
FJ-2/3の改良型であるFJ-4も後に開発されるんですが、これもまた全く別モノという機体になっています。こいつは2日後に見るのでまたその時にでも。
F-86が外国に輸出されたこともあって割とそこら中の博物館で保存されているのと対照的に、FJは全型式合わせて1000機以上生産された割に現存機は数えるほどしか残っていません。アメリカ海軍の艦上戦闘機史の中でもFJはすっぽり抜け落ちている(F6F、F4Uの次はFJを飛び越してF9Fみたいな感じ)印象ですので、どうも地味なので残らなかったのかなと。なのでこれも見かけたらラッキーと思ってください。
現役時代の印象というのは大事で、これが薄い飛行機あるいは鉄道車両なんてのは保存されにくい傾向がありますよね。印象の強い試作機なんかは保存されやすいですが、量産型はあまり・・・という感触です。個人的には完成形である量産型を残すべきだと思うんですけどね。
 ロッキードF-104Gスターファイター
ロッキードF-104Gスターファイター(2時間40分ぶり2機目・通算139機目)
ご存知、小さい機体に大出力エンジンという迎撃戦闘機なんですが、このG型はどうしてか戦闘爆撃機として設計された機体です。しかも戦術核爆撃機・・・。
G型はアメリカでは運用されておらず、西ドイツなどNATO諸国用の輸出機でした。つーかアメリカには元から戦闘爆撃機として開発されたF-105がいるんで使う必要ないんですよね。
いざという時は核爆弾を積んだこれでソ連を火の海にするっていう運用を想定してたみたいです。滑走路が破壊された時に備えて、F-104をカタパルトから発進させる装置まであったらしいですから、いやまぁ狂ってるなと。
詳しい出自は不明ですがこの個体はベルギー空軍で使われていた機体だそうな。わざわざベルギーから運んできたのか・・・というよりはこれはアメリカからベルギーに供与された機体で、退役後返還された後にここに回ってきたということかもしれません。
屋外展示をやっつけたところで今回はここまで。
その37へ→