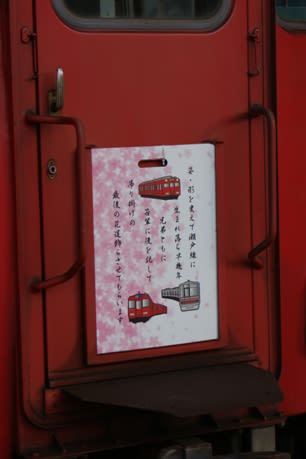今日は、地震の起こった後の下宿の様子を見に行ってきました。本当はもっと早くに行くべきだったんでしょうけど・・・。様子を見に行っただけで、すぐに実家にとんぼ返りしてきました。なので、今も実家にいます。
被害はと言うと、幸いなことに冷蔵庫と洗濯機が少しずれていただけという軽微なものでした。PCも中身のデータ的にも物理的にも吹っ飛ぶことなく、シナンジュのツノが折れるようなこともなく、フィギュアのパーツが欠けることもなく、安心しました。
さて、今回のメインはそれの前日の話です。
300系のJR東海所属車であるJ編成が消える寸前になる前にもう一度ガッツリ撮っておきたい・・・。
ということで、静岡の有名撮影地を数か所回って300系を撮影してきました。とはいっても、J編成は何十本来た新幹線のうち数本しか撮れませんでしたが。数が減っているのを改めて実感しました。
ちなみに、現在残っているJ編成は18本しかないらしく、最盛期の3割ということになります。その上に700系とN700系が大体60本ずつあるんですから、そりゃ確率も低くなるわけで。
今回は実はなかなか行かない静岡以西で撮影してきました。
まずは用宗駅のそばにある、ファンには「裏用宗」と呼ばれている場所へ向かいました。
険しい斜面を上り下りするのでちょっと危険な場所でしたね。レンズも200mmでなんとか撮影できました。

700系C23。
こんな感じに、カントの利いたいい写真が撮れます。300mmまであればもうちょい正面を強調できるんでしょうけど、これでも十分です。
それと、J編成という特定の編成を追うので、今回は系列に加えて編成番号も記してみました。

300系F1。後追いもまあまあ。
300系は300系でもこれはJR西日本所属のF編成なので、真の目標ではないんですよね。まあ、F編成もいつなくなるかわからないので撮影しておくに越したことはありません。
ところで、300系はこの後ろ姿がいいなと思っています。この面積の広いテールライトがかっこいい。700系は細すぎて認識しづらいですし(そもそもヘッドライトとは別のライトですし)、N700系は300系とほぼ同じでヘッドライトがそのままテールライトにもなる仕様ですが面積が小さいのでそれほどです。
300系みたいにヘッドライトに赤いフィルターをかけてテールライトとする車両も最近の新車では少なくなってきてちょっと残念ですね。

N700系Z18。

そして300系J57。1時間以上待ってやっと1本ってどんだけ少ないんだよという。
もう30分待ってみましたが、結局来ませんでした。次の場所にも行きたいのでこれで撤収。

用宗からさらに西へ行くんですが、次の浜松行きが40分後って、おま・・・。
東電の計画停電の影響で東海道本線の富士~浜松間は3割程度間引かれているのですが、ちょうどその間引かれた列車に当たってしまったようです。
用宗にいてもすることがないので、とりあえず10分後に来た島田行きに乗って終点の島田まで。島田で富士行きの方向幕を掲げた211系5000番台SS18を撮影します。

これの駅舎をまだ撮影していなかったので、外に出てみました。最近橋上化したのできれいですね。

しばらくたって、その40分後の浜松行きに乗車。間引き直後の列車だからなのか遅延していました。
そして、菊川駅で下車。ここから30分の行軍です。

道中にて。なんかもう夏みたいな空ですね。

そしてきました、ここです。先ほどの裏用宗は裏と言われてるだけあって知名度はそれほどですが、茶畑をバックにしたここはかなり有名ですね。
そして、いきなりきたのが300系・・・のF6。
300系の運用を調べたとしても実際来たのはF編成だったというオチもあるので、300系が来てもすぐには喜べないんですよね。てか、F編成が来る確率が明らかに高い(もっと突き詰めて調べればJ編成だけの運用もわかるんでしょうけど)。
F編成の運用数はそれほど変わらないけど、J編成のそれが700系に置き換えられているから相対的に高く感じるのかしら。

N700系Z10。

700系C36。

300系J61。J編成のラストナンバーです。まだ割ときれい。

ここでも2時間の長期戦に臨んだわけですが、次の「こだま」で撤収しようと決め、そして最後の最後に300系J56が来たんですが・・・・・・。
ちくしょうめええぇぇぇ!!
被られちゃったorz

苦し紛れに後追い。当然ながらだめだめです。
この後は新居町付近の場所へ行こうと電車に乗ろうとしたんですが、またもや間引き列車に当たってしまい、菊川駅で30分の待機。運悪いなー・・・。
しかも新居町のポイントでは、金網が設置されていて撮影不可能。ていうか以前から金網は設置されていたんですが、金網を破壊して穴を開けてそこからカメラを通して撮影していたようで。それってダメじゃんw穴が空いてたとしても躊躇うぞ・・・。今は穴の上に新たに金網を掛けているので、撮影不可能なわけです。
金網のない別のアングルからも出来たには出来たんですが、全体的にスカし気味な戦火な上に歩き続けで疲れてきたので、もう浜松で駅撮りして帰ることに。ここにはまた来るとしよう。

やってきました、浜松駅。駅撮りといっても静岡と違ってカーブしているので新鮮です。
300系はもうお約束のようにF編成。

700系C49。ただ、200mmじゃちょっと足りないようで・・・。
700系も正面から見るとかっこいいね。

最後にJ56きたあっ!
よしよし、J編成の形式写真もこれでなんとかなった。

最後に後追いしてこの日の撮影を終えました。
J編成の数は少なかったですが、それぞれの場所で一応撮影できたので一定の結果は出せたと思います。
茶畑のアレはリベンジしてみたいけど遠いからなあ・・・。
まあ、今回の撮影で700系とN700系はいやなほど撮影できたので、これら目当てに撮影に行くことは当分ないでしょうねw
被害はと言うと、幸いなことに冷蔵庫と洗濯機が少しずれていただけという軽微なものでした。PCも中身のデータ的にも物理的にも吹っ飛ぶことなく、シナンジュのツノが折れるようなこともなく、フィギュアのパーツが欠けることもなく、安心しました。
さて、今回のメインはそれの前日の話です。
300系のJR東海所属車であるJ編成が消える寸前になる前にもう一度ガッツリ撮っておきたい・・・。
ということで、静岡の有名撮影地を数か所回って300系を撮影してきました。とはいっても、J編成は何十本来た新幹線のうち数本しか撮れませんでしたが。数が減っているのを改めて実感しました。
ちなみに、現在残っているJ編成は18本しかないらしく、最盛期の3割ということになります。その上に700系とN700系が大体60本ずつあるんですから、そりゃ確率も低くなるわけで。
今回は実はなかなか行かない静岡以西で撮影してきました。
まずは用宗駅のそばにある、ファンには「裏用宗」と呼ばれている場所へ向かいました。
険しい斜面を上り下りするのでちょっと危険な場所でしたね。レンズも200mmでなんとか撮影できました。

700系C23。
こんな感じに、カントの利いたいい写真が撮れます。300mmまであればもうちょい正面を強調できるんでしょうけど、これでも十分です。
それと、J編成という特定の編成を追うので、今回は系列に加えて編成番号も記してみました。

300系F1。後追いもまあまあ。
300系は300系でもこれはJR西日本所属のF編成なので、真の目標ではないんですよね。まあ、F編成もいつなくなるかわからないので撮影しておくに越したことはありません。
ところで、300系はこの後ろ姿がいいなと思っています。この面積の広いテールライトがかっこいい。700系は細すぎて認識しづらいですし(そもそもヘッドライトとは別のライトですし)、N700系は300系とほぼ同じでヘッドライトがそのままテールライトにもなる仕様ですが面積が小さいのでそれほどです。
300系みたいにヘッドライトに赤いフィルターをかけてテールライトとする車両も最近の新車では少なくなってきてちょっと残念ですね。

N700系Z18。

そして300系J57。1時間以上待ってやっと1本ってどんだけ少ないんだよという。
もう30分待ってみましたが、結局来ませんでした。次の場所にも行きたいのでこれで撤収。

用宗からさらに西へ行くんですが、次の浜松行きが40分後って、おま・・・。
東電の計画停電の影響で東海道本線の富士~浜松間は3割程度間引かれているのですが、ちょうどその間引かれた列車に当たってしまったようです。
用宗にいてもすることがないので、とりあえず10分後に来た島田行きに乗って終点の島田まで。島田で富士行きの方向幕を掲げた211系5000番台SS18を撮影します。

これの駅舎をまだ撮影していなかったので、外に出てみました。最近橋上化したのできれいですね。

しばらくたって、その40分後の浜松行きに乗車。間引き直後の列車だからなのか遅延していました。
そして、菊川駅で下車。ここから30分の行軍です。

道中にて。なんかもう夏みたいな空ですね。

そしてきました、ここです。先ほどの裏用宗は裏と言われてるだけあって知名度はそれほどですが、茶畑をバックにしたここはかなり有名ですね。
そして、いきなりきたのが300系・・・のF6。
300系の運用を調べたとしても実際来たのはF編成だったというオチもあるので、300系が来てもすぐには喜べないんですよね。てか、F編成が来る確率が明らかに高い(もっと突き詰めて調べればJ編成だけの運用もわかるんでしょうけど)。
F編成の運用数はそれほど変わらないけど、J編成のそれが700系に置き換えられているから相対的に高く感じるのかしら。

N700系Z10。

700系C36。

300系J61。J編成のラストナンバーです。まだ割ときれい。

ここでも2時間の長期戦に臨んだわけですが、次の「こだま」で撤収しようと決め、そして最後の最後に300系J56が来たんですが・・・・・・。
ちくしょうめええぇぇぇ!!
被られちゃったorz

苦し紛れに後追い。当然ながらだめだめです。
この後は新居町付近の場所へ行こうと電車に乗ろうとしたんですが、またもや間引き列車に当たってしまい、菊川駅で30分の待機。運悪いなー・・・。
しかも新居町のポイントでは、金網が設置されていて撮影不可能。ていうか以前から金網は設置されていたんですが、金網を破壊して穴を開けてそこからカメラを通して撮影していたようで。それってダメじゃんw穴が空いてたとしても躊躇うぞ・・・。今は穴の上に新たに金網を掛けているので、撮影不可能なわけです。
金網のない別のアングルからも出来たには出来たんですが、全体的にスカし気味な戦火な上に歩き続けで疲れてきたので、もう浜松で駅撮りして帰ることに。ここにはまた来るとしよう。

やってきました、浜松駅。駅撮りといっても静岡と違ってカーブしているので新鮮です。
300系はもうお約束のようにF編成。

700系C49。ただ、200mmじゃちょっと足りないようで・・・。
700系も正面から見るとかっこいいね。

最後にJ56きたあっ!
よしよし、J編成の形式写真もこれでなんとかなった。

最後に後追いしてこの日の撮影を終えました。
J編成の数は少なかったですが、それぞれの場所で一応撮影できたので一定の結果は出せたと思います。
茶畑のアレはリベンジしてみたいけど遠いからなあ・・・。
まあ、今回の撮影で700系とN700系はいやなほど撮影できたので、これら目当てに撮影に行くことは当分ないでしょうねw